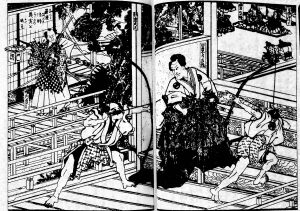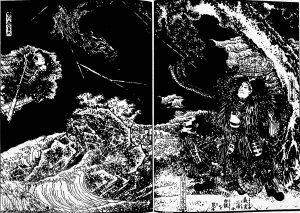◎ 幸徳秋水「社會主義神髄」(01)
3月から、「大逆事件」について、学び始めました。それに関連して、神戸での事件関係者に関する講座にも通っています。幸徳秋水の主要著作も、現代語訳もむくめて電子化されたテキストも多々ありますが、案外、フリーテキストされていない作品も目に付きます。そのなかから、「社会主義神髄」をテキスト化してみました。また、章の最後に、漢詩ないし漢文の引用での締めくくりがあるので、できるだけその典拠も書いてみたいと思っています。
“Let the ruling classes trem-
ble at a Communistic revolu-
tion. The proletarians have
nothing to lose but their chains.
They have a world to win.
Working men of all countries
unite !”
【編者注】「支配階級をして共産主義革命の前に戰慄せしめよ。プロレタリヤは、自分の鎖よりほかに失ふべき何ものももたない。そして彼らは、獲得すべき全世界をもつてゐる。
萬國のプロレタリヤ團結せよ!」
(幸徳秋水・堺利彦訳「共産党宣言」末尾より・青空文庫)
自 序
『社會主義とは何ぞ』是れ我が國人の競ふて知らんと欲する所なるに似たり、而して又實に知らざる可らざる所に屬す。予は我國に於ける社會主義者の一人として、之れを知らしむるの責任あるを感ずるが故に、此の書を作れり。
近時社會主義に關する著譯の公行する者、大抵非社會主我者の手に成り往々獨斷に流れ正鵠を失す、其然らざるも或は僅に其一部を論じ、或は單に一方面を描くに過ぎず。而して浩瀚の者は却つて
煩冗に過ぎ、短簡なる者、 亦要領を得難きの憾み有り。是を以て予は本書に於て、勉めて枝葉を去り、細節に拘せず、一見明白に其大綱を了會し耍義に誘徹せしめんことを期せり。世間未だ社會主義の何たろを知らざるの士之に依て、所謂『烏眼觀』を做すことを得ぱ、幸ひ甚し。蓋し著述の推きは徒に紙吸を多からしむるに在らずして、冥に次序の體を得せしむるに在り、材料を豐にするに在らずして繁簡の中を得せしむるに在り。本書固より闘々の小册なりと雖も、而も稿を代ふること十數囘、時を費す半年の久しきに及びて遂に意に滿つる能はず、慚悦何ぞ堪へん。但だ予の不才之な奈何ともするなくして、而して江湖の社會主義を知らんとする者、益々急なるを見て、忍んで剞劂に付するを爲せり。故に本書說く所に關し、反對の意見若くば疑間を以て質さるゝの人あらば、予は喜んで更に之が答辯說明の責に任ずべし。
本書執筆の際、參照に資せしは、
MARX, K & ENGELS, F. Manifesto of the Communist Party.
MARX, K, Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production.
ENGELS, F. Socialism, Utopian and Scientific.
KIRKUP, T. An Inquiry into Socialism.
ELY, R. Socialism and Social Reform.
BLISS, W. A Handbook of Socialism.
MORRIS, W. & BAX, E. B. Socialism : its Growth and Outcome.
BLISS, W. The Encyclopedia of Social Reforms.
等の數種也。初學少年の爲めに特に之を言ふ。
明治三十六年六月
著 者
第一章 緖 論
〇クロムウエルと言ふこと勿れ、ワシントンと言ふこと勿れ、ロベスピエールと言ふこと勿かれ、若し予に質すに古今最大の革命家を以てする者あらば、予は實にゼームス・ワット其人を推さずんばあらず。彼れ夫れーたび其精緻の頭腦を鼓して、造化の祕機を捉來し、之を人間の眼前に展開するや、世界萬邦物質的生活の狀態は、俄然として爲めに一變を致せるに非ずや。嗚呼彼所謂殖產的革命の功果や眞に偉なる哉。
〇蓋し今の紡績や、織布や、鑄鐵や、印刷や、共他百般工技の器、鐵道や、汽船や、 其他白般交通の具、之を望めば恰も魅應の如く、之に就けぱ恰も山撤の如く然り。而して此等の機器の常に自在に胴使せられ、無礙に運轉せらるるもの、唯だ慧々然たる蒸氣ー吹の力に由れることを思ふ、其術何ぞ爾く巧にして其能何ぞ爾く大なるや。若し十八世紀中葉の人類を地下に起して以て今日を觀せしめば、應に呀然として駭絕驚倒すべきや必せり。況んや之に次ぐに定氣發明の奇と其應用の妙、刻々に新なるを以てするに至って、人智の窮極する所、眞に測る可らざる者有り、予は萬物の靈長の語、於是て始めて驗有るを覺ふ。
〇然れども此等機器の發明及び共改善に由て打成せる、所綱殖焼的革命の貴尙すべき所以の功果は、獨り英技の巧且つ妙なるに在らずして、實に共殖產の饒多に、其交換の利便なるに在らざる可かず。
〇蓋し近時生產カ發達の程度及比率は、其產業の種類の異なるに從って差あるが故に詳密精確の統計を得難しと雖も、而も機械が人力に代れるが爲めに、槪して著大の增加を來せるや論なし。敎授イリーは日く、或種の產業は爲めに十倍せり、或種の產業は爲めに二十倍せり、更紗の生産の如きは、優に百倍し、書籍版行の如きは優に千倍せりと。ロバート・オーエンは早く前世紀の初に於て公言して日く、五十年前六十萬人の勞働を要せるの財富は、今や僅に二千五百人の力を以て生產し得べしと。而して爾後今日に至る迄百年間、更に幾層の進步ありしや、疑ふ可らず。某學士は亦日く、近時の器械は一家五口の戶々に供するに、各々昔時六十人の奴隸の生產せしと同額の資財を以てするを得べしと。由处觀之、最近百餘年間に於て、世界の生産力が少くも平均十數倍の增加を為せるは、何人も之を斷言するに躊躇せじ。
〇而して是等僥多の財富が、世界各地に運輸され交換さるゝや、亦其自在と敏活とを極む。蜘網の如き鐵道航路は、以て坤輿を縮小すること幾千里、神經系統の如き電線は、以て萬邦を束ねてー體と為す。濠洲に屠れる羊肉は直に英人の食膳に上る可く、米國にて作れる棉花は遍く亜細亜人の體軀を纏ふ。緩急の相依り、有無の相通ずる、有史以來實に今日より盛なるは莫し。
〇嗚呼是れ實に所謂近世文明の特質也、美華也、光蟬也。吾人生れて這個文明の民たるを得て、是等空前の偉觀壯觀を仰ぐ者、竊かに自ら慶し、且つ誇るに足る有るに似たり。
〇然れども、吾人は近世文明の民たるに於て、眞に自ら慶す可き乎、眞に自ら誇る可き乎。否、是れ疑問也、然り大疑問也。
〇試みに一考せよ、近時機器の助けあるが爲めに、吾人生産の力が十借、百倍、時としては千借せることは、卽ち之れ有り。然らぱ則ち世界多數の勞働者は、殖産的革命の以前に比して、大に其勞働の時と量とを減じ得可きの理也。而も事實は之に反す、彼等は依然として永く十二一時間乃至十四五時間苛酷の勞働に服せざる可らざるは何ぞや。奇なる哉。
〇又一考せよ、近時千百借せる饒多の財富は、運輸交通の機關の助けあるが爲めに、世界の一隅より一隅に至る迄、自在敏活に分配貿易せらるゝことは、亦眞に之れ有り。然らば則ち世界多數の人類は、衣食大に餘り有りて、洋々太平を謳歌し得可きの理也。而も事實は之に反す、彼のロ糟糠だにも飽かずして、父母は飢凍し、兄弟妻子離散する者、日に益々多きを加ふるは何ぞや、奇なる哉。
〇人力の必要は省減せり、而も勞働の必要は減少せざる也。財富の生産は堪加せり、而も人類の衣食は増加せざる也。旣に勞働の苛酷に堪へず、更に衣食の匱乏に苦しむ。故を以て學校の設くる多くして、人は敎育を受くるの自由を有せざる也、交通の機關便にして、人は旅行の自由を有せざる也、醫治の術進步して、人は療養の自由を有せざる也、多數政治の制ありて、人は参政の自由を有せざる也、文藝美術發達して人は娛樂の自由を有せざる也。而して所謂近世文明の特質や、美華や、光輝や、如此にして多數人類の幸福、平和、進步に於て、果して幾何の價値有りとする乎。
〇言ふこと勿れ人は麵麴のみにして生きずと。衣食なくして何の自由あることを得る耶、何の進步あることを得る耶、何の道德あることを得る耶、何の學藝あることを得る叫。晋敬仲云へる有リ、倉廩實而知禮節と、所詮人生の第一義は卽ち衣食問題也。而も近世文明の民たる多數人類は、實に衣食の匱泛の爲めに遑々たるに非ずや。
〇言ふこと勿れ、勞働は衣食を生ずと。見よ彼の勞働せる人の子を、彼や生れて八九歲の幼時より共老衰病死に至る迄、營々として牛馬の如く驅られ、兀々として蟻蜂の如く勞す、節儉にして勤勉なる、凡そ彼等に過ぐるは莫し。而して租稅滯納の爲めに公賣の處分に遭ふ者、年々數萬を以て算せらるゝ也。而して彼の衣食常に餘りある者は、常に勞働するの人に非ずして、却て徒手逸樂遊悟の人に非ずや。
〇然れども其勞働の痛苦や、猶ほ可也、若し夫れ勞働す可き地位職業すら之を求めて寛に得ること能はざるに至ては、人生の慘事實に之より甚しきは莫し。彼や壯健の體軀を有す、彼や明敏の頭腦を有す、彼や有爲の技能を有す、而して其カ能く衣食の生產に任じて餘り有る者にして、唯だ其職業を得ざるが爲めに、終生窮途に泣き溝壑に滾轉する者、 世間果して幾萬人ぞ。
〇好し高利に衣食せよ、株券に衣食せよ、地代に衣笈せよ、租稅に衣食せよ、今の所謂文明社會に處して然る能はざる者は、則ち長時間の勞働也、苦痛也、窮乏也、無職業也、俄死也。觥死に甘んぜずんば、則ち男子は强窃盜たり、女子は醜業婦たらんのみ、墮落あるのみ、罪悪あるのみ。
〇然り今の文明や、一面に於て燦爛たる美華と光輝とを發すると同時に、一面に於て暗黑なる窮乏と罪惡とを有す。燦爛の天に翺翔する者は千萬人中僅に一人のみ、暗黒の域に滾轉する者は世界人類の大多數也。是れ豈に吾人人類の自ら誇るに足る者ならん哉。
〇烏呼世界人類の苦痛や飢凍や、日は一日より急に、月は一月より激也、人類の多數は唯だ其生活の自由と衣食の平等とを求むるが爲めに、一切の平和、幸福、進步を犧牲に供せずんば已まざらんとす。人生なる者は竟に如此き者耶、 如此くならざる可らざる耶、 耶蘇の所謂祖先の罪耶、浮屠の所謂娑婆の常耶。咄々豈に是れ眞理ならんや、正義ならんや、人道ならんや。
〇嗚呼彼の偉大なる殖產的革命の功果は、竟に人道、正義、眞理に合す可らざる乎。所謂近世文明の世界は、遂に人道、正義、眞理を現す可らざる乎。是れ個の問題や二十世紀の陌頭に立てるスヒンクスの謎語也。之を解決する者は生きん、否らずんば死せん、世界人類の運命は懸けて此一謎語に在り。
〇誰か能く之を解決する者ぞ、宗敎乎、否、敎育乎、否、法律乎、重備乎、否、否、否。
〇夫れ宗敎や以て未來の樂園を想像せしむ、未だ吾人の爲めに現在の苦痛を除き去らざる也。敎育や以て多大の智識を與ふ、未だ吾人の爲めに一日の衣食を産出せざる也。法律や能く人を責罰す、人を樂ましむるの具に非ざる也。応備や能く人を屠殺す、人を活かしむるの器に非ざる也。嗚呼、噫、誰か能く之を解決する者ぞ。
以貨財害子孫。不必操戈入室。
以學術殺後世。有如按劎伏兵。
【編者注】漢文の典拠不明、「貨財を以って子孫を害す。必らずしも戈を操り室に入る要なし。學術を以って後世を殺す、剣を按ずるの伏兵あるがごとし。」と読み下しできるだろう。『金銭の力で孫子まで害をすのに、部屋に入る必要はない、弁論で後世まで抹殺するのは剣をもった伏兵がいるようだ。』くらいの意味だろう。ご教示を待つ。)