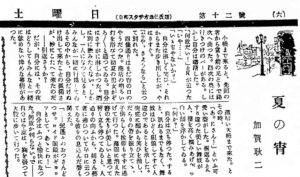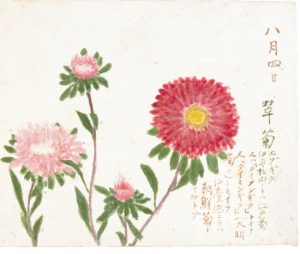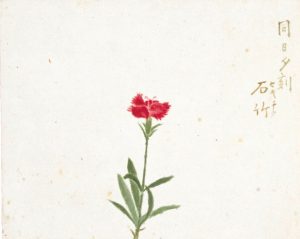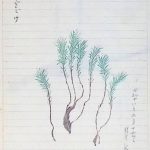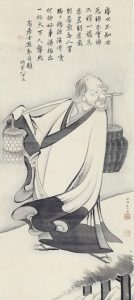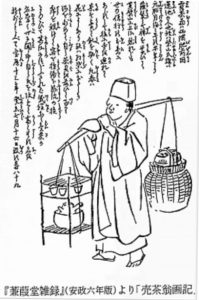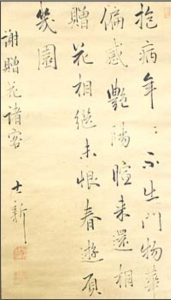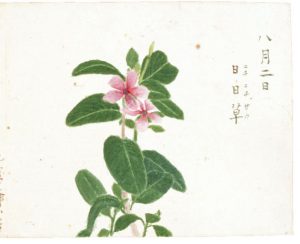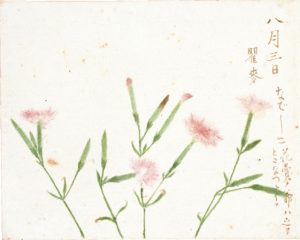◎チェーホフの手帖 神西清訳(新潮社版)(018)
「題材 ・ 断想 ・ 覚書 ・ 断片」から(続き)
編者より】
チェーホフの最晩年の三作、「谷間」「僧正」「いいなづけ」は、どれをとっても、珠玉の作品である。
ただ、前二作は、「いいなづけ」が「希望」の兆しが垣間見られたが、作品は、少しニュアンスが違う。「谷間」では、ロシアの田舎でも、「資本主義的な蓄積」がその開始時期も過ぎ、生産資本として成り立ってゆく時代の人物群像である。その代表である商人ツィブーキン家の次男の嫁、アクシーニアは、本格的な工場経営に乗り出す。その上で、長男の嫁リーバの幼子を、やや悪意を持って死なせてしまう。チェーホフは、その子を毛布にくるんで家路をたどるリーバの描写が物悲しく描いている。「僧正」では、幼い頃に別れた母親が、聖職者になった僧正ピョートルの礼拝の時も、名乗りをあげられない。その時は、ピョートルが、死の床にあった最期の時間に手を握りしめた一瞬であった。二作品で、チェーホフは、未来への展望は、一切語らない。チェーホフ的な「ペーソス」の極地であろうか?
筆致や人物造形はまったく違うが、バルザックの、前者は、貴族階級の没落をテーマとした「農民」に、後者は、聖職者としての出世が思うようにいかなかった僧侶の寂しい晩年まで描いた「ツールの司祭」にシチュエーションが似ていることが興味深く感じた。
ーーここからーー
彼は己れの卑劣さの高みから世界を見おろした。
――君の許嫁は美人だなあ!
――いやなに、僕の眼にはどんな女も同じことさ。
彼は二十万円の富籤をつづけざまに二度抽き当てることを夢想していた。二十万ではどうも少ないような気がするので。
Nは退職した四等官。田舎に住んで、齢は六十六である。教養があり、自由主義で、読書も好きなら議論も好きだ。彼は客の口から、新任の予審判事のZが片足にはスリッパを片足には長靴を穿いていることや、何とかいう婦人と内縁関係を結んでいることを聞き込む。Nは二六時ちゅうZのことを気にして、あの男は片足だけスリッパを穿いて、他人の細君と関係しているそうですな、とのべつに彼の噂話をしている。そのことばかり喋っているうちに、挙句の果には奥さんの寝間へでかけて行くようにさえなる(八年この方なかったことである)。興奮しながら相変らずZの噂をしている。とうとう中気が出て、手足が利かなくなってしまう。みんな興奮の結果である。医者が来る。すると彼をつかまえてZの話をする。医者はZを知っていて、今ではZは両足とも長靴を穿いているし(足がよくなったので)、例の婦人とも結婚したと話す。
あの世へ行ってから、この世の生活を振り返って「あれは美しい夢だった……」と思いたいものだ。
地主のNが、家令Zの子供たち――大学生と十七になる娘――を眺めながらこう思う。「あのZの奴は俺の金を贓ねている。贓ねた金で贅沢な暮しをしている。この学生も娘もそれ位のことは知ってる筈だ。もしまだ知らずにいるのなら、自分たちがちゃんとした風をしていられるのは何故かということを、是非とも知って置くべきだ。」
彼女は「妥協」という言葉が好きで、よくそれを使う。「私にはとても妥協は出来ませんわ。」……「平行六面体をした板」……。
世襲名誉公民のオジャブーシキンは、自分の先祖が当然伯爵に叙せられるだけの権利のあったことを、人に納得させようといつも懸命である。
――この途にかけちゃ、あの男は犬を食った(通暁しているの意)ものですよ。
――まあ、まあ、そんなこと仰しゃっちゃ駄目よ。家のママとても好き嫌いがひどいの。
――私、これで三度目の良人なのよ。……一番はじめのはイヴァン・マカールィチって名でしたの。……二番目はピョートル……ピョートル……忘れちゃったわ。
作家グヴォーズヂコフは、自分が大そう有名で、わが名を知らぬ者はないと思っている。S市にやって来て、或る士官と出逢う。士官は彼の手を長いこと握りしめて、さも感激したように彼の顔に見入っている。Gは嬉しくなって、こちらも熱烈に手を握り返す。……やがて士官がこう訊ねる、「あなたの管絃楽団は如何ですか? たしかあなたは楽長をしておられましたね?」
朝。――Nの口髭が紙で巻いてある。
そこで彼は、自分がどこへ行っても――どんなところへ行っても、停車場の食堂へ行ってさえ尊敬され崇拝されてるような気がしたので、従っていつも微笑を浮べながら食事をした。
鶏が歌っている。だが彼にはもはや、鶏が歌っているのではなくて、泣いているように聞える。
一家団欒の席で、大学に行っている息子がJ・J・ルソオを朗読するのを聴きながら、家長のNが心に思う、「だが何と言っても、J・J・ルソオは頸っ玉に金牌をぶら下げちゃいなかったんだ。ところが俺にはこの通りあるわい。」
Nが、大学に行っている自分の継子を連れて散々に飲み歩いた挙句、淫売宿へ行く。翌る朝、大学生は休暇が終ったので出発する。Nは送って行く。大学生が継父の不品行を咎めてお説教をやり出したので、口論になる。Nがいう、「俺は父親としてお前を呪うぞ。」「僕だってお父さんを呪います。」
医者なら来て貰う。代診だと呼んで来る。
N・N・Vは決して誰の意見にも賛成したことがない。――「左様、この天井が白いというのはまあいいとしてもですな、一たい白という色は、現在知られているところではスペクトルの七つの色から成るものです。そこでこの天井の場合でも、七つの色のうちの一つが明るすぎるか暗すぎるかして、きっかり白になってはいないという事も大いにあり得るわけです。私としては、この天井は白いという前に、ちょっと考えて見たいですな。」
彼はまるで聖像みたいな身振りをする。
――君は恋をしていますね。
――ええ、まあ幾分。
何事がもちあがっても彼は言う、「こりゃみんな坊主のせいだ。」
Fyrzikov.
Nの夢。外国旅行から帰って来る。ヴェルジボロヴォの税関で、抗弁これ努めたにも拘わらず、妻君に税をかけられる。
その自由主義者が、上着なしで食事をして、やがて寝室に引き取ったとき、私は彼の背中にズボン吊を認めた。そこで私には、この自由主義を説く俗物が、済度すべからざる町人であることがはっきり分った。
不信心者で宗教侮蔑者を以て任じているZが、こっそりとお寺の本堂で聖像を拝んでいるところを誰かに見つかった。あとでみんなからさんざん冷やかされた。
ある劇団の座長に四本煙突の巡洋艦という綽名がついている。もう四度も煙突をくぐった(身代限りをした)ので。
彼は馬鹿ではない。長いこと熱心に勉強をしたし、大学にもはいっていた。だが書くものを見るとひどい間違いがある。
ナーヂン伯爵夫人の養女は段々と倹約屋になって行った。ひどく内気で、「いいえ」とか「はい」とかしか言えない。手はいつもぶるぶる顫えている。或るとき、やもめ暮らしの県会議長から縁談があって、彼のところへ嫁に行った。やっぱり「はい」と「いいえ」で、良人にびくびくするばかりで、少しも愛情が湧かなかった。或るとき良人がとても大きな咳をしたので、彼女は動顛して、死んでしまった。
彼女が恋人に甘えて、「ねえ、鳶さん!」
Perepentiev君。
戯曲。――あなた何か滑稽なことを仰しゃいな。だってもう二十年も一緒に暮らしてるのに、しょっちゅう真面目なお話ばかりなんですもの。あたし真面目なお話は厭々ですわ。
料理女が法螺を吹く、「ワタチ女学校へ行ったのよ(彼女は巻煙草をくわえている)……地球がまんまるな訳だって知ってるわよ。」
「河船艀舟錨捜索引揚会社」。この会社の代表者が、何かの紀念祭には必ず現われて、N気取りのテーブル・スピーチをやる。そしてきっと食事をして行く。
超神秘主義。
僕が金持になったら、ひとつ後宮をこしらえて、裸のよく肥った女どもを入れとくね。尻っぺたを緑色の絵具でべたべた塗り立ててね。
内気な青年がお客に来て、その晩は泊ることになった。不意に八十ほどの聾の婆さんが灌腸器を持ってはいって来て、彼に灌腸をかけた。彼はそれがこの家のしきたりかと思ったので、大人しくしていた。翌る朝になって、それは婆さんの間違いだと分った。
姓。Verstak*.
*長い腰掛。
人間(百姓)は愚かであればあるほど、その言うことが馬にわかる。
「題材 ・ 断想 ・ 覚書 ・ 断片」(終了)