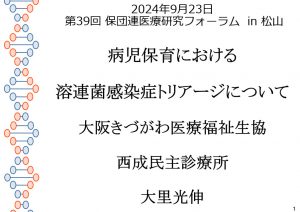◎チェーホフの手帖 神西清訳(新潮社版)(012)
小説家黒井千次は、こう書く。
く彼はひどく老い込んでから、若い女と結婚した。すると彼女はみるみる衰へて、彼とともに弱って行った。>
老い込んだ男が若い嫁をもらって若返るのではなく、衰弱していく老いた夫を見て若い妻がひとりますます艶つぼくなるのでもなく、彼女が夫とともに弱っていくというのはいささか残酷な話だ。この関係を更に煮つめればこんなところにまで来る。
く持主が死んだら、どうして樹がかうも見事に繁るもんですか?>
「年々歳々花相似、歳々年々人不同」という詩句があったけれど、チェーホフにはこの人と自然の関わりの間に所有被所有の関係をさしはさみ、樹の側から名指しで人を笑っているようなところがある。おそらく彼は、さわさわと揺れる繁茂した木の葉となって、死んだ持主を笑っているのだろう。けれどその笑いの中には、もしかしたら当の持主の名はアントン・パーヴロヴィチ・チェーホフというのかもしれないぞ、という苦い恐れもにじんでいるように思われるのだ。
しかし、こうやって「手帖」をめくりめくり楽しんでいたのではきりがない。かって読んだ折には特に目にとまらなかったのだが、今度通読してぼくが最も気に入った一行を最後に引用しておこう。
<四十五歳の女と関係して、やがて怪談を書きだした。>
実に老練な小説家らしいチェーホフと一体となった「観察」である。その他、黒井千次は「手帖」から次のような箇所を引用する。
く神経病や神経病患者の数が殖えたのぢやない。神経病に眼の肥えた医者が殖えたのだ。>
<商工業的医学>
く青年が文学界にはいって来ないといふのは、その最も優れた分子が今日では鉄道や工場や産業機関で働いてゐるからである。青年は悉く工業界に身を投じてしまった。それで今や工業の進歩はめざましいものがある。>
くXは日曜になると、スーハレフ広場へ古本を漁りに行く。「可愛いナーヂャへ。作者より」といふ献詞のついた父親の著書をみつける。>
く夫が友人たちをクリミヤの別荘へ招待する。あとで妻は、夫には黙つて勘定書をそのお客さんたちに出して、間代と食事代を受けとる。>
くボターポフは兄と親交を結んで、それが妹への恋のもとになる。妻と離別をする。やがて息子が、兎小屋のプランを送って来る。>
くNはずっと前からZに恋してゐる。ZはXに嫁ぐ。結婚後二年ほどしてZはNを訪れる。彼女は泣いて、何か話がある様子だ。てっきり夫の不平を言ひ出すのだとNは思って待ち構へる。ところがZは、Xを恋してゐることを打ち明けに来たのだった。>
では、チェーホフの手帖から
拙劣きわまる芸で、あらゆる役を片っ端から殺しつづけた女優――一生涯、死ぬまでそうだった。人気はないし、その演技は見物に怖毛をふるわせ、いい役を台無しにするのだったが、それでも七十の歳まで女優をしていた。
自分が悪いと感じる人間だけが悪人であり、従って後悔もできる。
補祭長は「疑い惑う人々」を呪う。ところが当のその連中はというと、唱歌隊席に立って、自らへの呪詛を歌っているのだ。
――スキターレツ
彼はこんなことを夢想した――妻が足腰たたずに寝込んでいる。彼は後生のために、妻の看病をする。……
マダム Gnusik*.
*鼻声。
油虫がいなくなった。この家に火事が出るぞ!『天一坊と役者たち』、『ツルゲーネフと猛虎群』――こうした論文を書くことは可能だし、また書かれることだろう。
題。――『レモンの皮』
チララ、チララ、兵隊チララ。
俺はお前の、本腹の夫だぞ!
海水浴をしていたら、波が、大洋の波がぶつかったので流産。――ヴェスヴィウスが噴火したので流産。
海と私、ほかには誰ひとりいない。――そんな気がする。
Trepykhanov*君。
*「息をはずませる」
教育。――彼のところでは、三歳になる赤ん坊が黒いフロックを着て、長靴をはいて、チョッキを着ている。
誇らしげに、「僕の出身はユーリエフ大学じゃありません、ドルパート大学ですよ!」*
*ドルパート(エストニヤ)はロシヤ名をユーリエフと言う。
その鬚は魚の尻尾に似ていた。
ユダヤ人 Tsypchik*.
*「雛っこ」の意。
笑うとき、まるで冷たい水の中にすっぽり漬かるような声を出すお嬢さん。
ママ、稲光りは何で出来てるの?
領地は厭な臭いがしている、厭な感じがしている。木々は兎にかく植えてはあるが、変てこな工合である。遥か彼方の隅の方では、番人の女房が一日じゅうお客様用の敷布などを洗濯している。――その姿は誰にも見えない。世間はこうした旦那がたに、来る日も来る日も自分たちの権利や、自分たちの高貴さについて喋らせて置くのだ。……
彼女は犬を極上のキャヴィヤで養っていた。
われわれの自尊心や自負心はヨーロッパ的だ。しかし発達程度や行動はアジヤ的だ。
黒犬――まるでオーヴァシューズを穿いているような。
ロシヤ人の抱いている唯一つの希望は、二十万ルーブルの籤を抽き当てることだ。
厭らしい女だが、子供はなかなか立派に躾けた。
人間というものは誰でも、何かしら秘しているものだ。
Nの小説の題――『ハーモニイの力』。
ああ、独身男や鰥夫男を知事に任命したらどんなにいいだろう!
あるモスクヴァの女優が、生れてこのかた七面鳥を見たことがなかった。
老人の言うことを聞いていると、愚言にあらずんば悪口である。「ママ、ペーチャはお祈りを上げなかったよ。」そこで寝ているペーチャを起こす。彼は泣き泣きお祈りを上げる。それから横になると、いいつけ口をした奴を拳で威かす。
その人物が男か女かということは、医者でなければとても分るまいと彼は思った。
一人は正教の坊主になった。もう一人は聖霊否定派の坊主になった。三人目は哲学者になった。本能的にそうなったのである。腰も伸ばさずに朝から晩まできちんと働くのが、みんなてんでに厭だったので。
「一つ胎の」という言葉が妙に好きな男。――一つ胎の私の兄さん、一つ胎の私の妻、一つ胎の婿、等々。
ドクトルNは私生児で、父親の膝下に暮したことがなく、父親のことを碌に知らなかった。幼な友達のZが案じ顔でこう告げる、「ねえ君、親父さんが淋しがっておられるぜ。病気なんだ。一目でいいから君に会えまいかと言われるのだが。」父親は『スヰス亭』という食堂を営んでいる。魚のフライをまず手づかみにして、それからフォークで扱う。ヴォトカはぷうんと下等な臭いがする。Nは出掛けて行って、店の様子を眺め、夕食を食べてみた。白髪まじりのこの肥った百姓親爺め、よくもこんなやくざな飯を商売にしやがってと腹が立っただけで、ほかにはこれという感想もなかった。ところが或るとき、夜の十二時にその家の前を通りかかって、ふっと窓を見ると、父親が背中を丸めて帳簿をつけている。その姿が自分にそっくりだった、自分の身振りに生写しだった。……
鼠色の去勢馬みたいに無能な男。
つい悪ふざけが過ぎて、そのお嬢さんに蓖麻子油を飲ませた。それでお嬢さんはお嫁に行かなかった。
Nは一生、有名な歌手や役者や文士に罵倒の手紙を書いて出した。――「恥知らずめ、よくものめのめと……」云々。署名はしないで。
彼(葬儀屋の松明担ぎ)が三角帽をかぶって、金モールのついたフロックに側条入りのズボンを穿いて現われたとき、彼女は彼を恋してしまった。
輝くばかりに明るい楽天的な性格。まるで、めそめそした連中をやっつけるために生きているような男。でっぷりして、健康で、大食である。みんな彼を愛しているが、実はそれもめそめそした連中が怖いからに過ぎない。底を割っていえば彼はつまらぬ男である、人間の屑である。ただもう食って大声で笑うだけの男である。やがて彼が死ぬ段になって一同は、彼が何一つしなかったことにやっと気がつく。彼という人間を見違えていたことに気がつく。
建物の検分が済むと、賄賂を取った委員連中は昼食に舌鼓を打った。それはまるで、喪われた彼等の名誉を追善する会食のようなものだった。
嘘をつく人は穢ならしい。
夜中の三時に彼は起される。停車場へ勤めに出るのだ。毎日毎日こうやって、もう十四年になる。
奥さんが愚痴をこぼす。「あの子に土曜日ごとに下着を更えなさいと書いてやります。すると返事に、なぜ土曜にするんですか、月曜じゃいけませんかと言って来ます。まあいいわ、では月曜にねと言ってやります。するとまた、なぜ月曜がいいのですか、火曜じゃいけませんかと言って来ます。正直ないい子ですけど、世話の焼けるったらありゃしない。」
賢者は学ぶことを好み、愚者は教うることを好む。(諺)
平僧も掌院も僧正も、その説教の相酷似せること驚くばかりだ。
人はよく、万民同胞だとか、民利だとか、勤労だとかいう問題について若いころ論争したことを思い出すものだが、本当は論争なんかやったことはついぞなく、ただ大学時代に酔態を演じたのに過ぎない。また、「学士章を着けている連中は社会の面汚しだ、曾て人間の権利のために、信教や良心の自由のために闘争した面目いまいずこにありや」などと書く。だが彼等は、一度だって闘争なんかしたことはないのだ。
領地管理人。ブキションといった型の男で、一度も主人に会ったことがない。だから、幻想に生きている。主人は定めし非常に賢い、人物のよくできた、高尚な人だろうと想像して、自分の子供達もそんな風に教育した。ところが、やがて主人がやって来たのを見ると、くだらない、了簡の狭い男だった。そこで眼も当てられぬ幻滅。
参考】
・ユリイカ「特集チェーホフ」1978年6月号 黒井千次「手帖の作家」
写真は、1885年の若きチェーホフ