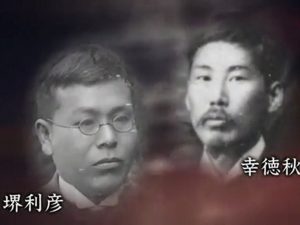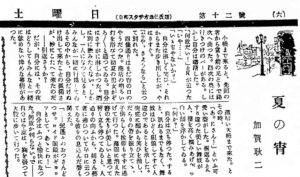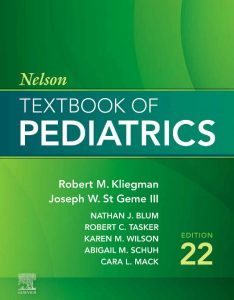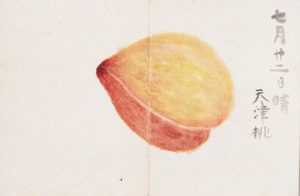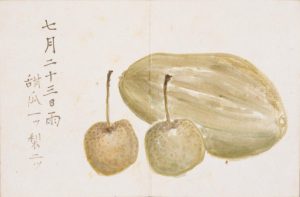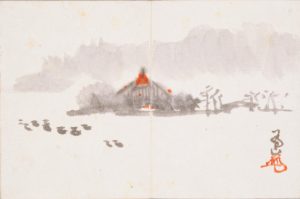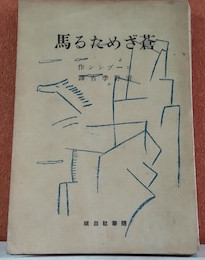◎チェーホフの手帖 神西清訳(新潮社版)(005)
新米の知事が属僚に向って演説をした。商人を集めて演説をした。女学校の卒業式で、教育の真義について演説をした。新聞の代表者に演説をした。ユダヤ人を集めて、「ユダヤ人よ、余が諸君の参集を求めたのは……。」一と月たち二た月たつが仕事の方は何一つしない。また商人を集めて演説。またユダヤ人を呼んで、「ユダヤ人よ、余が諸君の参集を求めたのは……。」みんな飽々してしまった。とうとう彼は官房の長官に言う、「いや君、こいつは俺の手に合わんよ。辞職しちまおう!」
田舎の神学校生徒が、ラテン語の糞勉強をする。半時間ごとに女中部屋へ駈け込んで、眼を細くして女中たちをつついたり抓ったりする。女中たちはキャッキャッと笑う。それからまた本に向う。彼はこれを「気分爽快法」と名づけている。
知事夫人が、例の役人を招んでチョコレートを一杯御馳走した。この声の細い男は、彼女の崇拝者だ。(胸にぶら下げた肖像)。彼はそれから一週間というもの幸福な気分を味う。彼は小金を蓄めていて、無利子でそれを貸していた。――「貴女にはお貸し出来ませんな。貴女のお婿さんがカルタで擦ってしまうでしょう。いや、それだけは御免を蒙ります。」知事の娘というのは、いつか毛皮頸巻をして劇場のボックスに納まっていた女だが、その夫がカルタに負けて官金を使い込んだのだ。鯡でヴォトカをやるのに慣れて、ついぞチョコレートというものを飲んだことのない役人は、チョコレートのお蔭で胸が悪くなる。知事夫人の顔に浮んでいる表情、「私、可愛らしいでしょう。」身仕舞いに大そうな金をかけて、それを見せびらかす機会――夜会の開催を、いつも待ち焦れている夫人だった。
妻君を連れて巴里へ行くのは、サモヴァル持参でトゥーラ*へ行くのと同じさ。
*欧露の都会。サモヴァルなどの金属手工業で有名。
インテリの地主一家の治療に招かれて、毎日その邸に通った。お金で払うのは工合が悪いので、その家では亭主へ服を一着贈ってよこして、彼女を大いに無念がらせた。長々とお茶を飲んでいる夫を見ると、彼女は癇癪が起きて来るのだった。夫と一緒に暮すうち、彼女はやつれて器量が落ちて、意地の悪い女になる。地団太を踏んで、夫をどなりつける、「あたしを離縁してお呉れ、この碌でなし!」夫が憎くてならなかった。彼女が働いて、謝礼は夫が受取るのである。彼女は県会の医員だから、謝礼を受ける訳には行かないのだ。知合いの人達が亭主の人物を見抜いて呉れず、やっぱり思想のしっかりした男だと思っているのが、彼女は忌々しかった。
青年が文学界にはいって来ないというのは、その最も優れた分子が今日では鉄道や工場や産業機関で働いているからである。青年は悉く工業界に身を投じてしまった。それで今や工業の進歩はめざましいものがある。
女がブルジョア風を吹かす家庭には、山師やぺてん師やのらくら者が育ち易い。
教授の見解。――大切なのはシェークスピヤではなく、これに加えられる註釈なり。
来るべきジェネレーションをして幸福を達せしめよ。だが彼等は、彼等の父祖が何のために生き、何のために苦しんだかを自問せねばならぬ。
愛も友情も尊敬も、何物かに対する共通の憎悪ほどには人間を団結せしめない。
十二月十三日。工場の女主人に会った。これは一家の母であり、富裕なロシヤ婦人だが、ついぞロシヤで紫丁香花を見たことがないという。
手紙の一節。――「外国にいるロシヤ人は、間諜かさもなければ馬鹿者だ。」隣の男は恋の傷手を癒しにフロレンスへ行く。だが遠くなるほど益々恋しくなるものだ。
ヤルタ*。美貌の青年が四十女に好かれる。彼の方は一向に気がなく、彼女を避けている。彼女はさんざ思い悩んだ挙句、腹立ちまぎれに彼についての飛んだ醜聞を言い触らす。
*クリミヤ半島にある避暑地。
ペトルーシャの母親は、婆さんになった今でも眼を暈どっていた。
悪徳――それは人間が背負って生れた袋である。
Bは大真面目で、自分はロシヤのモーパッサンだと言う。Sも同じ。
ユダヤ人の姓。――Chepchik*.
*小さな頭巾。
魚が逆立ちしたような令嬢。口は木の洞みたいで、つい一銭入れて見たくなる。
外国にいるロシヤ人。――男はロシヤを熱烈に愛する。女の方はじきにロシヤを忘れて一向に愛さない。
薬剤士Protior*.
*「眼を擦った」というほどの意。
RosaliaOssipovnaAromat*.
*「花咲く小薔薇」と「芳香」を組合せた女の姓名。
物を頼むには、金持よりは貧乏人の方が頼みいい。
で彼女は春をひさぐことになって、今ではベッドの上で寝る身分だった。零落した叔母さんの方は、そのベッドの足もとに小さな毛氈を敷いて臥せって、嫖客がベルを鳴らすと跳ね起きるのだった。お客が帰るとき、彼女は嬌羞を浮べて、科を作って言うのだった。
「女中にも思召しを頂かしてよ。」
そして時おり十五銭玉をせしめた。
モンテ・カルロの娼婦たち、いかにも娼婦らしいその物腰。棕櫚も娼婦みたいな感じ。よく肥った牝鶏も娼婦みたいな感じ。……
独活の大木。ペテルブルグの産婆養成所を出て助医の資格をとったNは、思想のしっかりした娘である。それが教師Xに恋した。つまり彼もやはり思想のしっかりした男で、日ごろ彼女の大いに愛読している小説ごのみの刻苦精励の人だと思ったのである。そのうち次第に、彼が酒喰いののらくら者で、お人好しの薄野呂だということが分って来た。学校を首になると、彼は女房の稼ぎを当てにして居候暮しをやりだした。まるで肉腫みたいな余計者で、彼女を搾り尽すのだった。或るとき彼女は、インテリの地主一家の治療に招かれて、毎日その邸に通った。お金で払うのは工合が悪いので、その家では亭主へ服を一着贈ってよこして、彼女を大いに無念がらせた。長々とお茶を飲んでいる夫を見ると、彼女は癇癪が起きて来るのだった。夫と一緒に暮すうち、彼女はやつれて器量が落ちて、意地の悪い女になる。地団太を踏んで、夫をどなりつける、「あたしを離縁してお呉れ、この碌でなし!」夫が憎くてならなかった。彼女が働いて、謝礼は夫が受取るのである。彼女は県会の医員だから、謝礼を受ける訳には行かないのだ。知合いの人達が亭主の人物を見抜いて呉れず、やっぱり思想のしっかりした男だと思っているのが、彼女は忌々しかった。
若い男が百万マーク蓄めて、その上に寝てピストル自殺をした。
「その女」……「僕は二十のとき結婚して以来、生涯ヴォトカ一杯飲んだことも、煙草一本喫ったこともありません。」そういう彼が他に女をこしらえると、世間の人は反って彼を愛しはじめ、今までよりも信用するようになった。街を歩いても、皆が今までより愛想よく親切になったのに彼は気づくのだった――罪を犯したばかりに。
結婚するのは、二人ともほかに身の振り方がないからである。
国民の力と救いは、懸ってそのインテリゲンツィヤにある。誠実に思想し、感受し、しかも勤労に堪えるインテリゲンツィヤに。
口髭なき男子は、口髭ある婦人に同じ。
優しい言葉で相手を征服できぬような人は、いかつい言葉でも征服はできない。
一人の賢者に対して千人の愚者があり、一の至言に対して千の愚言がある。この千が一を圧倒する。都市や村落の進歩が遅々としている所以である。大多数、つまり大衆は、常に愚かで常に圧倒的である。賢者は宜しく、大衆を教化しこれを己れの水準にまで高めるなどという希望を抛棄すべきだ。寧ろ物質力に助けを求める方がよい。鉄道、電信、電話を建設するがよい。そうすれば彼は勝利を得、生活を推し進め得るだろう。
本来の意味での立派な人間は、確乎として保守主義的な乃至は自由主義的な信念を抱く人々の間にのみ見出されるだろう。いわゆる穏健派に至っては、賞与や年金や勲章や昇給に著しく心を惹かれがちである。
――あなたの叔父さんは何で亡くなったのです?
――医者の処方はボトキン氏下剤*を十五滴となっていたのに、十六滴のんだのでね。
*極めて無害な緩下剤。
大学の文科を出たての青年が郷里の町へ帰って来る。そして教会の理事に選挙される。彼は神を信じているわけでもないが、勤行には几帳面に出て、教会や礼拝堂の前を通るときは十字を切る。そうすることが民衆にとって必要であり、ロシヤの救いはそれに懸っていると考えたからである。やがて郡会の議長に選ばれ、名誉治安判事に選ばれ、勲章を貰い、たくさんの賞牌を受けた。――さていつの間にか四十五の年も過ぎたとき、彼ははっとして、自分がこれまでずっと身振狂言をやって来たこと、道化人形の真似をして来たことを悟った。だが既に生活を変えるには晩かった。或る夜の夢に、突然まるで銃声のような声がひびいた――「君は何をしている?」彼は汗びっしょりになって撥ね起きた。