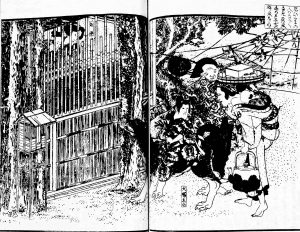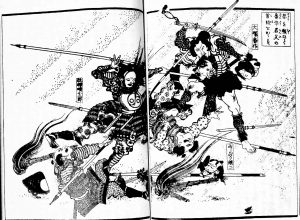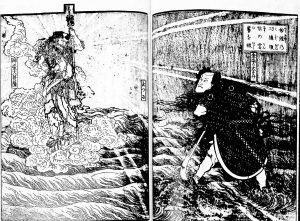◎ イプセン 原千代海訳「ヘッダ・ガーブレル」
劇作家だった宮本研氏(1926-1988)は、概ね次のようなことを言っている。
「芝居の幕は、いわば舞台装置(主に室内)の「第四の幕」である。特にイプセン以降の近代リアリズム演劇において成立した。いわば、「のぞき見」できる芸術である、そこには、おのずから前提ができあがる。観客は、のぞき見していることがばれないように、客席を暗くして、俳優ものぞき見られないが如く、独白など観客との接点を断つ。こうした約束事が近代劇にはあるのだ。」
この芝居も、定石とおりに、書き割り内部の長い描写から始まる。
ヒロインのヘッダ・ガーブレルは、一言で言えば、実に嫌な女性である。ヘッダとその夫と、その学問上および大学の地位を巡ってのライバル、かってはヘッダとまんざらでもなかった男性の三人を巡って劇は展開してゆく。ライバルが泥酔のあげく、夫を凌ぐほどの著書の原稿を紛失してしまう。その原稿を手に入れたヘッダは、ライバルの想い人への嫉妬からか、暖炉で原稿を償却してしまう。失意のあまり、ライバルは自殺してしまうが、使った拳銃は、ヘッダの所有物だった。それを知悉する判事は、ヘッダに脅迫まがいに言い寄ってゆく。万事休すのヘッダが取った行動は?
先に「嫌な女性」と記したが、尊敬する父親も含めて、夫、そのライバル、判事など、世間の男性の俗物性の「生贄」とされたのだろう。
チェーホフの「かもめ」のテーマとも重なるような気がふとした。
セリフの引用は、第三幕の最後、ヘッダが、原稿を焼くシーン。
ヘッダ あっ、ちょっと、形見の品を持っていっていただかなくちゃ!
ヘッダは書き物机へ行き、引き出しを開けて,ビストルのケ—スを取り出す。それから、このうちの一丁を手に、レェ—ヴボルクのほうへ戻ってくる。
レェ—ヴボルク (ヘッダを見て)それは!そいつを持っていけ、っていうんですか?
ヘッダ (ゆっくりうなずいて)覚えていらっしゃるでしょう? 一度はあなたを狙ったことがあるのよ。
レェ—ヴボルク あのとき、いっそ、やってくれたらよかったんだ。
ヘッダ はい !今度は、自分て使うのね。
レェーヴボルク (胸のポケットにビストルを突っ込み)ありがとう!
ヘッダ 立派によ、エイレルト・レェ—ヴ・ボルク! 約束してちょうだい!
レェーヴボルク じゃ、さようなら、ヘッダ・ガ—ブレル。工イレルト、ホールのドアから去る。
ヘッダはし,はらくの間、ドアのところで耳をすます。それから、書き物机のほうへ行き、原稿の包みを取り出す。包みの中をちょっとのぞき、はみ出している紙片を二、三引き出して、それに見入る。それから、包みを全部かかえ、ストーブのそばの肱掛け椅子に行き、腰をおろす。しばらくして、スト—ブのロを開け、包みを開く。ヘッダ (一折りの原稿を火に投げ込み、自分に言い聞かせるように、ささやく)さあ、あんたの子供を焼いてやる、テア!あんたの縮れっ毛も一緒にね!(さらに二、三帖の原稿を投げ込み)あんたの子供で、エイレルトの子供をね。(残りを投げ込み)焼いてやる、――焼いてやる、あんたの子供を。