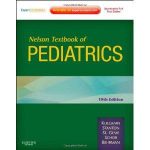◎清岡卓行、阿藤伯海とバッハ
清岡卓行の、戦時中、恩師であった漢詩人を扱った「詩礼伝家」の中に、その詩人の遺作と比べながら、以下のような一節があります。
「 バッハは死が近づいた床において、頭のなかに湧いてきた音楽、コラールの『われいま、汝の御座のまえに進みいで』を、看病してくれている婿に口述して書き取らせたが、それはいわば最後の吐息のように自然なものであったろう。絶筆と呼ぶのにまことにふさわしい構成的な作品は、やはり死の三年ほど前から書きはじめ、やがて視力恢復の希望において行った手術のかいもなく失明し、体力もすっかり衰えていた六十五歳のバッハが精魂を傾けつくしながらも、全曲のたぶん終わり近くと思われる個所で遂に中断せざるをえなかったのが大作『フーガの技法』だろう。
この地上において最も美しい音楽の一つと思われる『フーガの技法』を、オルガン、ペダルつきのチェンバロ、あるいは室内オーケストラなどのいずれで聞くにしろ、演奏が楽譜のその中断の個所で不自然にぴたりと止るとき、そこにはなんという異様な迫力をたたえた空白が現われることか。それは一面において、死のはかない感じをあたえるものではあるが、同時に、澄みきった敬虔さと疲れを知らぬ精力が漂っている感じを、あるいは少くともそうした敬虔さや精力が谺しているような感じをあたえるものだろう。」
此の文章で、また違った観方(聴き方)で「フーガの技法」を味わうようになるでしょう。
以上は、Facebook のあるグループへの投稿である。追加で、この小説で扱った阿藤伯海(Wikipedia)という漢詩人に触れてみたい。
離京
倦遊向鄕國 遊《ゆう》に倦《う》んで郷国《きゃうこく》に向ひ
別友大江邊 友《とも》と大江《たいこう》の辺《ほとり》に別《わか》る
握手情沈鬱 手《て》を握《にぎ》れば情《こころ》沈鬱《ちんうつ》にして
盪胷意結連 胸《むね》を盪《うご》かして意《おもひ》は結連《けつれん》す
帝畿飜落日 帝畿《ていき》は落日《らくじつ》を翻《ひるがへ》し
驛道斷荒煙 駅道《えきだう》は荒煙《くわうえん》に断《た》たる
此夜紅烽火 此《こ》の夜《よる》紅《くれなゐ》の烽火《ほうくわ》
警音頻有傳 警音《けいおん》の頻《しきり》に伝《つた》ふる有《あ》り
「紅烽火」(高射砲)が飛び交い「警音」(警報)が鳴り響く空襲下の東京を離れて、郷里岡山に向かう情景を詠う。
「苛烈な戦時を危うく生きのびて行く五十代はじめの反時代的な 漢詩人の社会的にまったく孤独な姿を、しみじみと浮かび上がらせているのである。」(清岡卓行)
阿藤伯海(1894-1965)は、若い頃には、フランスの象徴詩的な作風の「現代詩」も書いたが、のち、漢詩に移り、清岡卓行などの弟子に一高時代は講義をした。戦時下の好戦的な風潮に嫌気が差し、教授の職を辞職し、故郷に隠棲する。過ぎ去ったものへの郷愁が強かっただけに、嫌世的であり、その「抵抗」は、「後ろ向き」だったかもしれない。でも、後日、永井荷風も紹介するが、こうした「反時代的な姿勢」も、「死者との連帯」(中島岳志)という意味で忘却されるべきではなく、今を生きる私たちが継承するに値すると思う。
もう一首
臥龍庵に偃梅《えんばい》を哀れむ
鐵石心腸老臥梅 鉄石の心腸老臥梅
雪中何事忽隳摧 雪中何事ぞ忽ち隳摧《きさい》(折れ砕ける)す
艸堂從是無顏色 草堂是《こ》れより顔色無し
月夜寒園人不廻 月夜寒園人廻《めぐ》らず(人影はない)
自らを「老臥梅」に例え、逆説的には「鉄石の心腸」を持ち続けていると矜持しているように思える。
阿藤伯海故居跡は、岡山県浅口市にあり、現在は記念公園になっている。( )
参考】
・清岡卓行「詩礼伝家」
・石川忠久「日本人の漢詩」
付記
清岡卓行の詩がありました。バッハの何の曲が似合うでしょうか?
音楽会で
地球の裏がわから来た
老指揮者の振るバッハに
幼い子はうとうとした
風に揺らぐ花のように。
父は腕を添え木にした。
そして夢の中のように
甘い死の願いを聞いた
鳩と藻のパッサカリアに。
幼い子が眼ざめるとき
この世はどんなに騒めき
神秘になつかしく浮かぶ?
ああそんな記憶の庭が
父にも遠くで煙るが
フーガは明日の犀を呼ぶ。