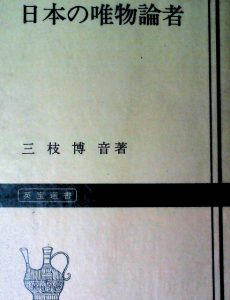◎ 三枝博音「日本の唯物論者」(002)
ー 私たちの国には唯物論者がいたか
日本には唯物論者がいたかどうか? いったい、日本には唯物論という思想の休系があったのかどうか? まずこの問いにこたえることから、この本をかきはじめたいと思う。
ずばり言ってしまうなら、私たちの国には唯物論者はいなかった、日本には唯物論の体系といっていいような思想の体系はなかった、そう言えるのである。
さて、このようにいってしまうと、ここに誰にとってもいろいろの疑間がむらがりおこるだろう。それらの疑問のうちでは、おそらくつぎの疑問がまず投げ出されることだろうし私たちの国には唯物論君はひとりもいなかったかと。ひとびとはさらにこうきくであろう。明治時代に中江兆民や幸徳秋水がいたではないか、大正・昭和の時代に河上肇や野呂栄太郎のような人がいたではないか。さらに、戸坂潤や永田広志のような人がいたではないか。人はきっとそうきくことであろう。そう、これらのひとびとは唯物論者と呼ばれているのである。そういえば江戸時代だっていないことはない。あんなに封建思想が強固で、ものを自巾に考えるすきさえもなかった時代に、かまだ・りゅうおう(鎌田柳泓)のような人がいて、人間が考えることは頭の中にある一種変った肉のしわざだというところまで主張したこともあるのだから、唯物論者はいなかったといってしまうと、とうぜん疑問がおこってくることだろう。だが、それにしても、私たちの国には唯物論者はいなかったという、さきの私の断定を私は改めないほうがよいと思う。もちろん、右にあげたようなひとびとをとらえて観念論者である(もっとも柳泓はここでしばらくあずかっておくけれども)とは、誰だって言いはしないし、私もそう考える何らの理由も持たない。それなら、右のひとびとは唯物論者であるか?問題はここからである。
ことに明治・大正・昭和の時代のなかからあげられた右のひとびとが、唯物論者であると呼ばれるのは、社会主義者であったがために唯物論者だとせられがちなのであり、共産主義者であったがためにそうされていることが多いのである。必ずしもそこにまちがいがあるわけではない。しかし、社会主義者であること、共産主義者であることが、唯物論者たることをきめるたったひとつの基準なのではない。私たちはこのことを考えておきたい。ロシアには、十九世紀の施半にすでに社会主義者がいくらも出ていたが、その人たちがことごとく唯物論者であったのではなかった。フランスには十八世紀に、すでに幾人かの、はっきりした唯物論者かいたが、その人たちは社会主ス者であったから唯物論者であったのではない。今日でも、ことごとく現実に共産主義者であるとみずから考えている人が、あらゆる意味において唯物論者であると決定することはできない。
唯物論には、それが唯物論であることの思想的な、世界観的な、いわば確乎たる特質があるのでなくてはならない。唯物論者はそうした世界観のシステムにつながっているのである。あたかも、めんめんとつらなる電送の太い線に結びついている碍子のように、その電線に結びついている限りにおいて、個々の碍子は電流を確実につたえるものの一つなのである。今日でも、個々の唯物論者は、或る政治的組織に入ったから、そのとき唯物論者になったのではなくて、その政治的組織のなかにある世界観的な唯物論の太い線に結びついたから、「唯物論者」なのである。
ヨーロッパでは、この線は小さいながら、古代ギリシアからはじまって、ぜんじ大きくなり、近代にいたっているのである。マルクス、エンゲルスは、この太い線をイデオロギーの歴史の発度のなかから見出した人たちなのである。マルクス、エンゲルスによってはじめてこの世界観の太い線が張られたのではなくて、これらのひとびとは、この線の現実的意味をはじめてみつけだし、これを深化し、強化したのである。
この思想的な世界観的な線が、私たちの国にあったか、それともなかったか。もしあったとするならば、どういうあり方であったか、これが私たちの問題である。
それは日本本にはなかったといいきれる。いや、日本のみでなく、もっとくわしくいうと、老荘的な、仏教的な、儒教的な思想、ことに仏教的な思想から深い影響をうけとっている東洋のすべての諸民族のなかには、あの太い世界観の線は通っていなかったのであるということができる。じつにこの意味において、私は私たちの国には唯物論はなかったというのであり、唯物論者はいなかったと主張するのである。唯物論者のあるなしについて、きびしくいえば、いちおう以上のようにいうことができる。
もちろん今日となればちがうだろう。唯物論という思想システムの線は、ヨー ロッパの近代世界観が日本へ移植されるとともに、ことに政治的イデオロギーの移入とともに、近代日本に移されている。それがゆえにこそ、中江兆民や幸徳秋水が、とにかくに唯物論者であるといわれ、河上肇や野呂栄太郎が、戸坂潤や永田広志が弁証法的な唯物論者であったということができるのである。私たちにとって問題なのは、これらの人たちが、あの唯物論という世界観の太い線が全くなかった国のなかに住み、そうした国の言語をもちい、そうした国の庶民の生活の仕方にならい、この国の習俗のなかにひたり、その思想(河上ならば河上、戸坂ならば戸坂の思想)の他人への影響力を狭い範囲の或る日本人の間にのみもっていたことなのである。
こうしたことが、考慮されないままで、すべて社会主義、マルクス主義に属していれば、なべてみな雎物論者であると言ってしまうことは、論を正しくすすめることにはならない。右にあげた中江兆民以下のひとびとが、その中でしばられて活動したあの社会的な諸条件のうちでも、その人の思想の他のひとびとへの影響力がいつまでも一定範囲にとどまりがちであったことは、唯物論者の存在にとって、重大な問題であると思うのである。私がかくいうのは、さきにあげた人々を唯物論者と呼びがたいとか、ほんとうの唯物論者と呼びたくないとか、そうしたことを言わんとしているためではないのである。むしろその反対なのである。これらの人たちは、唯物論の伝統の少しもなかったこの国において、多くの唯物論反対者にとりまかれて、いやそれどころか、じつに、ことごとくが観念論的な習俗のなかにあって、新しい世界観をかちとったことが、かえって、私たちにとつて切実に思われるのである。
それにしても、はじめから、日本には唯物論があった、わが国には唯物論者がいたと、.女易にきめて、私たちの問題(日本における唯物論のあり方という問題)を、おしすすめることはできないのである。だから私は、はっきりと、私たちの国には過去において唯物論の思想体系はなかった、したがって唯物論者はいなかった、すくなくとも、いることが困難であったと、まず提言したいのである。
底本】
三枝博音「日本の唯物論者」(英宝社・英宝選書)1954年6月30日初版)
その他、「科学図書館」所収の、PDF も適時参照した。
なお、底本中の、ふりがなは、ruby タグを用い、傍点は、太字表示の b タグ を用いた。