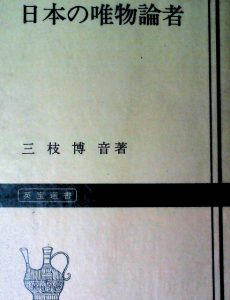◎ 三枝博音「日本の唯物論者」(001)
ま え が き
日本人は、外国人から唯物主義だといわれたり、理想というものがわからない国民だと批評されたりした。その一例をいえば、チェンバレンやデニングなどであるが、日本人の性質のうちにはそう批評される点のあることは否定できない。さて、そうでありながら他方において、日本には唯物論の哲学といわれるほどのものはないといわれている。こうなってくると、まことに割りの合わない話である。
ほんとうのところ、日本人は唯物論という思想はもたなかったのか。そういう思想組織がもてるようには、日本の思想丈化の成り立ちができていなかったのか。それとも、別の在り方をして、唯物論思想をもっていたのか。もしもっていたのなら、その思想はどういう形応でできていたのか。こうした問題はこれまで少しも明らかにされなかった。
さて、それが明らかにされるには、何が唯物論かという問いが改めて投げ出されねばならないであろう。なぜなら、日本に唯物論があったにしても、ヨーロッパにおける在り方とはちがっているにちがいないから。いずれにしても、唯物論の概念が明瞭でなくては、問題は前へすすまない。
いったい、マテリアリズムとは何をさすのであるか。
心かそれとも物か、意識かそれとも物質か、こうした問いを押しつめていったら、マテリアリズムは、はっきりとわかるのであろうか。いよいよのところは精神しかないのだという見解、いや、けっきよくは物質しかないのだという見解、この二つが、昔と変らないまま、今日る繰りかえされている。
私の考えでは、二つの見解のうちの前者は、頭のなかで<考え 傍点>をととのえ、紙のうえに文章をかき、人にものを教えることだけを仕事にしている人たちの場合において、真理とおもえるのであり、後者は、物を作ること、生産にいそしむことをしている人たち、および、それらの人たちの生活に共感できる人たちにとって、真理であり得る。私にはそのように思われる。
してみると、双方の主張者のこうした論議だけでは、観念論が真理なのか唯物論が真理なのか、きまらない。唯物論と観念論の是非は、あのような、ただひとつのディメンションではきまらないのではあるまいか。物質の概念の究明のほとんどなかった過去の日本人の場合では、ことにそうなのではあるまいか。
しかし、唯物論といわれる世界観が、どういうひとびとによって支持されているかがわかれば、そこから逆に、何が唯物論かが、かえって明らかになるのではあるまいか。
観念論とは、その社会が泥沼のようであろうと風波さえたたねばよいと現状を甘受し、享有している人たちの世界観であるのではなかろうか。唯物論とは、それとは逆で、現状に決定的に疯議し、人間生活の在り方を、ほんらいのものにかえそうとする人たちの世界観ではあるまいか。
おまえは神の子であると教えようとする人がいると、いや私たちは神の子ではないと言い張る。おまえの存在は本質的には精神だと宣言しようとする人がいると、いや私たちの存在の本質は物質の運動であると言い張る。こういったように、人間存在の本質から出てくる抵抗、ことにその社会的な本質からくる抵抗、それの思想的表現、これがじつに唯物論であるのではあるまいか。
私は、はじめから、このような唯物論の概念をたずさえて、日本人の生活の歴史のなかに入っていったのではなくて、世界観や学問観において傑出した過去の人物を評伝するうちに、以上のべたようなマテリアリズムに対する理解を、いっそう深くしたのである。
私は、その理解をさらにととのえ、それを公けにするために、日本の唯物論者の現われかたを、つぎのような仕方に分けて、論評してみたのである。すなわち、「唯物論への道を準備した人々」、「唯物論に近づいた人々」、「ふたたびそれへの準備をはじめた人々」、「新しい時代(明治・大正・昭和)の唯物論者」の四つである。日本の思想文化史のように、ひだやしわが多く、明暗の度の細かい思想の歴史のなかに、個々の唯物論者を見出すには、断定のゆきすぎをひかえることが大切なので、その点を考えて、試みた叙述方法なのである。
この「まえがき」で言っていないこと、それはほかでもなく、個々の唯物論者たちの相互の歴史的つながりのことであるが、それを「むすび」のところで述べておいたから、それをも、さきに併せて読んでもらうことがのぞましい。
ー九五六年六月下旬
三 枝 博 音
参考】
・ Wikipedia 三枝博音
三枝博音は、戦前、「唯物論研究会」に属し、様々な労作を執筆した。戦後も、そのスタンスは変わらなったが、「政治的党派」に与することなく、微妙な「距離感」を保っていたようだ。
底本】
三枝博音「日本の唯物論者」(英宝社・英宝選書)1954年6月30日初版)
なお、底本中の、ふりがなは、ruby タグを用い、傍点は、太字表示の b タグ を用いた。