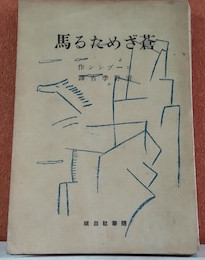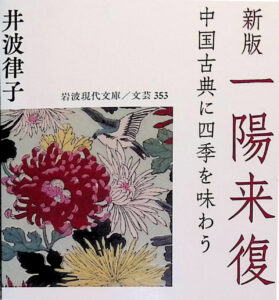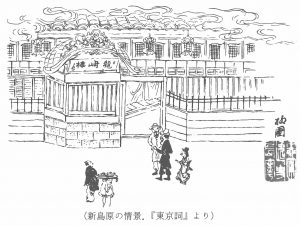◎蒼ざめたる馬(003)
ロープシン作、青野季吉訳
三月十七日。
私が何故この仕事を始めたか、私は知らない。然し他の者がそれに入つて來た理由は知つてる。ハインリヒはそれが私の義務だと信じてゐる。フエドルは妻が殺されたので私と付い た。 エルナは生きてゐるのは恥だと云ふ。ヴァニアは… ヴァニア自らに語らせやう。
最近彼が私の者となつて、一緖に郊外で終日した。 私は彼と旅舍で談合する約束があつた。
彼は、下層階級の人の着けるやうな長靴に靑服でやつて來た。彼は鰓髯を直して髮を圓く刈込んでゐた。彼は言つた。
「時に、君はこれまでキリストのことを考へたことがあるか?」
「誰のこと?」
「キリストのことさ、神人キリストのことさ。君はこれまで、何を信じなければならんか、どうして生きなければならんか、君自身に尋ねたことがあるかね?宿屋や、馭者溜りで僕はよく聖書を讀むんだ。そして僕は、人閒にはた二つの道しか開けてゐない、實際二つ切りだといふ結論に達したんだ。一つは、ての事は許す可きだと信することだね。いゝかね、例外無しに凡てのことがだだよ。もしどんな考へにも冒し進んで慄《おじ》けない心を持つてゐれば、その道によつてドストイエフスキーのスメルヂヤコフのやうな人物が作られるだ。 要するその態度にも論理はある、と云ふのは、神が存在せず、キリストが一個の人閒に過ぎない以上は、そこにはまた愛もない、卽ち君を抑へる何物も無いからね。モウ一つはキリストに導いて行くキリストの道だ。人閒の心に 愛があるなら―本統の深い愛だよ―彼は殺すことが出[來 1字補]ると思ふか出來ないと思ふか?」
私は答へた。「出來るさ、どんな場合でも」
「いや、どんな場合にも出來ない。 殺すことは大きな罪だ。「同胞の爲にその生命を棄つるより 「大いなる愛は無し」さ。 そして彼は、生命より以上の―彼の心靈も投け出さなければならないんだ。彼は彼自身の十字架に上らなければならんし、愛によつて―愛だけによつてが促されないからには、どんな決心もしてはならないんだ。他の動機なら彼をスメルヂヤコフ*に戾して仕舞ふんだ。僕の生命を取つて見給へ。何の爲めに僕は生きてゐるか?僕の最後の時が、僕が全生命をその爲に生きなければならなかつたものを證據立てる爲めなんだ、全く。僕は神に祈る。神樣、愛の爲めに君を死なせて下さいと。が、人殺しをする爲めにお禱りをする者があるか?人は殺すであらう、然しそれに就いて禱りはしない…僕は知つてゐる、僕は心の中に十分に愛を持つてゐないんだ。 僕の十字架は僕には重過ぎて擔へないんだ。」
「笑ふな。」と彼はすぐ後で言つた。「何にも笑ふことは無い。僕は神と神の言葉のことを話してるんだ。僕が譫語《たわごと》を言つてると君は思つてるんだらう。實際君は僕が譫語を云つてると思つてるかい?え?」
私は返事をしなかつた。
「默示錄の約翰」を覺えてゐるだらう。「この時に人々死を求ん爲《なせ》ども能はず。死んことを願へど死は遁去《のがれさる》べし。」と云つてゐる。死を願ふ時に、死が君から去るほど恐ろしいことがあらうか?君もまた死を求めるだらう。 我々皆も。どうして僕等は血を流すか?法律を破るか?君は法律を認めない。血は君には水と同じだ。然し覺えてる給へ、いつか君は僕の言葉を思出すだら う。君はその結末を追ひ求めてゐるが、それはやつて來ないだらう。 死は君から遁去るだらう。 僕はキリストを信ずる、實際信ずる。然し僕は彼と共に居ないのだ。 僕は彼に値しない。 僕は泥と血で穢されてるのだ。それでもなほ慈悲深い神は來て下さるだらう。」
私はぢつと彼の眼を凝視めて答へた。
「それなら、 何故殺すか?君は勝手に僕から離れていゝんだよ。」
彼の顏はすつかり靑ざめた。
「どうして君はそんなことを言ふんだ?僕の靈は惱んでゐる。然し僕は出來ない…… 僕は愛する。」
「譫語だ。ヴァニア。もうそんなことを考へるな。」
彼は答へなかつた。
私は彼を離れて、街へ出るとすぐ、すつかり忘れて仕舞つた。
[編集者注]
* ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」の登場人物、小説では、父親を殺害。
三月十九日。
エルナは泣いて淚の中から云つた。
「あなたはもうわたしを愛してゐない。」
彼女は私の肱掛椅子に坐つて、手で顏を蔽ふてゐた。彼女の手がそんなに大いことを、前に氣が付かなかつたのは不思議だ。
私は彼女を深く凝視して言つた。
「聲を立てるな、エルナ」
彼女は眼を上げて私を見た。彼女の赤いと落込んだ下唇が彼女を醜くした。私は窓の方へ向いた。 彼女は肱掛椅子から立つて、おづ/\私の袖を引いた。
「ごめんなさいよ」彼女は言つた。「もう聲を立てませんから」
彼女は時々泣聲を立てる。 最初に眼が赤くなつて、それから頬が膨れ出して、おしまひにはかすかな涙が頬の上にけて来る。何といふかな涙だ!
私は彼女を膝に引寄せた。
「エルナ」私は彼女に言つた。「僕がおまへを愛すると此迄云つたことがあつたかい?」
「いゝえ」
「僕はおまへを欺いたかい?他の女も僕は愛すると云はなかつたかい?」
彼女は答へなかつた。たゞ全身を震はした。
「どうだね。」
「え、そう仰つたわ。」
「だからね、おまへに飽きが来たら、僕はおまへに言つて仕舞ふよ。決してお前に祕したりなんかしない。僕を信するだらうね?」
「え、信じます。」
「む、それでいゝ。さあもう泣くのは止せ。 おまへより外には無いんだよ。」
私は彼女にキスした。 彼女は次のやうに云つて、樂しさうな顔をした。
「どんなにわたしはあなたを愛してるでしやう!」
然し私は彼女の大きな手を忘れることは出来なかつた。
三月廿一日。
私は英語は一言も知らない。旅館や、料理屋や、町で、片言混りの露亞西語をつかふ。それか 時々いやなことが起つて來る。
昨夜私は芝居に行つた。赭い、汗つほい顏をした嚴丈な男が側に掛けてゐた。彼が鼻を鳴して深い呼吸し、幕の開いてる間半眠りをしてゐた。幕合に私の方を向いて訊ねた。
「あなたは何國《どこ》の方《かた》ですか?」
私は返事をしなかつた。
「お分りになりませんか?」と彼は再び訊た。「あなたのお國を知り度いんです」
私は彼を見ないで答へた。
「私は英國皇帝の一臣民です。」
これで彼は満足しないらしかつた。
「誰の臣民だと仰るんですか?」と彼は重ねて訊ねた。
「英國人ですよ。」
「あゝ英國人…あなたが?それならあなたは世界で一番悪い國民にしてるんですね。 彼奴等《あいつら》は日本人に加勢して對島海峡で我國の旗艦を沈めた。彼奴等のすることはそんなもので。それでゐてあなたは知らん顏で、露西亞へ旅行に來てゐる。 止しにして貰ひ度い!」
人々が私達に目を向けた。
「私にものを仰ることをやめて戴きましやう。」と私は低い聲で言つた。
「あなたを巡査に渡します。 私のすることはそれだ。」彼は聲を張り上げて言ひ續けた。「お覧なさい此の男を!あれはきつと日本の間だ。それでなけりあ、何かの詐欺師だ。英国人だつて、本統に!巡査がなぜ尾けないんだらう」
私はポケットの中の拳銃を觸つた。
「お默んなさい。」と私は命じた。
「默れつて!いや、二人で警察へ行かう。そこへ行けばも何《なに》彼《か》も分るんだ。間諜は我国では許されないんだ。神聖な露西亞萬歳だ!」
私は立ち上つて、彼の闘い血の灑いた眼を眞直に見詰めた。
「三度君に警告する、默んなさい!」
彼は肩をすくめて一言も言はないで坐つて仕舞つた。
私は劇場を出た。
三月廿四日。
ハインリヒは丁度二十二になる。學生の時には會合でよく饒舌つた。その時分は眼鏡をかけて長い髪をしてゐた。今は、彼もヴアニアのやうに粗野になつた。痩せていつも顏を剃るつてゐない。彼の馬も痩せて、馬具はボロ/\で、橇は古物だ。彼は最下層階級のありふれた橇屋だ。
ある日彼は私とエルナをに乗せて來た。町の門を出る時に、彼はくるりと後を向いて言つた。
「このあいだ僕は坊主と喧嘩したよ。そいつがラウンド・スクエヤの番地を云つて、十五コペ ーキの橇代を拂はうと云つたんだ。僕は所を知らないから、橇をくる/\後を挽いて廻つたんだ。とう/\ 奴《やつ》怒り出して仕舞つて、毒付き出すんだ。『泥棒め、貴様は道を知らないんだな、巡査に引渡すぞ!』 それから續けて云ふんだ。『馭者といふものは自分の燕麥《からすむぎ》の嚢のやうに町をちゃんと知つて居らにやならんもんだぞ。貴様はきつと騙つて鑑札を取つたんだな。一ルーブル位の賄賂を つかつて、試驗なしに通して貰つたんだろう。』僕はそいつを取るのに面倒したよ。『どうぞ旦那様お赦し下さい』と僕は云つた。『キリスト様の爲めにお赦し下さい!』 彼の言ふことは實際だ。僕は試験を受けやしないんだ。 宿無しのカルプジヤが僕の代りに受けてくれて、僕は手間賃に五十コベーキ拂《はら》つたんだからね」
エルナは聞いてるなかつたが、彼は非常に油が乗つて續けた。
「すぐ二三日前も藝當をやつたよ。或お爺さんの夫婦を乗せたんだ。いゝ階級の禮儀正しい人らしかつたが、かなりの老夫婦だつた。丁度ロング・スツリートを駆けて行つた時に、電車が停留所に止つたんだ。それを餘り気にも留めないで、僕は軋道を駆けぬけた。すると橇の中の老夫婦は飛び上つて、激しく僕の首筋を蹴飛した。『惡者奴!』と彼は呼んだ。『貴様は私達が轢死させるつもりか?氣狂のやうに驅立てゝどうするんだ、畜生!』
「『旦那様何も驚きなさることはありません。』と私は言った。『横切つたつて何でもないことでございます。電車の出る迄にはまだ少時《しばらく》あります。その時女が佛蘭西語で彼に云ふのが聞えた。ジアン、そんなにお怒りなさるなよ。お體に大層さわりますよ。馭者もやはり人間ですから』 彼女 は實際、馭者もやはり人間だと云つたんだ。すると彼は露西亞語で答へた。『それはそうだらうが、此奴は獸《けだもの》だよ』『おゝ、ジアン、』と彼女は云つた。『そんなことを仰つては恥《はぢ》になります。それから彼が僕の肩を軽く叩くのを感じた。『濟《す》まなかったな。』と彼は言った。『氣に掛けなさんな。』そして彼は二十コペーキのチツプを呉れた。……彼等は多分自由黨なんだらう。……おい右だ 婆《ばあ》さん孃《ぢやう》さん!」
ハインリヒは惨めなよろ/\の馬に鞭を當てた。 エルナはそつと私に寄り添った。
「エルナ・ヤコヴレヴナさん。此の土地はいかゞですね?仕事に慣れましたか?」
ハインリヒは寧ろ辱かしそうにしてこの問ひを發した。 エルナは嫌やらしい風で答へた。 「すつかり満足してますわ。 そりあ仕事にももう慣れましたわ」
私の右手には黑い亡靈のやうな櫟樹があり、左手には野原《のはら》の白い衣があつた。町は前に展がつてゐた。會堂は日光に輝いてゐた。
ハインリヒは口を噤み、橇の軋る音の外は、通りは深い沈默の中にあつた。ハインリヒは私達を町へ返した。橇から下りる時に私は、彼の手に五十コベーキをおいた。彼は霜を被った帽子を脱いで、長い間私を見つてゐた。
エルナは低語いた。
「今夜、あなたのところへ行ってもよくつて?」
注記】画像は、古本市場で出品の「蒼ざめたる馬」奥付き。なお本文、訳文の著作権は消失している。
参考】川崎浃訳「蒼ざめた馬」(岩波書店 同時代ライブラリー)