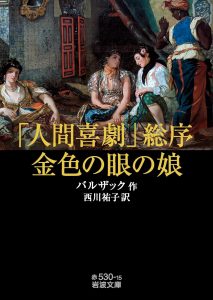◎バルザック「人間喜劇」カタログとゴリオ爺さん(001)
書店に立ち寄り、偶然手にしたのが、バルザック「『人間喜劇』総序・他」(岩波文庫)、「総序」も興味深いが、カタログ(1845年)を見ているだけで、十分「人間喜劇」に浸っている気がした。カタログに挙げられている130編余の小説のうち、有名所をほんの数編しかかじっただけだが、例えば、山の写真を見て、日本百名山を踏破したような気分である。もっとも百名山の登頂は半分を少し達成したが、まずは、一生のうちに「人間喜劇」のたとえ半分も読むことはないだろう。とりあえず、文庫の「付録」にあった「カタログ」の一部から抜粋。(余力があれば全カタログを紹介する。
第I部風俗研究 ÉTUDES DE MŒURS
[l] 私生活情景 Scénes de la vie priveé
(1『子どもたち Les Enfants』)
(2『女子寄宿学校 Un Pensionnat de demoiselles』)
(3『寄宿学校内 Intérieur de collége』)
4『毬打つ猫の店 La Maison du chat-qui-pelote』
5『ソーの舞踏会 La Bal de Sceaux
6『二人の若妻の手記 Méoires de deux jeunes mariées』
7『財布 La Bourse』
8『モデスト・ミニョン Modeste MignonJ
9『人生の門出 Un début dans la vie』
10『アルベール・サヴァリュス Albert Savarus』
11『ラ・ヴァンデッタ La Vendetta』
12『二重家庭 Une double familleJ』
13『家庭の平和 La Paixdu ménage』
14『マダム・フィルミアニ Madame Firmiani』
15『女性研究 Étude de femme』
16『偽りの愛人 La Fausse MaîtresseJ
17『イヴの娘 Une fille d’Éve』
18『シャベール大佐 Le Colonel Chabert』
19『ことづて Le Message』
20『ざくろ屋敷 La Grenadière』
21『捨てられた女 La Femme abandonnéeJ』
22『オノリーヌ Honorine』
23『ベアトリクス Béatrix ou les Amours forcées』
24『ゴプセック Gobseck』
25『三十女 La Femme de trente ans』
26『ペール・ゴリオ Le Pére Goriot』(ゴリオ爺さん)
27『ピエール・グラスー Pierre Grassou』→パリ生活情景
28『無神論者のミサ La Messe de l’athée』
29『禁治産 L’Interdiction』
30『夫婦財産契約 Le Contrat de mariage』
(31『婿と姑 Gendres et belles-mères』)
32『続女性研究 Autre étude de femme』
数少ない読了小説で、一番印象深かったのは、26『ペール・ゴリオ』(ふつう、『ゴリオ爺さん』という名で親しまれている。その頃、シェイクスピアの「リア王」を読み、芝居も覧たので、思いの外、プロットが似ていることが、興味のそそるところだったのかもしれない。
当方が、実際のカルチエ・ラタンの現場に佇んでいた経験をもった、だいぶ以前のことである。
続くかどうかは、自信はないが、その冒頭部分、(角川文庫昭和26年11月26日版小西茂也訳で、作者はもちろん、訳者の著作権も消失している。青空文庫にもないはずである。)図は、岩波文庫表紙と角川文庫版「ゴリオ爺さん」挿絵
— ここから「ゴリオ爺さん」
偉大にして令名赫赫たる
ジョセフロウ・サン・ディレール*へ
その著作と天才を讃美するしるしとして
ド・バルザック
*注)ジョセフロウ・サン・ディレール(1772-1844)動物學者。變態說論者。キュヴイエ・ガルなどと共にバルザックに大きな影響を與えた。
本文は、新字新かなづかい(創元社版)、ただし挿絵などは旧かな版からも転載した。
第一章 下宿屋
第二章 二つの訪問
第三章 社交界への登場
第四章 不死身
第五章 二人の娘
第六章 爺さんの死
登場人物
ゴリオ爺さん
かつて製麺業者として成功し、莫大な財産をきずいた商人。だが、愛妻を亡くしてからは、嫁いだ二人の娘の言うがままになって、ヴォケール夫人の下宿屋でひっそり暮らす。
アナスタジー・ド・レストー伯爵夫人
ゴリオ爺さんの上の娘。「サラブレッド」とあだ名される。父親から金をひきだすのがうまく、それがまた妹との喧嘩をひきおこす。
デルフィーヌ・ド・ニュシンゲン夫人
銀行家に嫁いだゴリオ爺さんの下の娘。名門に嫁いだ姉にたいする嫉妬にさいなまれている。ラスティニャックを夢中にさせ、親しくなる。
ウージェーヌ・ド・ラスティニャック
野望を胸にパリに出てきた二十二歳の青年。勉学に励んで学位をとる道と、社交界に進出して地位を手に入れるという、二股をかけた生活を送ろうとする。
ヴォーケル夫人
下宿屋の女主人。世間の苦労をなめつくしたやり手のおかみ。
ヴォートラン
得体の知れない四十がらみの大男。ラスティニャックの野心を見ぬき、金銭の援助を申しでる。
ボーセアン子爵夫人
パリ社交界の女王の一人。ラスティニャックの遠縁で、彼の上流社会進出に力をかす。恋の手練手管をラスティニャックに教えながら、いっぽうでは社交生活に虚しさを感じている。シルヴィ 下宿屋の太っちょの料理女。
ヴィクトリーヌ・タイユフェル
百万長者の父親に認知してもらえず、死んだ母の遠縁にあたるクーチュール夫人と下宿屋にひっそりと暮らす娘。
ビアンション
ラスティニャックの友人の医学生。
ダジュダ・パント侯爵
ポルトガルの富裕な貴族。ボーセアン子爵夫人の愛人。
下宿屋
ヴォーケル夫人は旧姓コンフランという年配のおかみさんで、もう四十年来パリで下宿屋を開いていた。カルチエ・ラタンとフォーブール・サン・マルソーの間にある、ヌーヴ・サント・ジュヌヴィエーヴ通りでのヴォーケル館といえば、すこしは人にも知られ、下宿人に老若男女を迎え入れていたが、相当に信用があるその下宿館の風儀を、ついぞ云々《うんぬん》せられたこともなかった。もっともここ三十年、若い連中をお客にしたことは一度もなかったし、家からの仕送りがよっぽど乏しければ別だが、若い身空でいて腰が落ち着けるような下宿屋でもまたなかった。
けれどこのドラマの始まった当時の一八一九年には、一人の貧しい娘がそこに下宿人になっていた。ドラマなる言葉は最近のロマンチック文学で、ふんだんに濫用されて歪められた結果、すっかり信用を堕《おと》してしまっているが、ここではぜひともその語を用いておく必要がある。なにもそれは言葉の本来の意味からいって、この物語がドラマチックだからというのではない。一巻のこの物語が果てるや、パリの城壁の内と外で、おそらく若干の涙が流されるであろうからである。だがこの物語は、パリ以外のところでも、十分に解ってもらえるだろうか? そうした疑問も一応はもっともだ。観察だくさんで、しかも地方色に溢れた本情景の特異性といったものは、モンマルトルの岡とモンルージュの高台にはさまれ、いまにも崩れ落ちそうな壁土とどぶ泥の溝川とで、名を売ったこの谷底のなかでもなければ、その真味を知るわけにはゆかぬからである。