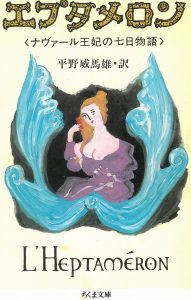◎風流滑稽譚(一)バルザック著小西茂也訳
【編者より】
またもや、大層な長文痛みいる。本文に《》が使われてる故、ルビの内容は[]で已む無くされた。
王の愛妾
今は昔、巴里両替橋の鍛冶場に居住するさる宝石師の娘に、飛切りの別嬪がおって、そのあでやかさは巴里じゅうにも鳴り響いておった。さるに依り恋の仕組のいつもごとを以て、言い寄る殿方も数知れず、妻に娶るべく莫大な金品を醵出しようとまでする篤志家も現われ、父御はすっかり有卦に入って恵比須顔でおられたとか。
その隣人の一人に最高法院の弁護士がおったが、世間様にお喋りを売ったお蔭で、犬に蚤めがいるように沢山と地所を買い込み、たまたま見染めた隣りの娘に、結婚事をおっぱめようとして、件の父親に立派な家屋を進呈して、うんと言わせようと計られた。ひげむじゃらのこの三百代言が猿面をしていようが、下顎に歯が僅かしかなく、それもみなぐらぐらしていようが、一向に父親はお構いなく、また育ちが育ちで、――いったい裁判所で、羊皮紙や判例集や真黒な訴訟書類などの、堆肥くずの残骸の蔭に起居する司法畑の連中は、みんな嫌な臭いを身に沁みこませているものだが、――そうしたむさい悪臭を婿どんが放とうが、些かも嗅いでみることもせず、二つ返事で娘をやることを合点してしまわれた。小町娘は未来の婿どんを見るや否や、《まあ神様、お助けを。あたし真平御免だわ。》と、真向から反対めされた。しかし家屋敷がすっかりお気に召していた父親は、《それは儂の知ったことか。結構人の良人を其方に選んでとらせたのだ。あとはお前から気に入られるようにするのが、あいつの才覚というものじゃ。お前はただ跋を合わせればいいのだ。》
『そんなものでしょうか。いいわ、お父さんの言附に従う前に、あの人にうんと将来を思い知らせてやるから。』
その晩、夕食後に弁護士が、彼女に燃えるような彼の訴訟事実を申し立てて、いかにぞっこんあつあつであるかを陳述いたし、生涯彼女に大御馳走を予約し出した時、彼女はあっさりとこう言った。『父はあなたに妾の身体を売りました。それを貴方が受けるなら妾は不仕鱈女になってお目にかけます。妾はあなたに身を許すくらいなら、行きすがりの人にこの身を任せた方がいいですわ。終世渝らぬまことを誓うのとは反対に、渝らぬまおとこ沙汰を、あたしはあなたに誓います。あなたかあたしか、どっちかの死ぬまでずっと。』
そう云ってまだおっぺされたことのない娘っ子がみんなするように、彼女もまた泣きじゃくり出した。知った後では、阿魔っ子は決して眼では泣かぬものである。人の好い弁護士は彼女のこの変手古な仕打を、からかいかおびき寄せの手と考えた。そういえば娘っ子は相手の情炎をさらに煽って、その愛溺に乗じ、寡婦財産設定や未亡人先取権獲得や、其他くさぐさの妻の権利を、泰山の安きにおこうとして、斯様な手立てをお用いめさることが屡々である。で、弁護士も老獪なだけに、ちっともそれらを真に受けず、愁歎の美女を嗤ってこう訊ねただけだった。『祝言はいつにしよう?』『明日でも結構よ。早ければ早いほど、好き勝手に色男がもて、選び放題に色恋のできる快楽生活を送れるわけですもの。』
童児の鳥黐にかかった河原ひわのように、恋の虜となったこの恋やみの弁護士は、早速に家に戻って嫁取り支度に取掛り、思いをただ彼女の方にばかり馳し、裁判所であたふたと婚姻手続を済ませ、司教代理判事の許で結婚の特免状を購い、彼の引受けたこれまでの訴訟事のなかで、ついぞ示したこともないようなあっぱれ迅速さで、手早く事を運んだのであった。
ちょうどこの時分、御遠征さきから戻られた国王には、宮廷じゅうが例の小町娘の噂で、持切りなのを御覧になられた。誰それどのの提供した一千エキュの金を、彼女が蹴ったとか、何がしどのに肱鉄をくらわせたとか、はては誰にも靡こうとせぬ操正しいこの堅気娘と、たった一日でも楽しい思いが出来たら、後生の一部を割いても惜しゅうないという意気込みの貴公子がたを、みんな彼女は袖にしたなどという評判を、王にはお耳にせられ、こうした獲物がりにはかねて目のない御尊貴方のこととて、早速に町へお忍びであらせられ、鍛冶屋敷に赴いて宝石師の許にお立寄りになって、その心の想い人の為に若干の宝石を購い、且つはその店の一番貴重な宝石を、お取引あそばそうとなされた。が、王にはなみの宝石がお気に召さなかった。或は言うならば、なみの宝石が王の御趣味には合わなんだ。それで店の主人が、隠し金庫の中を掻き探し、巨きな白ダイヤをお目にかけようとして、金庫に鼻を突込んでいる隙に、王様には小町娘にこう申された。『そなたは宝石を売る柄ではなくて、受ける方がいっそ適していよう。この店の指環[はめもの]のうち、儂にその一つを選べとなら、余人も惚れ、この儂にも気に叶う一品を、もう疾うに選出ずみじゃ。儂は永久にその臣下か下僕となろう。フランス王国を捧げても、そのあたいを払い切ることはかなわぬと見たぞ。』『陛下、明日妾は祝言事をいたさねばなりません。けれどもし妾に、陛下のお腰にしておいでの短剣を、一振り頂戴出来ますならば、誓ってわらわの花を守護し、「シーザーのものはシーザーへ」の福音書の訓え通り、その花を陛下の為に、取って置くといたしましょう。』
即座に王は短剣を御下賜あそばされた。彼女の雄々しい言葉から、王は御食慾を爾今うしなわれるまで御恋慕遊ばされ、イロンデル街の御別邸に、この新規な愛妾を囲おうと思召されながら、立去られたのであった。
さて弁護士は結婚でおのれを縛ろうと急ぎ、鐘の音と音楽の流れるなかを花嫁を祭壇に導き、お客を下痢させるほどの盛大な酒盛を開いたが、恋敵たちの無念の思いは、そも如何ばかりであったろう。その晩、舞踏もおひらきになってから美しい花嫁御のやすんでいる筈の翠帳紅閨に婿殿は赴いた。したが相手はもう麗しい花嫁どころの騒ぎでなく、いえば訴訟ずきの小悪魔、いかりたった妖魔であった。花嫁は安楽椅子に陣取ったきりで、婿どんの床に入ろうともせず、炉の前でその忿怒や前のものを焙っているばかり。喫驚いたした花婿は、花嫁御寮の前で膝を七重に折って、初太刀とっての心楽しい打物わざに、彼女を招聘いたしたが、フンともこれに彼女は答えなかった。ひどく彼に高いものについた彼処を、ちょっと眺めるためペチコートをまくろうとして、骨も挫けよとばかりピシャリとなぐられた。しかも花嫁は頑強に口を噤んだきりだった。このお茶番はしかしかえって弁護士のお気に召した。そこで、みなさん御存じのあのことを以て、この場のけりをつけたいと思った彼は、本気でこのお茶番に乗り出し、根性わるの嫁が君から、さかんな反撃を蒙ったが、組みついたり押しつけたり、ひっ繰り返したり、くんずほぐれつのその結果は、彼女の袖を片っ方ちぎり、スカートを綻ばせたりしてのち、すべらした彼の手は、あわや愛くるしい狙いの的に達しかけた折、あまりといえば不軌蔑しろなこの異図に、柳眉を逆立てた彼女はすっくとその場に立上って、王の短剣をやおら引抜き、『あたしから何が欲しいんです!』と叫んだ。『何もかも欲しいんだ。』『不承不承にからだを提供《おつとめ》するのは、売女同然の仕打です。妾の素女点が武装されてないと思ったら、大間違いですよ。さあ、これは王様から賜わった短剣です。妾に近づくようなことをなされば、これで殺してしまいますよ。』
そう言って彼女は、弁護士の方に眼を配りながら、消炭を取上げ、床の上に線を引いてこう附け加えた。『これから内側は王様の御領分ですから入らないで下さい。もし越境などしたら、お命は頂戴してよ。』
打物を執ってといっても、短剣でなんぞ色恋をする積りはなかったので、花婿はすっかりしょげてしまわれた。しかしむごい彼女の宣告を聞いている間、仰山の金を費して敗訴となった弁護士の彼は、彼女のスカートの破れ目から白いむっちりしたあでやかな太腿のけなるい一部や、ローブの綻びを塞いでいる輝かしい主婦むきの裏地や、其他の隠しどころをまじまじと眺めて、ちょっとでもそれが味わえたら、死んでもよいとまで思い込み、《死のうがどうしようが!》と叫んで猛然と王領のなかに殺到いたした。
その勢いの凄じさといったら、どすんと彼女も寝床の上に押し倒されたくらいだったが、しかし気を鎮めて花嫁は、健気にもこれに応戦し、手足をばたつかせて逆らったので、突貫花婿にせいぜい出来たことは、金色の毛皮に手を触れ得たことだけだった。それも背中の脂肉を、短剣でいささか切り取られた奮戦の賜物とはいえ、それくらいの手傷で、王の持物のなかへ突入できたとすれば、彼にとってそう大して高いものでもなかった。この僅かな勝利に酔った彼は、《この綺麗なからだ、この愛の驚異を、おのが物にせねば生きる甲斐がない。どうか俺を殺してくれ!》と叫んで、またもや王の禁猟地へ肉弾攻撃にと移った。王様のことがあたまにある花嫁は、こうした花婿の偉大なる恋情にも、べつに感動もせずに重々しげに云った。『そんなにしつこく妾を追い廻すのでしたら、あなたを殺すかわりに、あたしは自分を殺します。』
そう言った眼差のたけだけしさに、弁護士はあっけらかんとして、べったりそこに腰をおとし、今宵の不首尾を打歎いてその夜を送った。世間の相愛の男女にとっては、楽しくもめでたい初夜を、彼は悲嘆と哀願と号叫と約束――何でも浪費してよい、黄金の茶碗で食べさす、領地や城館を購って、町娘から一廉の立派な上臈にする、八方いたらぬなき親切を尽す云々――のお世辞文句の裡にその一夜をあかし、仕舞にはもし妻が、愛の誉れの出会の槍を、良人に一回だけ折ることを許すならば、すっぱりと妻から離れて、その望む通りに、この生命を棄てても苦しゅうはないとまで申した。
しかし相変らず頑なな彼女は、朝方になって死ぬことなら許すと云い、彼女が与え得る果報は、ただそのことのみと申した。『妾が先日申したことは、金輪際本当です。ただあの折の約束とは違って、王様にこの身を任せるつもりですわ。ですから先に威したように、行きずり人や人足や車挽きなどには、許しませんから有難く思って頂戴。』
暁方になるや、彼女はスカートをつけ、婚礼衣裳をまた着て、望まざる花婿が依頼人の許に、しょうこと無しの用事で出掛けるのを、根気よく待った。そして弁護士が外出するや、大急ぎで彼女は王様を探しに町へ出た。が、弩[おおゆみ]の射程ほども行かぬうち、館のまわりを王の言附で見張っていた侍従に呼びとめられた。まだ貞操に南京錠をかけていた花嫁に、侍従はいきなりこう云った。『そこ許は国王を探しておられるのではありませんか?』『そうですわ。』『じゃ安心して私に何でも打明けて下さい。これからは互に助け合い、庇い合おうじゃありませんか。』とこの機敏な廷臣は肝煎り顔で、王の人となりや、王の心の掴み方や、今日は熱中し明日は冷却するそのむら気なことや、なにやかやを語り聞かせてくれた。金もふんだんに貰え、待遇も此上なしだが、ただ王を尻の下に敷くことを忘れぬようにとも、彼女に忠告してくれた。道々そんなためになる訓えをさかんにしてくれたので、イロンデル街のお屋敷に――ここは後にデタンプ夫人のお館になった――着いた時は、彼女はもうすっかり一廉の淫奔女[それしあ]に、教育されてしまっていた。
花嫁の姿が家に見えぬもので、可哀想な良人は、犬に吠え立てられた鹿のように泣き悲しんで、それからというもの、めっきり陰鬱な男になってしまわれた。コンポステル寺で本尊のサン・ジャックさまが讃仰される数ほども、彼は同僚から嘲りや恥じしめを受け、あれこれ悲観してすっかり憔悴し乾からびてしまったので、却って仲間うちの同情を惹くくらいになった。これら髯むじゃらの状師どもは、三百代言的根性から詭弁を弄して、こう判定いたした。すなわち弁護士どのは御内儀から、騎馬槍試合を拒まれておったゆえ、決してまだ寝取られ亭主とは申されぬ。また間男が国王以外の仁であったら、結婚解消に就いて訴訟を提起出来るに残念な次第だなどと抜かした。けれど弁護士は死ぬほど彼女にぞっこん惚れ込んでいたので、何時かは彼女を自分のものにしようというあてなし頼みから、王様に預けっぱなしにしておき、あとで一晩でも一緒に巫山の夢を結べたら、終生の長っ恥も物の数ではないとまで考えめされていた。なんと深くも愛したものでは御座らぬか。それなのに、かかる偉大なる恋愛を、嘲弄めさる殿方衆が世に多いとは、嗟乎!
かくて彼は相変らず彼女のことしか念頭になく、おのが訴訟や依頼人やちょろまかしごとや何やかやを、すっかり等閑に附してしまっていた。落し物を探し歩く吝嗇漢のような恰好で、彼は裁判所に出入し、うなだれ、放心し、気遣わしげで、遂にはある日なんど、弁護士連中がよく用を足す壁に向って、小便をしている積りで、評定官の法服に小便を引掛けてしまったことさえあった。
その間、彼の御内室は朝に晩に国王の御寵愛をかたじけなくし、また王様にも彼女に飽満あらせられたためしがおりなかった。それほど彼女は恋の道にかけて、縦横にあじな特技を発揮し、恋の火を燃やすのも消すのも巧みな、豪の手だれとなっておったのである。今日は王様を邪慳にあしらうかと思えば、明日は猫っ可愛がりに可愛がるという風で、変幻自在に手立てを尽し、深閨の座が賑やかで、粋で艶っぽく、陽気でさかしく、達者で、色の諸わけを皆式わきまえ、他の女子衆には到底出来ぬような、いびり方やじゃらつき方まで心得ておられた。
ブリドレ殿と申す仁は、トゥレーヌにあるブリドレの領地を彼女に捧げたが、恋の情を掛けて貰えぬ恨みから、自裁して果てられた。艶なる槍一突きのために、かく領地をも捧げて惜しまぬといったトゥレーヌの昔の伊達衆は、もう向後はござりゃまおすまい。さればこの殿の死は彼女をいたく悲しませた。それに懺悔聴聞僧も、この落命を彼女の咎目に帰したので、身は王の愛妾にありながらも、爾今はおのが魂を救済のため、領地もどんどん受領して、こっそり快楽を八方に頒とうと、内心誓った次第である。かくてこの時以来、町の尊信を彼女にあつめさせたあの大身代を、築き始めることと相成り、それと共に多くの縉紳を破滅から救ったが、なにせよその琵琶の調子を合わせることが巧く、またぬけぬけしい嘘が上手でもあったので、王様には臣下の者に福祉を授けるのに、彼女の力が大いに与っておったとは、ちっとも御存じにならなかった。いたくそのお気に召した彼女は、天井板を床板と、王に信じ込ませることもいと容易に出来たと申すのは、イロンデル街の下屋敷におられる時間の大部分を、王様にはもっぱら横臥の姿勢をお執りになっていたため、板のお見分けも覚束なくなってしまわれた故であった。王はたえず嵌物をあそばし、かの美しいしろものを擦り減らせるかどうかとお試みになったが、擦り切れたのは結局御自分で、後に好漢ついに色の病で果て給うたのである。それにまた彼女は心して宮廷でも一番に貫禄のある美貌な公達にしか肌身を許さず、従ってその御眷顧は、奇蹟のように稀れだったに拘らず、岡焼連中や競争相手は、一万エキュ出せば、しがない一介の貴族でも王者の快楽をほしいままに出来ると、蔭口いたしておったが、これはまったく跡方もない赤嘘であることは、いよいよ王と別れるという際、このことで王のお咎めを蒙った折り、彼女は王に傲然とこう答えた言辞に徴しても明らかであろう。『そんな出鱈目をわが君に申した奴を、あたしは唾棄します、呪います、三万遍も憎みます。あたしとの肉炙りに、三万エキュ以上出さぬようなしみったれなんか、ついぞ相手にしたことはございませんもの。』
すっかり震怒あそばされていたが、王にはこの返事を聞かれて御微笑を禁じ得なかった。そして世間の徒口[あだぐち]を鎮めるため、一ケ月近くもなおお手許にとめおかれた。到頭デタンプ夫人が競争相手の彼女を失脚させ、代って出頭第一の寵姫とも女御ともなられたのであるが、その失脚ぶりがまた羨しい限りと申そうか、お婿さんとして若い殿御をあてがわれ、その殿御もまた彼女に添って至極幸福を味わられた。というのは、あまり事を知らなさすぎて、罪作りとなっているような冷たい女人衆に、転売のできるくらい彼女にはぎょうに恋情と情火が豊かだったからである。
閑話休題[あだしことはさておき]、ある日のこと、王の愛妾は、飾紐やレースや小沓や襟飾などの恋の軍需品をもとめに、輿に乗って町に出られた。その形艶なことといい、綺羅を飾ったよそおいといい、彼女を見たもの誰もが、天国が眼前にひらけたのを見るような思いをいたした。別して若い坊主どもにはそうだった。ところがトラオワールの十字路の近くで、彼女は良人の弁護士にはたと出逢ってしまった。輿の外にその美しい片足を出し、ぶらぶら揺すっていた彼女は、蝮蛇でも見たように、慌てて顔をひっこめた。婚姻の宗主権を軽蔑して、亭主を辱しめつつ傲然と通り過ぎる御内儀が多いこの世に、なんと殊勝な志ではおりないか。『どうなさいました?』と尊崇やみがたく彼女に同伴していたド・ランノワ殿には訊ねられた。『なんでもないの。』と彼女は低い声で答えた。『あそこを通るのは、妾の良人ですが、可哀想に随分変ったこと。むかしは猿に似てましたが、今はジオブそっくり。』
哀れにも弁護士は、大口あけたままそこに立竦んでいた。熱愛の妻とその華車な足を目にして、心の張り裂けるのを覚えたあまりである。
聞いてランノワ殿は、大宮人の嘲弄口調でこう弁護士に言った。『あの方の良人というのに、お通り[パッセ]<*注1>を邪魔するって法があるかい?』
この洒落を聞いて彼女は大笑いをした。が、人の好い良人は、勇ましく荊妻を手にかける代りに、彼のあたまや心臓や肝玉や何やかやを断ち割る、その笑い声を聞くと、そのまま泣き出し、王の愛妾を見ながら、因果骨に活を入れようとしていた傍らの年寄の町人の上に、危く倒れかかった。蕾の時に我が物とした美しい花が、今は匂やかに咲きみちたのを見て、その白いむっちりした肌色、妖女のようなあじまやかな肢体に接し、一段と恋煩いを覚え、言葉では到底につくせぬほど、首ったけになってしまわれた。そうした恋慕地獄を知ろうとならば、べっかんこする情婦に、先ずは狂おしい恋をしての上でなければ、何とも思案に落ち申さずだが、それにしても当時の彼ほどの溺れ方は、たぐい稀れと申さねばなるまい。いのちでも財産でも名誉でも何でも、たった一度、肉と肉であえたら、すっかり犠牲にしてもいいし、その愛の大御馳走には彼の臓腑も腰も、置き去りにして参ろうと、堅く誓ったほどだったからで、その晩は夜もすがら、『おお、そうだ。必ず彼女をものにしてみせる。神様、私は彼女の亭主ではございませんか。なんたる不愍な身の上でしょう。』など云いながら額を叩き、かつかつ座にいたたまれぬうつけなていたらくであった。
さてこの世の中には偶然というものが幅を利かしておる。それを料簡の狭い連中は、超自然の遭遇だなんどと申し、信じようとはめさらぬが、しかし高遠な想像力をお持ちの仁は、まこととして真をおかれている。何故ならそう易々とは偶然を案出することがかなわぬからだ。で、左様な訳で弁護士が彼の愛の空頼みに望みをかけて、重苦しい徹夜に耽ったちょうどその翌日のこと偶然が彼に訪れたのである。即ち彼の依頼人のひとりで、常々王の御前に伺候していたさる知名の廷臣が、朝方、弁護士の許に参って、一万二千エキュほど即座に用立てる周旋をして貰えぬかと頼みに来た。この髯むじゃらの猫はそれに答えて、そんな大金は造作なく街角にころがっている代物ではござらぬと申し、担保や利子の保証が要るばかりか、腕組して一万二千エキュの金をぽんぽに擁しているほどの人は、この広い巴里にもたんとはいる筈がないから、それを見附けることが先ずは難事だなどと、屁理窟屋の言うような文句を並べた。『閣下、あなたさまは慳貪[けんどん]きわまる債権者をお持ちのようですな?』『そうなんだ。なにしろ相手は王の愛妾の一物ときている。が、このことは内緒だ。今夜二万エキュと俺のブリの地所を提供して、その味を試みるという寸法になっているのだから。』
聞いて弁護士は蒼くなった。弁護士の泣きどころに触れたように延臣は思ったが、凱旋したばかりとて、王の愛妾に良人があることなぞ、彼は一向に知らなかった。『顔色がお悪いようじゃが……』『ちょっと熱があるんでごあす。で、あなたさまが契約したり金を渡したりのお相手は、しんじつ王様のあれでございますか。』『そうだよ。』『誰が取持ちに入るんです?
それとも直々のお取引で?』『いや、そんな細かいとりきめやなんかは、小間使がやっている。これがまた凄い腕達者で芥子よりぴりっとしている女だ。王の目を掠めての夜の周旋ごとで、たんまり甘い汁を吸っているらしい。』『私の友人の高利貸[ロンバード]なら、或いは御用立ていたすかも知れません。したが血を黄金に変ずるという大錬金術師そこのけの逸物の代価を、小間使がここに来て受取らぬ限り、何とも出来ぬし、また一万二千エキュも鐚銭一文の値打もないというわけですな、フーン。』『そうなんだ。小間使に処方[アキット]<*注2>を書かせれば、占めたものなんだが。』
と笑いながら延臣は答えた。
小間使を寄越すようにと廷臣に頼んだので、案の定、金を受取りに、弁護士の処へ小間使はやって参った。晩祷に行く尼さんの行列のように、ずらりテーブルの上に、並べられたぴかぴかした金貨の美しさ輝かしさ気高さ頼もしさ若々しさと申したら、けだし無類千万。おそらく折檻最中の驢馬でさえ、にこりといたすに違いあるまい。が、弁護士は何も驢馬に見せつける為に、拡げた訳ではおりなかった。金の山を見た小間使はぺろぺろ唇をなめ、黄金に対して拝み文句を仰山に並べ立てた。折もよしと弁護士は彼女の耳の中に金臭芬々たる次の言葉を吹き込んだ。『これはお前さんにやるよ。』『まあ、あたしこんなにお代を頂いたことありませんが……』『おっと、と、お前の上に載せろというんじゃないよ。』そう云ってちょっと彼女を引寄せて続けた。『俺の名前をあの殿から聞かなかったかい?
なに、知らぬ!
そうか。何を隠そうお前がいまつかえているあの王様の堕落させたマダムの本当の良人は、この俺様なんだ。この金をあれに届けたら、またここへ戻って来てくれ。きっとお前の好みにもあうような条件で、お前にやる分の同額の金は、ちゃんと耳を揃えておくから。』
初め不審を起した小間使は、気が鎮まると同時に、弁護士に触れずに一万二千エキュ稼げるというのは、どうした訳かと知りたがって、すぐと間違いなく戻って来た。『さあ此処に一万二千エキュある。この金で領地も買えれば、男も女も買えるし、尠くも坊主三人ぐらいの良心は買収出来よう。だからこの金でお前の心も身体も上腹も何もかも、こっちのものに出来る寸法だ。で、俺はお前を信頼する。《与える者に与えよ。》の弁護士道の建前からだ。だからすぐこれからあの廷臣の処へ行って、今晩お楽しみの予定のところ、俄かに王様が夜分お成り遊ばされることになったから、今晩だけは他へ行って、その方の埒は明けるようにと、申して来てくれ、すれば俺にあの幸運児や国王の代理が勤められる訳だ。』『まあ、どうやってですの?』『俺はお前を買収したんだ。お前もお前の細工も、俺には頤使出来る筈なんだ。俺の女房と楽しめる手筈をつけるのは、お前にすればこの金を見る瞬き二つぐらいの造作もないことだろう。だがそうしたからとて、お前は決して神様に対し、罪を犯したことにはならないんだぜ。司祭の前でちゃんと式を挙げ、手と手を握りあった夫婦を結ばすことは、いったい敬虔な信心わざじゃなかろうか。』『わかりました。どうぞお出で下さい。夕食後明りを消して、真暗にしておきますから、たんと御堪能あそばせ。但し一言も口を利いてはいけませんよ。幸いあのお方は歓喜の絶頂には、口を利かずに叫ぶばかりですし、物腰でだけ用を弁ずる習いです。根が極めて内気なたちですから、宮廷の上臈衆のように、いやらしいことばをあの最中に弄することを、何よりもお嫌いあそばしているのです。』『おお、そうか。占め占め。じゃこの金はお前のものだ。もし俺が当然この拙者に属しているあの逸物を、ペテンにかけてでもこっちのものに出来たら、お前にこの倍の金は改めてくれてやろう。』
そこで時刻や入口や合図など、すべての打合せを済ませ、小間使は驢馬に金を積んで、しっかり宰領して戻って行った。寡婦や孤児や其他から、僅かずつ弁護士が搾って貯めた金も、万物が――もともとそこから出て来たわれわれの生命さえも、――溶かされてしまうあの小さな坩堝の中へ、運ばれて行ったわけだった。
さて弁護士は髯を剃ったり、香料を帯びたり、最上のシャツを着たり、息の臭くならぬように、玉葱を食べるのを控えたり、精力のつく物を食べ込んだり、髪に鏝をあてたり、裁判所の下卑助が、伊達な貴公子に身をやつそうとするいろいろな秘術と芸当を尽し、若い瀟洒な紳士を気取り、軽快闊達なところを見せようと、なんとかその醜い御面相を隠すべく心を挫いたが、所詮すべては無駄であった。何処までも三百代言の匂いが、ついて廻ったからである。美しいのと好きなので有名なポルチョンの洗濯小町が、ある日曜日、色男の一人に逢おうとおめかしして御秘蔵を洗い、薬指を御存じのところへ、ちょっと滑らせて嗅いでみて、《あら、いやだ。まだ臭いわ。青い川水で滌いでみよう。》と浅瀬でいきなり鄙育ちの貝母をごしごしやったような才覚は、この弁護士にはとんとなかったのである。べたべたとありとある化粧品を塗りたくったので、彼は世にも醜悪なつらになったが、自分では世界一の色男気取りでいた。
さて手短かに申し上げるといたそう。寒気は麻の輪が首吊りの頸を締めるように肌を引締めたが、彼は軽装して家を出て、大急ぎでイロンデル街にはせつけ、かなりの時間待ちぼけを食い、さては愚弄せられたかと思いついた頃、漸く真夜中になったもので、小間使が門を開けに来てくれた。弁護士は得々として王のお館へすべり込んだ。愛妾が休む寝床の傍らの忍び戸棚へ、小間使は弁護士を大事に閉じこめたが、その隙間から弁護士は、愛妾の美しいあらわなくまぐまを残りなく拝むことが出来た。ちょうど彼女は炉の前でお召換の最中で、何もかも透いて見える戦闘着に着換えつつあったからである。小間使と二人きりと思ってか、衣裳をつけながら、女子衆が申すなるあの埒もない事どもを彼女は口走っていた。『今夜のあたし、一万エキュぐらいの値打がなくって?
それにブリのお城がつくのだけれど頃合のお値段じゃないかしら?』
そう言いながら、稜堡のようにかたい二つの白い前哨を、彼女は軽く手で持ち上げてみせた。それは猛烈に攻撃されてもぐんにゃりいたさなかった代物ゆえ、今後幾多の強襲をも優に凌げるかに見えた。『あたしの肩だけだって、王国一つぐらいの値打はあるでしょう。王様だってこれに及ぶものは作れませんもの。けれど本当の話、あたしもこの稼業がそろそろいやになったわ。何時も骨折れるばっかりで、快楽なんかちっともありゃしない。』
小間使はにこりとしたので、愛妾はさらに申した。『お前に代って貰いたいくらい。』
小間使はさらに高く笑ってこう答えた。『黙って。あの人がいます。』『あの人って?』『御亭主さんです。』『どっちの?』『本当の。』『しッ、静かに。』
そこで小間使は一伍一什[いちぶしじゅう]を打明けた。愛妾の御愛顧をつなぎたいのと、一万二千エキュが欲しかったからである。『じゃ折角だからお金だけのことはしてやりましょう。けれどうんと凍えさせてやるがいいわ。あんな奴になんか触れられたら、肌のこの輝きも消え、妾までとんでもない醜い御面相になってしまう。だから妾の代りにお前が寝床に入って、お前の分の一万二千エキュを稼ぐがいいよ。彼奴には妾に計略がばれるといけないからと云って、明日の朝は早く帰ってお貰い。夜明けのちょっと前、妾は入替りに、彼奴の傍に行くことにするから。』
可哀想に良人は寒さでぶるぶる慄え、歯をガタガタいわせていた。小間使はシーツを探す口実で、忍び戸棚のところへ行って彼に言った。『もうじき暖かい思いが出来ますよ。マダムは今夜ははり切っておめかしをしていますから、さだめし結構なお相伴にあずかれるでしょう。けれど声を立てずに猛威を揮って下さいね。さもないと妾の身の破滅になりますから。』
到頭お人好しがすっかり凍え上った頃あい、やっと明りが消され紅閨のなかで、小間使はマダムに、殿方がお出でになっていますと囁き、そう云って自分が寝床に就き、マダムは小間使のふりをして出て行ってしまった。冷たい隠れ場から出た弁護士は、暖かいシーツの中に、得たり賢しともぐり込んで、『おお、なんて極楽じゃろう』と呟いた。
その通り小間使は、彼にまったくのところ十万エキュ以上のものを施しめされた。弁護士は王室の濫費と、町家のけちな支出との相違を、とっくり堪能をいたした。小間使はスリッパーのように笑いながら、その役割を上首尾に果してのけ、やさしい叫び声や、身の捩りや、藁の上の鯉のような跳躍や、痙攣的なとび上りで、弁護士をさかんに饗応して、言葉の代りにはア、アアで済ませた。彼女の数重なる要求に、弁護士も逐一これに充分なる回答に及んで、遂にはからっぽのポケットのようになって睡り込んでしまわれたが、終る前にこのあじな恋の一夜の記念物を手土産にしたいと思って、彼女の一跳躍に乗じて、毛を引抜いた。してそれはどこの毛か、吾儕はその場に居合せたのではないゆえ存ぜぬが、彼はこれを王の愛妾の生温かい貞操の貴重なる証拠品として、手の中にしっかと握りしめたのである。
朝方、鶏も啼き出したので、愛妾は良人の傍らに忍び込んで、睡った振りをいたした。小間使はやって来て、この果報者の額を軽く叩きながら耳許に囁いた。『お時間ですよ。早く股引をはいてお帰りなさい。夜が明けましたから。』
おのが宝物を残して立去るのを、ひどく悲しんだ弁護士は、消え失せた彼の幸福の源を見ようとした。と、証拠物件の検真の手続にと及んだ彼は、喫驚して言った。『おや、見たのは慥に金色だったが、これは黒いぞ。』『どうしたんです、数が足りないと、マダムが気附くじゃありませんか。』『うん、だが一寸見て御覧。』『まあ、何でも弁えていられる筈のあなたが、御存じないのですか。摘まれたものはすべて萎びて色が変るのは習いじゃありませんか。』とさげすむように云って、彼を追い出し、後で小間使と愛妾は大笑いをいたした。
この話は世間一般の評判となって、フェロンというこの哀れな弁護士は、おのが女房をものに出来なかった唯一人というわけで、とうとう口惜し死を遂げた。この一件から別嬪フェロニエルと、呼ばれるにいたったこの愛妾は、王と別れてのち、ブザンソワ伯爵という若い縉紳と結婚いたしたが、晩年よくこの佳話を人に語り聞かせて、三百代言の匂いを嗅がずに済んだと、笑いながら申しておったとか。
夫婦の軛をつけられるのをいやがる妻女には、あまり執着せぬがよろしいという、これはその訓え草である。
<注>
(1)「パッセ」には「経験する」「殺す」の意味もあって、ここでは三重の洒落になっている。(一)本文通り。(二)……良人なのに女房の味を知らぬ奴があるか。(三)……不義した妻を生かしておく法があるか。
(2)「アキット」には錬金術の「処方」という意味と、「領収証」という意味と二つあり、ここではその両方に掛けて洒落ている。
解説
王の愛妾 LAMYEDUROY
王とは「禁欲王」(Ⅱ)のフランソワ一世である。王がデタンプ公妃(一五〇八―一五八〇)と情交を重ねたのは一五二六年以降であるから、丁度その頃の物語であろう。愛妾フェロニエルは実在人物で、一五四〇年頃逝去しているが、レオナルド・ダ・ヴィンチの筆と誤り伝えられている彼女の肖像画が、今なおルーヴルにある。王に寝取られた弁護士がわざと花柳病に罹って、妻を通じて国王に感染させ、宝算を縮め参らせたという説もある。王が悪疾で御他界になったことは「金鉄の友」に見える。 この小説は種々の好色咄から材料を仰いだ模様で、例えば姦通宣言のくだりはブラントーム「艶婦伝」にあり、床に線を引く話は「新百話」の第二十三話、違う女性と添寝の話は「エプタメロン」、それが下婢だったという話は「デカメロン」の第四日第八話といった工合である。なお篇中のポルチョンの洗濯小町の娘は「当意即妙」「あなめど綺譚」(Ⅲ)に再出している。
編者注】「エプタメロン」の作者は、アンリ四世の祖母に当たるマルグリット・ド・ナヴァール 。「後退りの記(010)」でも言及した。