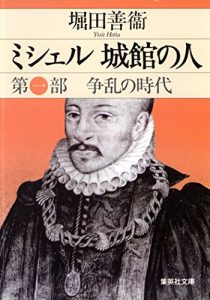◎ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」
◎モンテーニュ「エセー」(岩波文庫その他)
◎堀田善衞 「ミシェル 城館の人 第一部」(集英社文庫)
モンテーニュ「エセー」は、昔読んだ時には、深くは感動しなかった。というのは、青年期の生意気のせいか、あまりにも「常識」の範囲をこえず、生ぬるいといった印象だったからだ。しかし、堀田善衞の著作など読んでいると、それはごく表面的なとらえ方であるとの思いが強くなった。
さて、バルテルミーの虐殺後、わがアンリ四世は、その余燼ともいえるラ・ロシェルをめぐる攻防で、ユグノー征伐の隊列に加わるよう強制される。ラ・ロシェル攻防戦は前回、メリメ「シャルル九世年代記」でも紹介した。その行軍の途中で、モンテスキューと邂逅する。小説から、少し長い引用をすると、
連れの人は、宗教戦争ほど宗教に無関係なものはないという意見だった。途方もないことばだが、…宗教戦争はその根を信仰に持っていないし、人間を敬虔にすることもない。一方の人にとって、宗教戦争は野心の口実であり、他方の人にとって、それはみずからを富ますための機会にすぎない。全く、宗教戦争で聖者の現われることはない。逆にそれは民衆と王国を弱らせる。民衆も王国も他国の欲望の餌食にされてしまうのだ。
誰の名も言われなかったのだ。…カテリーナ(時の王国母)も、息子のアンジュー(後のアンリ三世)も、プロテスタントたちの名も。それでも彼の言葉は他の何人にも言えぬほど不敵なものだった。この言葉に襲いかかったのは怒涛や嵐だけではない。ほとんどあらゆる人間が怒号をもってこの言葉をおしつぶすところだったろう。国王さえも声を大にして言いえぬことを、貴人とはいえなみの人間があえて口にしているのに、アンリはいたく驚いた。
少なくとも、モンテーニュは、バルテルミーの虐殺をつぶさに見て、その頃の、「寛容」の意味するところ、「仕方なく相手を許す」との考え方をギリギリ守りながら、一歩も二歩もそこらから推し進めようとしたことが分かる。その過程を「エセー」本文と堀田善衞「ミシェル 城館の人」で辿るようにしたい。
旧ソビエトの小説家・ヤセンスキーの「無関心な人々」という小説の、題辞に、
友を恐れるな、彼は君を裏切るだけだ。敵を恐れるな。彼は君を殺すだけだ。無関心な人々を恐れよ。彼らの沈黙の同意があればこそ、この世に無数の裏切りと殺戮が存在するのだ。
というのがある。でも少し違うような気もする。昨今の政治情勢に引きづられるわけではないが、無関心な人々の語られぬ思いに、耳を傾けよ、そこにこそ、われらのかすかな希望があるのだ。モンテーニュも、痛苦な経験を経た上で、きっとそうつぶやいたに違いない。