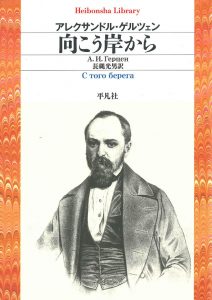◎アレクサンドル ゲルツェン「誰の罪」
まずは、ゲルツェン「ロシアにおける革命思想の発達について」(金子幸彦訳)の訳者の解説から。
ベリンスキイはその論文『一八四五年のロシヤ文学』(ー八四六)のなかでゲルツェンの小説『誰の罪か?』の特質について語っている。
「目的とか内容の空しさとかを意に介せずに、ときには無から作品を生み出すところのたかい芸術性というものを示している作品があるが、ゲルツェンのこの小説はこのような作品には属さない。しかしまたこれはつぎのような作品ーーすなわち空想力に欠けた作家が、あたかも論文のなかにおけるように、一定の道徳的問題についてのおのれの思想と見解とを発展させ、性格も動きもまったくないような作品ともちがう。『誰の罪か?」の作者は知力を詩にみちびき、思想をいきいきとした人物に変え、自己の観察の果実をー劇的な動きにみちた行動へ移す不思議な能力をもっている。全巻をとおして現実のなんという驚嘆すべき正確さが見られることであろう。すベては見事に調和している。ーーーつの余分なものもなく、一つの欠けたものもない。文体のおどろくべき独創性、そしてなんとゆたかな知力、ユーモア、機知、愛情、感情が見られることであろう。」
「誰の罪か?」の日本語訳は、今のところ、大正11年(1922年)の梅田寛訳しか刊行されていないようだ。そこで、利用規約などを参照すると、著作権フリーの文章を「翻訳・公開」するのは、OK のようなので、今回、「機械翻訳」による訳文作成を試みた。とりあえずは、作品の「梗概」などから…これも、ロシア語版Wikipediaおよび Wikiquote に掲載されているので、ライセンス的にはパスである。
「機械翻訳」なので、日本語的に意味が通じないところの「瑕疵」はあると思われるが、最小限に止め、基本はそのまま掲載する。なお、梅田寛訳を参照したところもあるが、逐一注記しない。
以上、したがって訳文の二次利用は可能であるが、訳文の正誤までは、当方の責任外である。
「誰の罪か?」の新訳が現れることを心から期待しつつ…
「梗概」
作者 Gertsen, Alexander Ivanovich
原語 ロシア語
執筆年代 1841-1846
初版発行1846年
出版社 Otechestvennye Zapiski「誰が悪いのか』(原題:Who’s to Blame?)は、アレクサンドル・イヴァノヴィチ・ヘルツェンによる二部構成の小説で、1841年から1846年にかけて書かれ、1846年に雑誌に発表された。ロシア初の社会・心理小説の一つであり、ロシアリアリズムの最初の作品の一つである。
プロット
村に住む地主のアレクセイ・アブラモヴィッチ・ネグロフは、息子のミーシャのために新しい教師を雇う。ドミトリー・ヤコヴレヴィチ・クルシフェルスキーである。
ネグロフ一家は、読書やその他の知的探求に馴染みがなく、家庭経営に積極的に参加することもなく、取るに足らない仕事に没頭し、大食と睡眠にふけっていた。無作法で無愛想だ。しかし、ネグロフの隠し子であるルバにとっては、このような生き方はまったく異質なものだった。そのため彼女は、同じくネグロフ家の生き方を受け入れられない教養ある青年クルシフェルスキーに近づく。二人は恋に落ちる。ドミートリ・ヤコヴレヴィチはあえて手紙で自分の気持ちを打ち明ける。クルツィフェルスキーの気持ちを察した家庭教師のエリザ・アウグストヴナが彼を助け、恋人たちのデートの約束を取り付ける。元来臆病なクルツィフェルスキーは、手紙を渡すためだけに夜のデートに出かけることにした。恐ろしくなった青年は、目の前にいたのがルボンカではなく、ネグロフの妻グラフィラ・ルボヴナであることを知り、手紙を忘れて逃げ出す。困惑したグラフィラ・ルヴォヴナもまた、イライザ・アヴグストヴナに騙された罪のない犠牲者となっていた。腹立たしく思った女性は、夫に手紙を渡した。アレクセイ・アブラモヴィッチは、この手紙が非常に好都合に発見されたことに気づき、隠し子という重荷を取り除くために、先生をリュボンカと結婚させることにする。結婚に先立つこのようなばかげた状況にもかかわらず、クルツィフェルスキフの家庭生活は幸せで、夫婦は互いに愛し合っていた。この愛の結実がヤーシャ少年であった。二人は家族ぐるみで仲良く暮らし、唯一の友人はクルポフ医師だった。
この頃、ネグロヴィー県の中心地であるネルン市に、それまで長い間不在だった裕福な地主ウラジーミル・ベルトフが外国からやってきた。彼は貴族選挙に参加するつもりであった[6]。彼の努力にもかかわらず、NNの住民はベルトフを仲間に受け入れず、ベルトフにとって選挙は時間の無駄であった。ある民事事件のためにNNに留まることを余儀なくされたベルトフは、自分の居場所を見つけようとしたこの試みも失敗に終わったことに絶望する。彼はほとんど完全に孤立し、NNでの唯一の友人はクルポフ医師だけだった。彼はベルトフをクルシフェルスキー家に紹介する。ベルトフとクルツィフェルスキー一家は、新しい出会いをとても喜ぶ。ベルトフは自分の考えやアイデアを分かち合う相手を得、クルツィフェルスキーは彼の中に、自分たちの内面を豊かにすることのできる、高度に発達した人物を見出す。かつてネグロフ家でリューバとドミトリが理解し合ったように、彼らは言葉半分、目半分で理解し合う。リューバとベルトフの一致は、大きなもの、愛へと発展していく。気持ちを隠しきれなくなったベルトフは、クルシフェルスカヤに告白する。そして一気に3人の人生を破壊する。リュボフ・アレクサンドロヴナは夫から離れられず、ベルトフも愛しているが、夫を愛している。クルツィフェルスキーは、自分がもはや以前ほど愛されていないことに気づく。ベルトフは、最も親しい人の人生を台無しにしてしまったという思いに苛まれ、彼のそばにはいられない。街中に噂が広まる。クルシフェルスキーは酔いつぶれている。クルポフ医師は起きたことに罪悪感を覚える。ベルトフは、自分もクルチェフスキーに劣らず苦しんでいること、自分の感情をコントロールできないこと、リュボフ・アレクサンドロヴナは夫より身近な人を見つけたが、以前のように幸せになることはないだろうと断言する。他に出口がないと考えたベルトフは、クルポフと同意して旅立つことにした。彼は再び祖国を去る。
リュボフ・アレクサンドロヴナは枯れていく。クルーツィフェルスキーは酒を飲んでいる。別れは幸福と心の平安をもたらさなかった。未来は悲しく暗い。登場人物
アレクセイ・アブラモヴィッチ・ネグロフは退役した騎兵少将。「太った、がっしりした男。裕福な地主。1812年の戦争に参加。引退してモスクワに定住し、その後、怠惰から村に移り住む。村では農奴の娘ドゥーニャと結ばれ、リューバをもうけた。村での生活も退屈になり、彼はモスクワに戻り、結婚を決意するまで、再び怠惰な娯楽に耽った。ドゥーニャとその娘は不名誉なことになり、精神病院に送られた。結婚後、ネグロフはミーシャとリサという子供をもうけた。世俗的な生活に飽き、すっかり怠惰になった夫婦は、ついに村に移り住んだ。
ドミトリー・ヤコヴレヴィチ・クルシフェルスキー – モスクワ大学物理数学科卒業。地区医師ヤコフ・イヴァノヴィチとドイツ人女性マルガリータ・カルロヴナの息子。ヤーコフ・イヴァノヴィチの診療所は悲惨な状態で、一家は貧しかった。一家には5人の子供がいたが、3人は猩紅熱で死に、長女はどこかの下士官と駆け落ちし、ミーチャだけが残された。ミーチャは病弱だったが、母親の努力で生き延びた。ある慈善家が地元の体育館を訪れ、そこでミーチャに目を留め、モスクワ大学で学ばせたいと申し出たのだ。大学の物理学科と数学科を卒業したドミートリ・ヤコヴレヴィチは、就職先を見つけることができず、状況はますます悪くなっていった。そんな矢先、ネグロフの寛大な申し出があった。
グラフィラ・ルボヴナ・ネグロヴナは、アレクセイ・アブラモヴィッチ・ネグロヴの妻だった。浪費家の伯爵と商人の娘である彼女は、マヴラ・イリニシナ伯爵夫人に育てられた。伯爵夫人は姪に対して非常に厳格で厳しかった。結婚が彼女の運命を好転させた。
セミョン・イヴァノヴィチ・クルポフ医師は医学委員会の検査官である。クルポフは『クルポフ博士』の中で、万病説を展開する。
リューバは、アレクセイ・アブラモヴィッチ・ネグロフと農奴の娘ドゥーニャの隠し子である。ネグロフの結婚後、彼女はルドメンスカヤに追放されたが、グラフィラ・ルボヴナの取り成しのおかげで紳士の家に戻され、貴婦人として育てられた。
ウラジーミル・ペトロヴィチ・ベルトフは裕福な地主で、元公務員であった。ベルトフの母ソフィは農奴だった。女主人は、利益を上げるために、農奴の娘数人を家庭教師にすることにした。その中には、後にウラジーミルの母となる女性も含まれていた。教育を受けたソフィーは、近所の地主に売られた。その地主の若い甥は、放蕩三昧の生活を送っていたが、ソフィーに目をつけたが、驚いたことに拒絶された。哀れな少女は仕方なく、地主にタダにしてくれるよう懇願し、サンクトペテルブルクに逃れた。しかし、ベルトフが流した噂が彼女の評判を落とし、どこにも居場所を与えられなかった。窮地に追い込まれたソフィーは、ベルトフに怒りの手紙を出すことにした。その手紙に心を打たれたベルトフは、自分のしたことを深く悔い改め、その結果、二人の関係は結婚に至った。やがてベルトフは2歳の息子を残して亡くなった。教育の重荷はすべて、母親と家庭教師のスイス・ヨーゼフの肩にのしかかった。成長したウラジーミルは、モスクワ大学法学部に入学した。同大学を卒業後、サンクトペテルブルクに奉公に出た。ロシア官界の堅苦しい雰囲気に馴染めず、半年後に退官。医学や美術に携わろうとしたが、こうした活動もすぐに冷めてしまった。恋愛に失敗したベルトフは、異国の地へ赴く。
創作の歴史
作者の紹介によれば、この小説は1841年に亡命先のノヴゴロドで書き始められ、最初の部分もそこで書かれた。モスクワに到着後、ゲルツェンは書き上げた作品を友人たちに見せたが、彼らは気に入らなかった。この原稿はベリンスキーに高く評価された。
編者注】画像は、ベリンスキーの肖像(Wikipedia から)