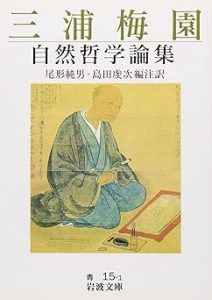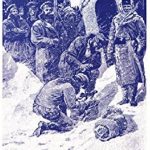◎神西清訳 チェーホフ「シベリアの旅」(08)
八
シべリヤ街道、 これは世界ぢゆうで一番大きな道だ。また一番單調な道かも知れぬ。チュメーンからトムスクまでは、それでもまだ我慢が出來る。と言っても決して役人のお蔭ではなく、この地力の自然的條件の賜物である。この邊は森林のない平原で、 朝降った雨も夕方には乾いてしまふ。若しまた五月の末になっても雪解がやまず、 街道が氷の小山で蔽はれてゐるやうなら、 勝手に野原を突切って廻り路も出來るわけである。トムスクから先は大密林と丘陵の連續だ。こつでは地面はなかなか乾かず、 廻り路などはしようと思つても出來ない。厭でも街道を行くことになる。そこでトムスクを過ぎると旅行者が急にロ喧しくなって、 不平帳にせつせと書き込むやうになるのだ。役人諸君も几帳面に彼等の不平を讀んで、 一々「詮議に及ばず」と書いて行く。書くなんて餘計な手間だ。支那の役人ならとつくに印判にしてゐるだらう。
トムスクからイルク—ツクまで、 二人の中尉と軍醫が一人道伴れになった。中尉のの一人は步兵で、 毛むくじゃらな毛皮帽を被つてわる。もう一人は測量將校で總肩券附けてゐる。宿場に着くたびに、 馬車の遲さと動搖とでくたくたになった上に泥だらけで、びしょ濡れで、 睡くてならぬ私達は、早速長椅子に轉がって不平を連發しだす。――「やれやれ、 何て汚ない何てひどい道だい。」すると驛の書記や各主がかう答へる。――
「これ位はまだ何でもありませんよ。まあ見てゐて御覽なさい、コズーリカ越えはどんな工合だが。」
トムスクから先は、宿場に着くたびにこのコズーリカで威かされる。書記たちは謎みたいな笑ひを浮べ、行き合ふ旅人は意地の悪い笑顏で、 かう言ふ ――「私は越して來ましたよ。今度は君の番ですね。」あまり威かされるので、化舞には神祕なコズーリカが嘴の長い綠色の眼をした。鳥になって、夢にまで現れて來ろ。コズーリカといふのは、チェルノレーチェンスカヤとコズーリカの兩驛間二十ニ露里の道を指すのだ(これはーノチンスクとクラスノヤールスク兩市の間に當る)。この怖ろしい場所の手前二三驛あたりから、旣に豫言者が出現しはじめる。行き合った一人は四度も顚覆したといふし、 もう一人は車の心棒を折ったと零すし、三人目は難しい顏をして物も言はない。道はいいかと訊いて見ると、かう答へる,「いやはや結構の何のって。」とりわけ私を見る人々の眼は、死者を悼む眼附に似てゐる。何故なら私の馬車は自腹を切って買った車だからだ。
「きっと毀して、泥んこの中へ陷りますよ」と、 溜息まじりに言って吳れる、「惡いことは言はない、 驛馬車になさい。」
コズーリカに近づくにつれて、豫言者は次第に物凄くなる。程なくテェルノレーチェンスカヤ驛といふ邊で、道伴れの乘つた馬車か引繰り返つた。夜だった。兩中尉も軍醫も、 トランクや包みや碁石やヴァイオリンの函もろとも、泥んこめがけて飛んでしまつた。その夜中には今度は私の番だった。愈ヽチェルノレーチェンスカヤ驛といふ間際になって、 私の車の軸釘が曲ったと急に版片が言ひ出した。(これは車臺の前部と軸部とを結ぶ鐵のボルトだ。だからこれが曲ったり折れたりすると、車體は地面に腹這ひになってしまふ。)宿場で修繕がはじまる。むかつくほど大蒜や玉葱の臭ひをさせる馭者が五人掛りで、泥んこの車を横倒しにして、曲った軸釘を金槌で打ち出しはじめる。まだ何とかいふ橫木も割れてゐる、何やらの舌も她んでゐる、ナットが三本も飛んでゐるなどと、彼等は口々に吿げる。が私には何ひとつ分らない。また分りたくもない。……暗いし、寒いし、退屈だし、睡い。……
宿場の部屋に簿暗いランプが燃えてゐる。石油と大蒜と玉葱の臭ひがする。長椅子の一つには毛皮帽の中尉が橫になつて眠ってゐる。もう一つの長椅子には何やら髯の長い男が坐つて、て、大儀さうに長靴を穿いてゐる。今しがた電信の修理に何處やらへ行けと命令を受けたのだが、睡いので出掛けたくないのである。總肩章の中尉と軍醫とは卓に向つて、重くなった頭を兩手に支へて居睡りしてゐる。毛皮帽の舟聲が聞え、外では金槌を打つ音がする。
馭者の話聲も聞える。……かういふ宿場の話といふと、 街道ぢゆうを通じて話題は一つだ、 つまりその土地土地の役人の月旦と、道路の惡口とである。遞信關係の業務はシベリヤ街道に沿ひ謂はば君臨してゐるだけで、別に政治を布いてゐるわけではないのに、天の憎みを蒙ることが最も甚だしい。イルクーツクまでまだー千露里以上の道程を扣へながら、 すでに困憊し切ってゐる旅人の耳には、 宿場の物語は唯々凄まじく響く。何とかいふ地理學會の會貝が、細君を伴っての旅行中に二度も自分の馬草を毀し、とどのつまりは森の中で一夜を過ごさなければならなかった話、何とかいふ貴婦人があまり搖れが酷いため頭を割ってしまった話、何とかいふ收稅吏が十六時間も泥濘のなかに坐り績けて、たうとう百姓に二十五ルーブルやって引張り出して貰ひ、宿場まで送り屆けられた話、 自用の馬車は一臺として無事に驛まで行き通した例しがないといふ話。かういふ話がみんな、まるで不吉な鳥の啼聲のやうに胸に響き返るのである。
さうした話から推すと、 最も苦勞の多いのは郵便であるらし.い。もし篤志な人があって、ペルミからイルクーツクに至るシベリヤ郵便の動きを丹念に追って、 その印象記を書きとめるなら、さだめし讀者の淚を誘ふやうな物語になるだらう。それは先づ、宗敎、敎化、商業、 秩序、金錢などをシベリヤに齎らすこれらの皮製の梱や叺の總てが、怠惰な汽船がいつも汽車との連絡に;..!にはいといふだけの理由で、空しく幾晝夜かをペルミに停滞するところから始まる。チュメーンからトムスクまでは、春も六月に入るまで、郵便も河川の凄まじい氾濫と這ひ出ることも出來ぬ泥濘と闘ふ。氾濫のお蔭で、ある宿場にー畫夜ちかく待たされたことがあった。郵便もやはり待つてゐた。重い邺便物を小舟に積み込んで、河や水浸しの牧地を渡す。その小舟が顚覆を免れるのは、シベリヤの郵便夫のため、その母親が恐らく熱い祈りを捧げてゐればこそである。さてトムスクからイルクーツクまでには、コズ—リカだのチェルノレーチェンスカヤだのといふ難所が數知れずあって、郵便馬車は十時間乃至二十時間づつも泥濘の中に立往生する。五月二十七日に或る宿場で聞いた話では、郵便物の重みでカチャ川の橋が落ちて、馬も郵便も危く沈んでしまふ所だつたといふ。こんなことは普通の事故で、シベリヤの郵便はもう夙に慣れつこになつてゐるのだ。イルクーツクを發って先へ進む途で、六晝夜の間もモスクヴァからの郵便に追ひ抜かれなかったことがある。つまり郵便が一週間以上も遲れてゐた譯で、まる一週間何かの事故に引き留められてゐたことになる。
シベリヤの郵便夫は殉敎者だ。その負ふ十字架は重い。彼等は英雄だ。祖國が頑迷にも認めようとしない英雄だ。彼等ほどに勞働し自然と鬪ふ者は、他にはゐない。時には堪へられぬほどの苦勞も嘗める。しかも、 彼等が免職され解雇され罰金を課せられる度數は賞與を受ける度數に比して頗る頻繁だ。諸君は彼等の月給の額を知つてゐるだらうか。諸君は生涯に一度でも、 郵便夫が褒章を着けてゐるのを見たことカあるだらうか。「詮議に及ばす」と書く人達などより、 彼等はずっと有用かも知れぬ。だが見るがいい。彼等が諸君の前に出ると、どんなに怯えたち、どんなにおどおどしてゐるかを。……
だが、やっと修繕が出來たと言って來た。これで先へ進める。
「起き給へ」と、軍醫が毛皮帽を起す、「呪はれたコズ—リカなんか、 さっさと越してしまふのが一番だ。」
「いや皆さん、 繪で見るほどに惡魔は怖くないと言ひましてね」と、 長髯の男が慰める、「なあに、コズーリカだって、他の宿場よりちつとも惡いことはありません。それにもし怖けりや二十二露里ぐらゐ步いたつて譯はありませんや。」
「さう‘泥んこに陷りさへしなけりやね……」と、 書記が言ひ添へる。
空が朝焼けけに染まりはじめる。寒い。立場の構內を岀もせぬうちから、もう馭者が言ふ、 ――「何て道だね、やれやれ。」最初は村の中を行く。……車輪を沒するどろんこの泥道があるかと思ふと、 今度はからからな丘になる。かと思ふと粗朶や棧道を渡した卑濕地に出る。それもどろどろの糞を被ってゐるうへに、丸太が肋骨のやうに突き出て、渡るとき人間の魂は反轉し、馬車の前は摧ける。……
だが村が盡きた。怖るべきコズ—リカに差し掛る。成る程ひどい道てはあるが、といつてマリインスクや例のチェルノレ—チェンスカヤあたりの道にくらべて、 別段惡いとも思へない。幅のひろい森の切通しかあってそれについて幅五間足らずの粘土と塵芥の堤が、ずつと續いてゐると想像して見給へ。これがつまり街道だ。この堤を横から眺めると、 樂器の蓋を外した胴みたいにオルガンの太い心棒が地上に突き出て見える。その兩側には溝がある。心棒の上には、深さ一尺以上もある辙の跡が何本も走り、またこれを橫切る夥しい轍がある。從って心棒全軆は一群の山脈狀を呈し、それなりにカズベック*もあればエリブルース*もある。山巔は乾いてゐて車輪に突き當るし、麓の方はまだ水をはねかす。よつぽど巧みな奇術師でもなければ、 この堤の上に馬車を平らに据ゑることは難しいだらう。先づ大抵、 馬車はまた慣れぬ諸君が「おい馭者 、引繰り返るぢやないか!」と、 思はす一分毎に怒鳴り出すやうな位置をとる。右側の車輪が二つとも深い轍に陷り込み左の車輪が山巔に突き立つかと思ふと、二つの車輪が泥濘にめり込み、第三の車輪は山巔に、第四は空に廻ってゐる。……馬車の位置が千變萬化するにつれて、諸君が頭を抱へたり横腹を抱へたり、四万八方へお辭儀をしたり舌を嚙んだりする傍では、トランクや箱が大騒動をして、互ひに重なり合つたり諸君の上に被さったりする。だが版者を見給へ。この輕業師は何と上手に馭者臺の上に坐ってゐることだ。
もし誰かが私達を橫から眺めたら、 あれは馬車で行くのではない、氣が觸れたのだと言ふだらう。少し先の所で、 私達は堤から離れようと思ひ、 棧道を探しながら森の緣を辿った。だがそこにも轍があり、小山があり、肋骨があり、棧道がある。暫く行くと馭者は車を停めた。ちよつと考へてゐたが、やがて、さあ愈ヽ愚劣千萬なことをやりますぞと言ふやうな表情で力無く咳拂ひをすると、堤の方へ馬首を轉じていきなり溝へ乘り掛けた。物の爆ける音がする。前の車輪ががちやんと行き、次いで後の車輪もがちやんと行く。溝を越すのである。それから堤へ乘り上げるときも、 矢張りがちやがちやんと鳴る。馬から湯気が立つ。梶棒が裂ける。尻帯も頸圈も橫へずれてしまふ。……「ほうれ、大將」と、馭者は力一ぱい鞭を振りながら叫ぶ、「ほれさ、御兩人。ぼやぼやするなってば!」十步ほど馬車を引きずつたかと思ふと、馬は停つてしまふ。幾ら鞭をやらうが、喚かうが、今度は動かうともしない。仕方がない。また溝を乘り越えて堤を下りる。また抜道を探す。それからまた逡巡して、車を溝へ向ける。限りがない。
かうして乘って行くのは辛い。實に辛い。だが、 このみつともない痘痕だらけの地の帶、この黒痘痕が、ヨ— ロッパとシベリヤを繫ぐ殆ど唯一の動脈であるのを思ふ時、心は一層暗くなる。人々は一軆、 どの動脈を通ってシベリヤへ文明が流れ入ると言ふのか。如何にも、 彼等の喋々する所は實に多い。だがこれを若し、馭者なり郵便夫なり、それともヨーロッパ へ茶を送る荷車の列の傍で泥濘に膝まで潰かつて、びしよ濡れに泥を浴びてゐる農民なりが耳にしたとしたら、彼等のヨーロッパ及びその誠意に對する感槪は果してどんなものであらうか。
序でに荷車の列を見て置き給へ。四十臺ほどの車が茶箱を積んで、 堤の上に續いてゐる。……。車輪は半ば轍の深みに隱れ、瘦馬が一齋に頸をのばす。……車の傍には運搬夫がついて行く。足を泥濘から引つこ抜いたり、 馬に力を借したりで、精も根もとつくに盡きてゐる。……列の一部が停ってしまった。どうしたのだ。一臺の車の輪が碎けたのだ。……いや、もう見ない方がいい。
へとへとになった馭者や郵便夫や運搬夫や馬を、まだ嘲弄し足りないのか、誰やらの差圖で煉瓦の碎片や石塊が道の兩側に盛り上げてある。これは、 間もなく道がもっと酷くなるぞといふことを、 瞬時も忘れさせぬためである。シベリヤ街道に沿ふ町や村には、道路修繕の名で月給を取る人間がゐるといふ。これが若し本當なら、どうそ修繕には及びませんと、月給を上げてやらなければなるまい。彼等の修繕に逢ふと道は益ヽ惡くなるばかりだから。百姓の話では、 コズーリカなどの道路修繕は次のやうにするのだといふ。六月の末から七月の初めにかけては、 この土地の「埃及の災*」として殼物につく蚊の盛んに發生する季節だが、 その頃になると人人を村から「驅り出し」て、指の間で擦り潰せる程からからな枯枝で、 乾いた轍や穴を埋めさせる。修理の仕苦は更か終るまで續く。すると雪が降って船醉ひを起させるほど搖リ上げ搖り下ろす世界無類の穴ぽこが、 道路一面に出來る。それから春の泥濘が來る。また修理が始まる。これが連年の行事である。
トムスクの手術で或る評議貝と知合ひになって、 三二驛のあひだ一緖に行ったことがある。私達が、とあるユダヤ人の農家に坐って鱸のスープを食べてゐると百人頭がはいって來て、何處共處の道略がすつかり損じてゐるが‘そこの請負人が修理をしようともしないと、評議員に報告した。……
「ここへ呼んで來い」と評議貝は命じた。
暫くすると頭の毛のもぢやもぢやな小男の土百姓が、 顔を歪めて這人って來た評議員は威勢よく椅子を起つて、百姓めがけて突進した。……
「この恥知らず奴。何だって道を修理せんのか」と彼は泣聲で呶鳴りはじめた。「道は通れん、 頸つ玉は折れる、 知事の報吿は飛ぶ、 何もかもこの俺の罪になる。ええ、この惡黨め。呪はれたこのへちゃむくれ奴。――それでいいと思ふか、ああん。何たる貴樣は穀潰しだ。明日はちゃんと通れるやうにして置け。明日引き返して來て、萬一まだ直ってゐなかつたら、 しやつ面ひん吳れるぞ。跛にして吳れるぞ。出て行け!」
土百姓は眼をばちくりさせて、 汗だくになった。益ヽ歪んだ顏附をして、扉から消え失せた。評議員は卓子に歸って來ると、 坐るなりにやにや笑ってかう言った。――
「左様、そりや勿論ペテルブルグやモスクヴァの後ぢや、 ここの女はお氣には召しますまい。だが、じっくりと捜して見れば、ここにだって娘はをりますで……」
土百姓が明日までに間に合つたかどうか知りたいものだ。この短い間に一體何が出來るだらうか。シべリヤ街道にとって幸か不幸かは知らないが、評議員は長くその椅子にとどまらない。その交送は頻繁である。こんな話も聞いた。――ある新任の評議員が持場に着くや占や、百姓を驅り出して道の兩側に溝を掘らせた。その後を襲つた男がまた、前任者の奇行に負けまいと、百姓を驅り出して溝を埋めさせた。三人目は持場の道路に、.厚さ一尺餘の粘土を敷かせた。それから四人目、五人目、六人目、七人目も思ひ思ひに、せつせと蜜を蜂巢へ運んだ。……
一年中を通じて道路は通行に適しない。春は泥海で、春は小山と穴と修理で、冬は陷し穴で。嘗てヴィーケリや、後れてはゴンチャローフの息の根をとめたと言はれる疾走は、今日では冬、雪の初路ででもなければ想像し得ぬところだ。現代の作家も、シベリヤを术ばす壯快さを書いてにゐる。だがこれは、苟もシベリヤに來て、よし空想でなりと疾走の壯快を味はないでは、 引つ込みがつかぬからである。……
コズーリカが軸棒や車輪を毀さなくなる日を待つのは、空頼みも甚たしい。シベリヤの役人たちがその生涯に、道路が改善されるのを見たことがあらうか。この儘の方がお氣に召すらしい。ド平帳も通信記事も、シべリヤ族行者の批評も、修理に計上される金額と同様、道路には殆ど利目がない。……
コズーリスカヤ驛に着いたときは、 もう日が高かった。道伴れには先へ行つて貰つて、 私は馬車の修繕に殘つた。
【注】
*カズベック コ—カサスの高峯。氷のピラミッドをなし、高さ一萬六千五百呎。
*エリブル—ス コーカサス主山脈め最高峯。東西の兩峯があって、ともに一萬八千呎を超える。
*埃及の災 エホバが、十の災(血に化する水・蛙・蚤 蚋、獣疫、腫物、雷雹、蝗、暗黑、長子の死)をエジプトに降した說話。『出埃及記』第七章――第十二章。
*ヴィーゲリ 『囘想錄』の著がある。(一七八七―一八五六)
*ゴンチャローフ 『オブローモフ』の作者(一ハ一ニ―九一)が提督ブーチャチンの祕書として、海路遙々日本を訪問したのは一八五三年(嘉永六年)である。その翌年彼はシベリヤを橫斷して歸つた。