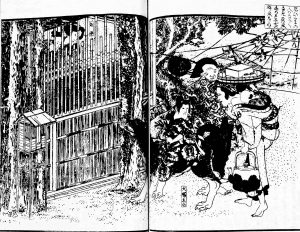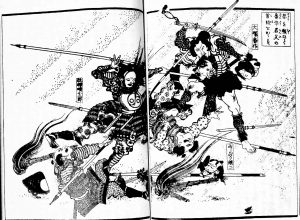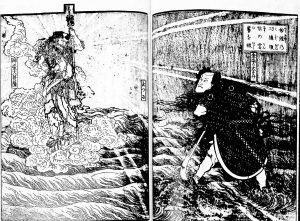◎ 宮本研「日本人民共和国」
まずは、題字…
«この敗北で斃れたのは、革命ではなかった。斃れたのは、革命以前の亡霊であり、それまで断ち切れずにいたさまざまの、人物や幻想や観念や計画であった。»—マルクス『フランスにおける階級闘争』
歴史に、「もし」(if)という過程はあり得ない。しかし、その都度々々にときに垣間見せる、オルタナティブパスウェイ(別の道筋)を想像し、芝居などに現実化することができる。それも過去の局面により、濃淡が出てくるような時代がある気がする。その一時期が、1945年の敗戦後、幾ばくも経っていない時代の特質であろう。
時代背景は、1946年夏から1947年春にかけて、敗戦直後の、2.1ゼネストをめぐる労働組合の事務所が主な舞台である。まず劇冒頭から、当時の権力関係を如実に反映し、時の占領軍(GHQ)のエージェンシーの役割を担った、黒田が登場する。労働組合の中に、「協力者」を物色するためだ。
第一幕
<一九四六年――夏>
機関銃の音が、眠っている記憶をよびおこすように、遠くからひびいてくる。
紗幕の向うに矢田部がうずくまっている。声(黒田)あれから一年。……ちょうどひとまわりして、また夏がやって来たな。お前はまだ、そこにそうやってうずくまっている。矢田部、もういいじゃないか。
そこにそうしているのはもういい。……お前はもう、第六航空軍三十三戦隊の兵長じゃない。……戦争は終ったんだ。戦争だけじゃない。戦争を終らせまいとするおれたちの努力もまた終ったんだ。舞台の下手に、黒田の姿。
黒田 ……歩きはじめてはどうなんだ。どっちの方向だろうと、おれはもう、命令もしなければ制止もせぬ。おれはもう、お前の上官でもなければ同志でもない。……立てよ。矢田部。歩き出すんだ。おれたちの、お見事な誤算でしかなかった努力が終って一年。……動いてみろ、矢田部。でなければ、お前がおれたちから離れていった意味なんかない……
矢田部は、かっての兵隊当時の部下、どうやら「戦争遂行工作」に加担させたらしい。その矢田部は、やがて、労働組合活動の中心人物となってゆく。やがて、その運動の最大の高揚期、1947年2月1日を期する、2.1ゼネストの遂行が大きな課題となる。
矢田部 日本は負ける、負けた方がいいなんてふざけたことを考えてた野郎がいて、しかし、結局こうして、その連中のいう通りになっちまったなんて、本当をいうと、今だって歯ぎしりだ。…そしたら、キャップがいうんだ。……社会ってな……世界っていったつけかな…一度出来上ったら、ハンダでくっつけたみてえに百年千年動かねえもんじゃねえ。いくらだって変るし、変えられる。事と次第によっちゃ、土台からやりかえることだって出来る。おれたち、それをやってるんだっていうんだがね。
文 そうよ。
矢田部 そういわれても、まだ、合点がいくわけじゃねえけど、 ……しかし、パリ・コンミュ—ン、あいつはいいな。
文 パリ ・コンミュ—ン。
矢田部 フランスは戦争に負けた。けど、責任をとらなくちゃいけねえのは戦争おっばじめたやつなんで、鉄砲もたされパンパンやった兵隊じゃねえ。捕虜になっちまったボナバル卜の野郎はそっちにくれてやる。おれたちはおれたちのフランスをつくる。……パリ・コンミュ—ン。
文 労働者がっくった、世界で初めての労働者の政府。
矢田部 軍隊と警察を廃止して労働者が武装した。……裁判官や検事の賃金を労働者と同等に切り下げ、工場のリストをつくって労働者に引き渡した。……共和制の自治政府。
文 パリ・コンミューン。
矢田部 パリ・コンミューン。
ゼネスト直前になり、GHQ のスト中止命令が出る。その時も矢田部は、独自の活動で、大勢の動向に抗しようとするが…
終幕近くで、GHQ の「手先」黒田が登場する。この芝居を見事に芝居たらしめるような、この「枠組み」は、時の権力関係を象徴したようでもある。
矢田部 (冷ややかに)……何しに来た。
黒田 お前に、お別れをいおうと思ってな。
矢田部 ……
黒田 おれは昨夜ここにやって来た。……なぜだと思う?
矢田部 おれは、引き受けてなんかいない。何も頼まれてなんかいない。
黑田 しかし、お前はおれに頼まれたとおりのことをやった。しかも、組織にたてついてまでもだ。…….昨夜、おれはこの部屋に来た。……もう一度聞くが、何のためだと思う?
矢田部 ……
黒田 おれの頼みを聞いてくれるかどうかを見届けにじゃない。おれは、お前にゼネストをやめさせようと思って来たんだ。
矢田部 (思わず黒田を見る)
黑田 アメリカさんは、本当はゼネストに突入してもらいたかったんだ。……禁止命令は出した。しかし、どこか一つ位向う見ずのところが出て来るだろう。そしたら、それを口実に全体を叩く。そして、終戦からこっち、ブレーキの利きにくくなった左翼を一挙に撃滅する。……分ってるだろうが、やつらはもう、左翼の友軍じゃない。……お前はそのワナにかかろうとした。おれはお前に、それを教えてやろうと思った。しかし、お前はやった。
矢田部……
黒田 お前はやっとお前の戦争に勝ったようだな。ゼネス卜は負けた。しかし、そんなことはどうだっていい。お前たちはアメリカさんに中止命令というド口をはかせたんだからな。その上、お前は自分にも勝った。これから先、お前がどんな道を歩くのかは知らん。しかし、お前はもう、成功も失敗も、人のせいではなくて、自分の責任として引きうけてやっていけるだろう。……おれは駄目だ。生きてる世界がだんだん狭くなって来た。これでいい。だから、お前とはこれでさよならだ。お前はよくやった。……元気でやれ。……もう、ここにも来ない。
(中略)
党員1 矢田部君。……うまくいえないんだけど、このままでは、もう駄目かも知れないね、党。党員1、静かに出て行く。
文 矢田部さん…あたし、行くわ。
矢田部、答えない。
文、出て行く。
歌声が急に高くなる!矢田部、はじかれたように立ってドアをうしろ手に閉める。……その視線の方向に、一枚だけ残ったスローガンが垂れている。
今から考えると蛇足のようであるが、この場面で、観劇していた「前衛党員」は、怒って軒並みに席を立ったようだ。心情的に分からぬわけではないが、その後の党の推移もまた象徴している気がしてならない。
繰り返しになるが、歴史に「if」はありえないし、やり直しも効かない。でも、「オルタナティブ・パスウェイ」(もう一つの道)を提示する力が、芝居にはあることを、いつまでも信じたい。