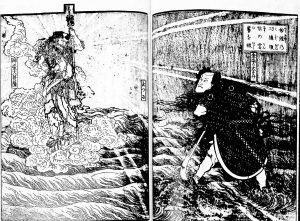◎ シェイクスピア・坪内逍遥訳「リア王」(07) 第五幕
——————————————————————————-
リヤ王:第五幕 第一場
——————————————————————————-
第五幕
第一場 ドーワ゛ーに近きブリテン軍の陣營。
鼓手、旗手をひきゐてエドマンド、リーガン、士官ら、兵士ら出る。
エドマ
(士官に)公爵の許へ往って、承知ってまゐれ、先般の御案通りであるか、 又は其後何等かの理由で方針を變へられたかどうかを。自分自身でしたことを非難して、 始終變へてばかりをられる。確定したところを承知って參れ。
命を受けて一士官入る。
リガン
姉上の家來は、何か(途中で)間違ひが生じたのに相違ない。
エドマ
さうかも知れません。
リガン
(うちとけて)エドマンドさん、 貴下はわたしが貴下に對して好意を有ってることはごぞんじでせう。 おっしゃいよ……眞實の事を……事實そのまゝでなくては不可ませんよ。…… 貴下はわたしの姉を愛していらっしゃるの?
エドマ
さ、姉上として、愛してゐます。
リガン
兄上でなくっては入られない處へお入りなすったことはなくって?
エドマ
とんでもない事をおっしゃる。
リガン
わたしは心配でなりません、貴下は殆ど夫婦と呼んでよいほどに、 姉と同心一體ぢゃァないかと思って。
エドマ
決してそんなことはありません。
リガン
わたしは決してそんな眞似を姉にさせてはおきません。貴下、姉とは親しんで下さいますな。
エドマ
大丈夫です。……(奧を見て)お姉上とおつれあひの公爵!
鼓手、旗手をひきゐてオルバニー、ゴナリル、及び兵士ら出る。
ゴナリ
(二人の樣子を目早く見て、傍白)妹めに、あの人との仲を邪魔されるくらゐなら、 今度の軍に負けたはうがよい。
オルバ
リーガンどの、めでたうお目にかゝりまする。……(エドマンドに)うけたまはれば、 王は我が苛政に憤激せる不平黨に擁せられて、其女コーディーリャ方へ赴かれたとの事だ。 正義と信ずるに至らんうちは、勇斷を致しかねるのが吾等の性質ですが、此度の事は、 フランス王が、王を助くるのを本意とはせずして、敢て我が國を侵掠しようと企てるのであるから、 棄て置かれません。王及び其黨與に至っては、正當な且つ重大な理由があって干戈を動かされたのであるから、 これに刄向かふことは……
エドマ
(冷笑して)いや、實に公明正大なお考へです。
リガン
そんな事ァ如何でもいゝぢゃありませんか?
ゴナリ
只協力して敵を防げばいゝのですよ。内部の、個人に關することは當面の問題ぢゃありません。
オルバ
では、老功の者を輯めて、會戰の手續きを定めませう。
エドマ
すぐさま御陣所へ參りませう。
リガン
姉上、いらっしゃいませんか?
ゴナリ
いゝえ。
リガン
いらっしゃったはうが都合がようございますから、どうぞ一しょにいらっしゃって。
ゴナリ
(傍白)おほう、其謎は解ってますよ。……參りますよ。
一同が入らうとする時、假裝したエドガーが出る。最もおくれて入らうとするオルバニーに對って
エドガ
かやうな賤しい者にもお目を賜はりまするならば、一言申し上げたいことがございます。
オルバニーは、立止まって、先きに立ってゐる人々に
オルバ
ぢき追ひ附きますよ。……
皆々入る。オルバニーとエドガーだけが殘る。
申せ。
エドガ
御開戰以前に、此書面を御覽下さい。若し御勝利でございましたら、 喇叭を以て此書を持參しました私をお呼び出し下されたい。 見るかげもない私でございますが、書中に誓ひおきましたる事程は、 見事に劍を以て證明して御覽に入れまする。萬一にも御敗軍となりますれば、此世に關する御能事は終り、 隨って陰謀も止みまする。御幸運に渡らせられまするやう!
オルバ
此書を讀み了るまで待ってをれ。
エドガ
それは相叶ひません。其時刻となりましたら、傳令使に命じてお呼び立て下されませ、 すれば再びお目にかゝりまする。
オルバ
では、きげんやう。書面は讀みおくであらう。
エドガー入る。
エドマンドが出る。
エドマ
敵は迫りましたぞ。備へをお立てなされ。勤勉な斥候の此報告で、敵軍の兵力其他確實な事が分ります。 (書面を渡す。)お急ぎを願ひます。
オルバ
勇んで出陣しませう。
とオルバニー入る。
エドマ
(皮肉な笑ひを浮べて)姉にも妹にも夫婦約束をしておいたので、互ひに危み疑ってゐる、 一度さゝれた者が蝮をあやぶむやうに。どッちを取ったものか?兩方ながらか? かた~か?どちらも止すか?兩方を生しておきゃ、どちらも此方の有にゃならん。 未亡人のはうを取りゃァ姉のゴナリルが憤激して狂人のやうになる。かと言って、 所天が生きてゐて見れば、此方の手もまづしと。まづ、ともかくも、 戰爭中はあの男の助けを利用することにして、戰ひが濟んだら、夫を邪魔物にしてゐるあの女に工夫させて、 手早く押方附けることにしよう。あの男は、リヤやコーディーリャに慈悲を施さうとしてゐるが、…… 戰爭が濟んで、あいつらが捕虜となった曉にゃァ……赦免なんぞさせるこッちゃない。 おれの今の境遇は礪行が肝腎だ、ぐづ~考へてゐべきぢゃァない。
エドマンド入る。
“読書ざんまいよせい、改め、人生は台詞、全てこの世は舞台(002)” の続きを読む