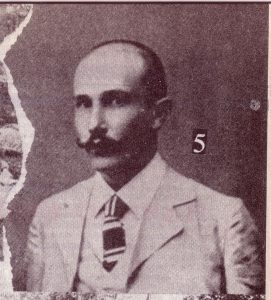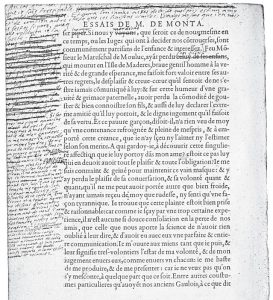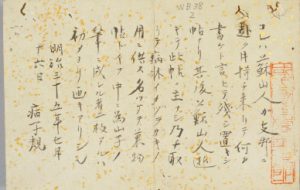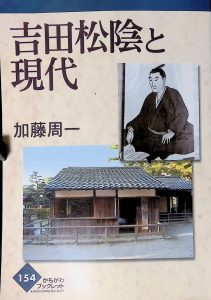◎蒼ざめたる馬(005)
ロープシン作、青野季吉訳
◎蒼ざめたる馬(004)
ロープシン作、青野季吉訳
四月六日
復活祭の前週間は過ぎた。今日、楽しいは鳴り響いてゐる。復活祭の日曜日だ。夜は、投び 満ちた行列、キリストの讃美の中に、過ぎた。街々は朝から澤山の人出がして、林檎一つ落ちる 余地もない。頭に白いハンカチーフを巻いた百姓女、兵隊、襤褸を着た食、制服の學生 彼等はみんな接吻したり、 向日葵の種を噛んだり、お僥舎《しやべ》りをしたり、笑ったり、無駄口をたさいたりしてゐる。赤い復活祭の卵や、しやうが<傍点>餅が路傍で賣られ、色のついた風船がリボンにつながれてゐる。群衆は、巣の中の密蜂のやうに、ブンブン鳴りざめいてゐる。
少年時代に私達は、四旬齋《レント》の六週間のあひだ聖晩餐の仕度をした。 丸一週間斷食をして、式の日にも、晩餐の儀禮のすむまでどんな食べ物に觸れなかつた。それから五週間目《パツシヨンウイク》が来た。 ……おゝ、私達の跪拝の狂熱、會堂に展けられた救世主の御慕への熱情的な密着! 「主よ、われらが罪を赦させ玉へ。」復活祭の朝々は、天國のやうな感じを與へた。蠟燭の輝き、蠟の匂ひ、僧侶の雪白な法服、金色の龕があつた。・・・・・興奮で息が詰りそうであつた。キリストはすぐ甦り玉ふか?
私達は清められた復活祭のバンの一片を持つてすぐ家に歸らうか?
家では、すべてがお祭りの仕度になつてゐた。復活祭の全週間はお祭り日であつた。
「お占ひなされ、旦那さま。」一人の小娘が私の手に封じ物を押し入れた。
小娘は裸足で襤褸を着てゐる。お祭りらしい様子は何にもない。 彼女から買った灰色の紙に、次のやうな豫言がある。
「悪運に追廻さるとも、希望を棄つる勿れ、失望に道をゆづる勿れ。汝は大いなる困難に打克ち、運命をして汝にその車輪を向けしむるならん。汝の企は、汝の思ひしよりも更に一層大いな る、全き成功を以つて飾らるゝならん。」
そうだ、私にとって、これは佳い復活祭の卵ではないか?
四月七日
ヴァニアは他の人達と一緒に、馭者立場に暮してゐる。彼は腰掛の上に彼等と喰付いて眠る。彼は共同釜で食つてゐる。 自分で馬の手入れをして、馬車の掃除をする。 彼は馬車を驅って、終日、街中で費す。彼はこぼ<傍点>さない。彼の仕事にすつかり満足してゐる。
今日、彼は新しい着物を着て居り、頭髪は鮮やかに油をぬられて、長靴は氣持よく鳴る。
彼は私に云つた。
「遂に復活祭が来た。それは善い・・・・・・キリストは甦った。眞實だよ、ジヨーヂ。」
「うむ、何が善いことだい?」
「あゝ、君は・・・・・・君は悦びを持つてゐない。君は、萬象を在りのまゝに受取らないんだ」
「君はそうか?」
「僕?そりあ全く別だ。しかし僕は君が気の毒だよ、ジヨーヂ。」
「気の毒だ?」
「そうだ・・・・・・君は誰をも愛さい。 君自身をさへ愛さないんだ。・・・・・・僕等の立場《たちば》に。一人の馭者がゐる、チツホンと云ふんだ。色の黒い髪の巻き下つた百姓なんだ。彼は悪魔のやうに意地惡だ。以前には大變な物持ちだつたんだが、大火ですつかり持つてたものを無くしたんだ。人が憎くんで彼の家へ放火したんだ。彼はそれが忘れられないで、誰でも、どんなものでも、呪つてゐる。彼は、神も、學生も、商人も、小供さへも、呪つてるんだ。 彼は彼等をすつかり嫌つてるんだ。『彼奴等は犬畜生だ。彼奴等は誰も彼も。』と彼は云ふんだ。『彼奴等はキリスト教徒の 血をすゝつてるんだ。そして神は、天から彼奴等を見下して、それを観て楽しんでゐるんだ。』・・・・・・或日、僕が茶店を出て立場へ歸つて来ると、チツホンが立場の真中に突立つてゐた。脚を廣く 開いて立ち上つて、袖を巻くし上げてゐた。大いに手綱を握つて、馬の眼を激しく打つてゐるんだ。生命《いのち》の氣《け》もない可哀想な馬は、拳固を外そうとして頭をふるのに、彼は續けかけ續けかけ眼を亂打するんだ。『骸骨奴!』 彼は皺枯れ聲で努鳴った。『獣奴!思ひ知らしてやるぞ』『チツホン 何故可哀相なものを打つんだ!』私は彼に問ふた。『默れボロ野郎!』彼はさう答へて、益々怒つて馬を打つんだ。。
ヴアニアは砂糖の小さい一塊りを嚙んで、茶を綴って、續けた。
「怒るなよ、ジヨーヂ、笑ふな。僕の考へてることを知ってるかね?僕等は、僕等はみんな、貧しい心なんだ。僕が生活を驅つて行く力は何だ?憎惡だ、たゞ憎惡だけだ。僕等は愛さない、愛すと云ふことはどんなことか、僕等は知らない。僕等は戰ふ。僕等は殺す。 僕等は焼く。そして僕等もまた絞め殺され、縊られ、焼かれるのだ。何者の名に於いて、それが爲されるのか?聞かせてくれい。。
私は肩をゆすつた。
「ハインリヒに聞け、ヴアニア。」
「あゝ、ハインリヒ!彼は人々を自由にして、彼等のすべてに食物を與へることを信じてゐる。 しかしそれはマルタの役目なんだ。マリアお役目は何だ?人が自由の爲めに死なんとする。いや 自由の爲めばかりぢやない、一滴の涙の爲めにも死なんとする、それは僕は十分了解する。僕も、地に奴隷なく、飢ゆる者の無いことを、神に禱る。しかしそれで事がすむんぢやないよ、ジヨーヂ。現在、人々の生活が非眞理の上に建てられてあることを、僕等は知ってる。眞理はいつたい何處に在るのか?話せるなら話して呉れ。」
「眞理とは何か?君の言ふのはさうか?」
「そうだ、真理とは何か?ねえ君 『我の生れ、我の此世に来れるは、眞理の證《あかし》を爲さんが爲めなり。眞理に在る凡ての者は、我聲を聞く』さ。」
「ヴァニア、キリストは、汝殺すこと勿れ、と云つたよ。」
「知ってる。しかし血のことはまだ云ふな。何か他のことを話して呉れ。歐羅巴は世界に二つの言葉を與へて、それを苦痛で封じ込んだ。第一が自由だ、第二が社會主義だ。しかし僕等は世界にどういふ言葉を與へたか?自由の名において、多くの血が流された。が、誰が自由を信ずるか?が、君は實際、社會主義が地上の天國だと信ずるか?愛の名において、愛の爲めに、誰が火刑柱に上つたか?人々が自由になり、子供が食に飢えず、母が泣き悲しまないだけでは充分ではないと、僕等のうちの誰かこれまで敢《あ》えて言つたか?それよりもつと以上に、彼等がお互に相愛する必要が、大いなる必要があるんだ。神は彼等共に在り、彼等の心の中に在らねばならんのだ。それだのに、その神と愛を、彼等は忘れてゐる。しかしマルタは眞理の分でしかない。あとの半分はマリアだ。僕等のマリアは何處に居るか?一つの大きな道の爲めに、今や戰はれてゐる、僕は强くそれに信頼する。それは百姓の道だ。凡てのキリスト教徒の道だ、實にそれは、キリストの道なんだ。それは神の爲めに、愛の爲めに、戦はれてゐるんだ。人々は釋放たれ、食を與えられ、愛の生命は彼等のものとなるだろう。僕もまた、吾々は神の民だといふことを、信ずる。愛が吹き込まれ、キリストがその中につてゐるのだ。僕等の言葉は、復活の言葉だ、主よ、甦れ!……僕等の信仰は小さい、僕は小供のやうに弱い。それだから僕等は劍を執《と》るんだ。僕等が劍を振廻すのは、力がある爲ぢやない。僕等の弱さと僕等の恐怖とからなんだ。しかしながら明日来る者を待て。彼は純なる者だ。彼等は劍を要しない。彼等は强い。が、彼等の來る前に、僕等は死ぬだらう。そして僕等の小供のその孫が神を愛するであらう。彼等は神のうちに生き、キリストを讃美するであらう。新しい世界が彼等に啓らけ、彼等はその中に、僕等が現在見ることの出来ないものを、見出すてあらう。……そして、おゝ、ヂヨーヂ!今日は復活祭の日曜日だ。キリストは甦つた!せめて今日一日だけで僕等の傷《きず》を忘れやう。そしてお互に眼を打合ふことを止《よ》そう……」
彼は、新しい考が突然思ひ浮んだやうに、寧ろ不意に止《や》めた。
「どうしたんだ、ヴァニア?何か云はうとしてるたんぢやないか?」
「君に云ふがねぇ。鎖を斷ち切ることは不可能だ。僕には他の途はないんで、全く何にも。僕は殺しに行く、しかし僕は福音を信する、キリストを讃へる。おゝ、苦痛だ!」
居酒屋は、お祭りを祝つた酒醉ひの喧騒で滿たされてゐた。ヴアニアは卓子掛の上に頭を低く垂れかけて待つてゐた。私は何をすることが出来たか・・・手綱《たづな》で彼の眼を打つことか?
・写真は、「集合写真の断片。ボログダでの若きサヴィンコフ(Wikipedia より)
・著者・訳者とも著作権は消失している。