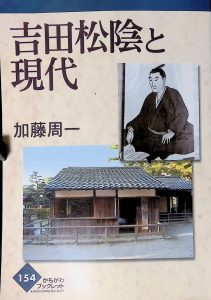◎加藤周一と吉田松陰
久しぶりに、加藤周一の吉田松陰を扱った小冊子を手にしてみたが、いささかの違和感を感じた。思いの外、松陰に肩入れしているからだ。特に、彼の抱いていた政策が極めて現実的であったことを評価するのは、興味のあるところだ。ただ、加藤周一が語らぬところだが、「松下村塾」を通じて「弟子」たちに伝えていったことが、その後の日本の行く末を決定したことも間違いないが、果たしてそれが良かったのだろうか?
そこで、少し、加藤周一の「日本文学史序説」も、松蔭の漢詩に触れた部分を繙いてみた。
松陰の詩は、その大部分を、『松陰詩稿』に収める(『全集』、岩波書店、ー九三九の第七巻)。そこには頻に「墨土火船」とか「四夷」とか「国恥」とかいう語がみえ、また頻に「忠義」とか「勤王」とか「報国」とかいう憂国の語があらわれる。身辺雑事の観察はなく、四季の吟詠もなく、恋の歌もない。措辞の洗練も、詩的「イメージ」の独創もなくて、彼の詩はほとんど日記のように、機会に応じてその政治的理想を述べる。彼が詩人であったのは、そういう詩を書いたからではなく、その生涯の思想と行動とが一種の詩に他ならなかったからである。
狂愚誠可(㆑)愛
才良誠可(㆑)虞《おそる》
狂常鋭(二)進取(一)
愚常疎《うとし》(二)避趨(一)
才多(二)機変士(一)
良多(二)郷原徒(一)
流俗多(二)顛倒(一)
目(レ)人古今殊《ことなり》
オ良非(二)才良(一)
狂愚豈狂愚
(「狂愚、『松陰詩稿』)
(書き下し文)
狂愚誠に愛すべし 才良誠に虞るべし
狂は常に進取に鋭く 愚は常に避趨に疎し
才は機変の士多く 良は郷原の徒多し
流俗顚倒多く 人を目すること古今殊なり
才良も才良に非ず 狂愚豈に狂愚ならんや
引き続き、加藤の詩の「解説」は長い引用になるが…
「進取に鋭く」は、『論語』、子路篇、第二ー章の「狂者進取」に拠る。「郷原の徒」は、同じく、陽貨篇、第二ニ章の「郷原徳之賊也」を踏まえて、 いわゆる「八方美人」である。「機変の士」すなわち機会主義者(または現実追随主義者)に対し、また「八方美人」に対して、あくまで前進し、困難を避けない「狂愚」を、彼は愛するといったのである。そういう心情は、力関係の冷静な判断や費用と効果の計算や戦略的な妥協というもの、つまり政治的な思考と、背馳するにちがいない。彼には詩人の気質があって、政治家の天性がなかった。しかるに時代は、詩人を政治的状況のなかにまきこんだのである。吉田松陰という現象は、まさに詩人の政治化であった。そのことから現実主義に媒介されない政治的理想主義が生じる。現に彼の理想主義から影響を受けた青年は多く、非現実的な行動計画に賛成した同志は少なかった。かくして孤立は強まらざるをえず、獄中に孤立した松陰の行動計画の撰択の範囲は、いよいよ狭くなるはずであった。それでも積極的に動こうとすれば(「進取」)、もはや「テロリズム」以外に手段がなくなるだろう。妥協のない理想主義から孤立へ、孤立から手段の過激化へ、したがってより以上の孤立へ!という悲劇的な道は、ついに効果の点で絶望的な行動に終らざるをえない。その最後の行動は、もはや政治的な面においてではなく、詩的な、あるいは精神的な面においてのみ、象徴的な意味をもち得る。それが藩主の待ち伏せ計画、いわゆる「要駕策」であった。「要駕策」が失敗し、捕えられた門人に送つた彼の書簡には、「天下一人の吾れを信ずるものなきも、吾れに於ては毫も心を動かすに足るものなし」という(「和作に与ふ」、『己未文稿』、ー八五九)。詩人はどれほど政治家しても、詩人に還るのである。
加藤特有の「論旨」の建て方には感服する面もあるが、後の世代にも引き継がれ、日本の行く末を危うくした松蔭の「ニヒリズム」が果たして詩人の「資質」なのだろうか?ここは、高杉晋作の「三千世界の烏を殺し、主と朝寝がしてみたい」という都々逸に現れるやや退嬰的な雰囲気のほうが、「詩情」に富む気がしてならない。(高杉晋作については、日本人と漢詩(030)でも触れた。)
参考】
・加藤周一「吉田松陰と現代」(かもがわブックレット)
・加藤周一「「日本文学史序説・下」(ちくま学芸文庫)