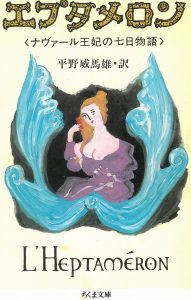◎ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」
◎アンドレ・ジッド 渡辺一夫訳「モンテーニュ論」(岩波文庫)
◎堀田善衛「ミシェル 城館の人 第一部 争乱の時代」
少し、おさらいすると、モンテーニュは、1533年、ボルドー近郊のモンテーニュ城に生まれた。フマニスト・エラスムスが亡くなったのが、1536年だから、その生涯を引き継ぐ形になっている。ルターの『95ヶ条の論題』でのカトリックへの糾弾の始まった1517年の16年後のことである。幼少期から少年期にかけての、父親の「ラテン語しごき」をへて、へ入学する。
「真に 我が子の自由な教育を願望する父兄は、学院、 特に宗教家の経営する学院などに入れるべきではない。(エラスムス)」
かどうかは分からないが、当時の学校はともすれば、
「(教師)がこういう人たち(生徒) が、自分こそ人間中の第一流の人物だと思っていられるような幻を授けてやっているのですよ。」(同じくエラスムス)
と、当時の教育の悪循環も非難する。
モンテーニュの父親も、その特訓から後、息子の教育についていろいろ迷ったことだろう。プロテスタントに傾いていたマルグリート・ド・ナヴァール公妃とも関係が深い、ボルドーのギュイエンヌ学院に入学させた。そこでは、「詰め込み」もあったが、学風は概してリベラルなものであり、ミシェル少年の勉学もローマ古典文学を手がかりに、カトリック的スコラ神学主義とは違う、異教徒的なものであったと堀田善衛は指摘する。ある意味、昨今の時の政権による Académie japonaise への政治的介入よりも自由だったかもしれない。13才で学院を卒業する頃には、(ちょうどボルドーで暴動騒ぎがあったが)
もっとも 軽蔑してはならない階級は、…最下層に立たされている人々のそれであると思う。… 私 は いつも 百姓 たちの行状や言葉が、われわれの哲学者たちのそれよりも、真の哲学の 教えにかなっていると思う。〔 庶民の方がかえって賢明である。必要な程度に知っているからである。〕
という、まっとうな見解は持ち得たのである。
フランスの文学者・小説家にアンドレ・ジードがいる。彼はモンテーニュについていくつか、小評論を書いている。戦前に渡辺一夫訳で出たものだ。そのせいだけではないが、少し難解で意味がなかなかとりにくいきらいもある。その評論で「エセー」を引きながら、晩年、モンテーニュは、「もし余が再びこの人生を繰り返さねばならぬとしたら、余のして来た通りの生活を再びしたいものである。余は過去を悔まず、未来を恐れもしないから」と書いているという。モンテーニュのこうした非宗教的態度は、死ぬまで持っていたようだ。
いずれにしても、アンリ四世との本格的な邂逅があるのは、もう少し後の話である。