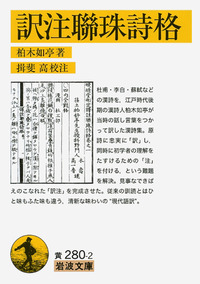◎梁川紅蘭と梁川星巌
先日、昨今のコロナ感染症(COVID19-9)後遺症の診療を精力的に取り組んでおられる医師の講演を拝聴した。現在わかっていること、解決の課題となっていることが、なかなかに整理されていた講演であった。後遺症(SNS などでは、long corona と呼ばれている。)の一部には、昔から「血の道を良くする」とされる漢方薬の当帰芍薬散が、効果があるらしい。(もちろん、個人差や症状の微妙な相違があるので、服用にあたっては、必ずかかりつけ医と相談することが必須である。)
当方も成分は少し違うが、山歩きなど「こむら返り」を起こした時に「芍薬甘草湯」を即効性の有る漢方薬として、重宝している。
ところで、梁川紅蘭にこんな漢詩がある。
階前栽芍藥 階前《かいぜん》に芍薬《しゃくやく》を栽《う》え
堂後蒔當歸 堂後《どうご》に当帰《とうき》を蒔《ま》く
一花環一草 一花環《ま》た一草
情緖兩依依 情緒《じょうちょ》両《ふた》つながら依依《いい》たり
語釈など]当帰:「当《まさ》に帰るべし」と夫の帰りを待ちわびる 花草に心を寄せる(どうして別れることがありましょうや)
また従兄弟で夫である梁川星巌が、旅に出て、留守宅で、薬草を育てていた時の作である。新婚当時で、夫が不在がちなので、親類からは「別かれては…」と勧められていたそうだ。当時は、こうして自家栽培で、それを収穫、煎じて、薬にしていたことが分かり、興味深い。
当時、紅蘭は美濃「梨花村草舎」(現在の大垣市)におり、夫から「三体詩」の暗誦を命ぜられていたが、みごとに全編を諳んじることで、帰宅した星巌を驚かせたという。無聊を慰めるため、江馬細香らの詩の集いに参加し、大いに腕を磨いたとある。孤閨にこりた紅蘭は、文政五年(1822年)、連れ立って西遊の長征の旅に出る。ときに、紅蘭十九歳。帰宅したのは、文政九年(1826年)、あしかけ4年の長丁場の旅路だった。途中の旅先で、その路銀の寡なさを記にしながらも、その頃詩名の高かった、頼家の人々や、菅茶山などと交友を深め、それが目的の一つだったのだろう、歓待、逗留の光栄に浴した。旅も三年目になると、望郷の念、耐えがたく、一首を残している。
紅事蘭珊綠事新 紅事は蘭珊《らんこ》として緑事新《あらた》なり
每因時節淚沾巾 時節に因《よ》るごとに涙は巾《きれ》を沾《うるお》す
遙知櫻筍登厨處 遥に知る桜筍《おうじゅん》厨《くりや》に登る処
姉妹團欒少一人 姉妹団欒《だんらん》一人を少《か》くらん
訳文など]桜、桃、杏の季節も過ぎ、すっかり新緑のときとなった。こうしためぐりの中で、涙がハンカチに溢れる。家では、さくらんぼや筍をが台所に並んでいるのに、姉妹は、仲良く歓談しているのに、私一人だけ不在なのだ。
彼女は、詩作にあたっては、三体詩をそらんじていたというから、王維の「九日山東の兄弟を懐ふ」を念頭に置き、詩のモチーフとして用いたと思われる。(日本人と漢詩(080)を参照)
一方、夫の星巌は、食道楽もあり、広島で牡蠣を食し、詩では、楊貴妃のおっぱいに見立てて表現している。ここらあたりは、遺稿を託された柏木如亭のひそみに習ったのかもしれないが、紹介は別の機会に…
天保五年(1834年)星巌は、江戸で「玉池吟社」を起こし、以来弘化二年(1845年)それを閉じるまでは江戸在住、以前紹介した大沼枕山などと広く交流したのだろう。天保という年号の時代、世の中は、天保の大飢饉、大塩平八郎の乱、蛮社の獄など大きく変動した、その最中である。
星巌は、良く言えば、用字など先鋭的な表現に工夫し、悪く言えば「僻字《へきじ》」(異常に奇異な文字)を用いるなど、奇をてらうところがあろう。こうした事は、現実世界への態度にも反映し、政治的には、ときに過激な行動を取らしめたのではないか?想像に過ぎないが、彼の主管した「玉池吟社」などは、「勤王志士」の情報交換の場だったかもしれない。対する、 旅先の彦根で知り合った(かもしれない)井伊直弼の懐刀・長野主膳には目の敵にされていたようだ。ところが、星巌は、明治維新を見ることなく、安政の大獄直前にその頃流行っていたコレラで急死する。紅蘭もそのとばっちりを受けて、半年間の牢獄の実となった、明治十二年(1879年)にこの世を去ったが、なかなか芯の強い女性であった。
最後に、梁川星巌が、大塩平八郎の乱の勃発を聞き及んだ時の詩
誰か仁義を名とし戈矛《かぼう》を弄《ろう》せん
清平《せいへい》に軍《いくさ》あることこれ天警《てんけい》
合党《ごうとう》多しといえども国讐《こくしゅう》にあらず
君子は情を原《たず》ね功罪《こうざい》を定めよ
訳文など]
仁義を名分として乱を起こすやつがいるか。やむにやまれぬ気持ちというのがあるのだ。天下泰平に内乱というのは天の戒めというやつだ。合力は多いが、国の仇にはなるまい。その事情と気持を察した上で、功績と処罰を決めるべきだ。
ここでは、白文を略する。「小説 渡辺崋山」には、七律とあるが、一、二句が対になっていないので、七言絶句の誤りだろう。星巌せんせー、至極当然の事をのべるなどなかなかやるじゃん。
写真は、当帰と芍薬の花(Wikipedia から)と二人の旅程図
参考図書】
・大原富枝「梁川星巌・紅蘭 放浪の鴛鴦」(淡交社)
・杉浦明平「小説 渡辺崋山」(上)