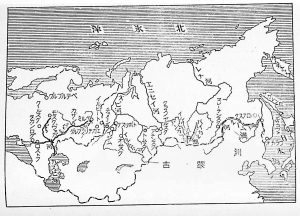◎噫無情(001)
ヸクトル、ユーゴー 著
黒岩涙香 譯
噫無情 : 目次
タイトル:噫無情 (Les Misérables, 1862)
著者:ヸクトル、マリー、ユーゴー (Victor Hugo, 1802-1885)
譯者:黒岩涙香 (1862-1920)
底本:縮刷涙香集第二編縮刷『噫無情』
出版:扶桑堂
履歴:大正四年九月十五日印刷,大正四年九月十八日發行,大正七年七月十七日廿二版(實價金壱圓六拾錢)
目次
* 小引
* 一 一人の旅人《りよじん》
* 二 其家を窺《のぞ》き初めた
* 三 高僧と前科者
* 四 銀の皿、銀の燭臺
* 五 神の心と云ふ者だ
* 六 寢臺《ねだい》の上に起直り
* 七 社會の罪
* 八 恍として見惚《みと》れた
* 九 恐る可き分岐點
* 十 愚と云はふか、不幸と云はふか
* 十一 甚《ひど》いなア、甚《ひど》いなア
* 十二 華子
* 十三 小雪
* 十四 斑井《まだらゐ》の父老《ふらう》
* 十五 蛇兵太《じやびやうた》
* 十六 星部《ほしべ》父老《ふらう》
* 十七 死でも此御恩は
* 十八 夫がなくて兒供が
* 十九 責道具
* 二十 畜生道に落ちた
* 二十一 警察署
* 二十二 市長と華子
* 二十三 運命の網
* 二十四 本統の戎瓦戎《ぢやん、ばるぢやん》が
* 二十五 不思議な次第
* 二十六 難場の中の難場
* 二十七 永久の火
* 二十八 天國の惡魔、地獄の天人
* 二十九 運命の手
* 三十 聞けば兒守歌である
* 三十一 重懲役終身に
* 三十二 合議室
* 三十三 傍聽席 一
* 三十四 傍聽席 二
* 三十五 傍聽席 三
* 三十六 傍聽席 四
* 三十七 傍聽席 五
* 三十八 市長の就縛 一
* 三十九 市長の就縛 二
* 四十 市長の就縛 三
* 四十一 入獄と逃亡 一
* 四十二 入獄と逃亡 二
* 四十三 むかし話
* 四十四 再度の捕縛、再度の入獄
* 四十五 獄中の苦役
* 四十六 老囚人の最後
* 四十七 X節《クリスマス》の夜 一
* 四十八 X節《クリスマス》の夜 二
* 四十九 X節《クリスマス》の夜 三
* 五十 X節《クリスマス》の夜 四
* 五十一 X節《クリスマス》の夜 五
* 五十二 X節《クリスマス》の夜 六
* 五十三 X節《クリスマス》の夜 七
* 五十四 客と亭主 一
* 五十五 客と亭主 二
* 五十六 客と亭主 三
* 五十七 抑《そ》も此老人は何者
* 五十八 隱れ家 一
* 五十九 隱れ家 二
* 六十 隱れ家 三
* 六十一 隱れ家 四
* 六十二 落人《おちうど》 一
* 六十三 落人《おちうど》 二
* 六十四 何物の屋敷 一
* 六十五 何物の屋敷 二
* 六十六 尼寺 一
* 六十七 尼院 二
* 六十八 尼院 三
* 六十九 尼院 四
* 七十 本田圓《ほんだまるし》
* 七十一 父と子
* 七十二 本田守安 一
* 七十三 本田守安 二
* 七十四 ABC《アーベーセー》の友
* 七十五 第一、第二の仕事
* 七十六 異樣な先客
* 七十七 青年の富
* 七十八 公園の邂逅《めぐりあひ》
* 七十九 白翁《はくおう》と黒姫《くろひめ》
* 八十 白翁と黒姫 二
* 八十一 白翁と黒姫 三
* 八十二 白翁と黒姫 四
* 八十三 神聖な役目
* 八十四 四國兼帶の人 一
* 八十五 四國兼帶の人 二
* 八十六 四國兼帶の人 三
* 八十七 四國兼帶の人 四
* 八十八 四國兼帶の人 五
* 八十九 四國兼帶の人 六
* 九十 四國兼帶の人 七
* 九十一 四國兼帶の人 八
* 九十二 四國兼帶の人 九
* 九十三 陷穽《おとしあな》 一
* 九十四 陷穽《おとしあな》 二
* 九十五 陷穽《おとしあな》 三
* 九十六 陷穽《おとしあな》 四
* 九十七 陷穽《おとしあな》 五
* 九十八 陷穽《おとしあな》 六
* 九十九 陷穽《おとしあな》 七
* 百 陷穽《おとしあな》 八
* 百一 陷穽《おとしあな》 九
* 百二 町の子
* 百三 十七八の娘
* 百四 私しと一緒
* 百五 愛 一
* 百六 愛 二
* 百七 愛 三
* 百八 庭の人影 一
* 百九 庭の人影 二
* 百十 庭の人影 三
* 百十一 愛の天國
* 百十二 無慘
* 百十三 千八百三十二年
* 百十四 容子ありげ
* 百十五 疣子と手鳴田
* 百十六 家は空《から》である
* 百十七 死場所が出來た
* 百十八 一揆軍 一
* 百十九 一揆軍 二
* 百二十 軍中雜記 一
* 百二十 軍中雜記 一
* 百二十 軍中雜記 一
* 百二十一 軍中雜記 二
* 百二十一 軍中雜記 二
* 百二十一 軍中雜記 二
* 百二十一 軍中雜記 二
* 百二十一 軍中雜記 二
* 百二十二 軍中雜記 三
* 百二十二 軍中雜記 三
* 百二十二 軍中雜記 三
* 百二十二 軍中雜記 三
* 百二十二 軍中雜記 三
* 百二十三 軍中雜記 四
* 百二十四 軍中雜記 五
* 百二十五 軍中雜記 六
* 百二十六 軍中雜記 七
* 百二十七 軍中雜記 八
* 百二十七 軍中雜記 八
* 百二十八 軍中雜記 九
* 百二十八 軍中雜記 九
* 百二十八 軍中雜記 九
* 百二十八 軍中雜記 九
* 百二十八 軍中雜記 九
* 百二十九 蛇兵太の最後
* 百三十 守安の最後
* 百三十一 エンジラの最後
* 百三十二 堡壘の最後
* 百三十三 哀れ戎瓦戎 一
* 百三十四 哀れ戎瓦戎 二
* 百三十五 哀れ戎瓦戎 三
* 百三十六 哀れ戎瓦戎 四
* 百三十七 哀れ戎瓦戎 五
* 百三十八 哀れ戎瓦戎 六
* 百三十九 哀れ戎瓦戎 七
* 百四十 哀れ戎瓦戎 八
* 百四十一 哀れ戎瓦戎 九
* 百四十二 哀れ戎瓦戎 十
* 百四十三 哀れ戎瓦戎 十一
* 百四十四 哀れ戎瓦戎 十二
* 百四十五 哀れ戎瓦戎 十三
* 百四十六 哀れ戎瓦戎 十四
* 百四十七 哀れ戎瓦戎 十五
* 百四十八 最後 一
* 百四十九 最後 二
* 百五十 最後 三
* 百五十一 最後 四
* 百五十二 大團圓
噫無情 : 小引
■「噫無情」と題し茲に譯出する小説は、ヸクトル、マリー、ユーゴー先生の傑作『レ、ミゼラブル』なり
■著者ユーゴー先生は多くの人の知れる如く、佛國の多恨多涙の文學者にして又慷慨なる政治家なり、詩、小説、戯曲、論文等に世界的の傑作多し、先生千八百二年に生れ八十四歳の壽を以て千八百八十五年(明治十八年)に死せり
■『レ、ミゼラブル』は先生が國王ル井、ナポレオンの千八百五十年の非常政策の爲に國外に放逐せられ白耳義に流竄せる時に成りしと云へば、即ち五十歳以上の時の作なり、最も成熟せし著作と云ふ可し(先生が初めて文學者として世に著はれしは其十四歳の時に在り)
■「ミゼラブル」ちは、英國にては視るに忍びざる不幸の状態を指すの語なり、佛語にては多く『身の置所も無き人』と云ふ意味に用ゐらる、即ち社會より窘害せられて喪家の犬の如くなる状態に恰當する者の如し、我國の文學者が一般に『哀史』と云ふは孰れの意に取りたるやを知らずと雖も先生が之を作りたる頃の境遇より察すれば前の意よりも後の意に用ひたる者なるが如くに察せらる
■余先頃、ヂュマのモント、クリストーを巌窟王と題せしに或人は巌窟王の音が原音に似たりとて甚だ嘆稱せられたり、余は爾まで深く考へたるに非ざりしを、勿怪の幸ひと云ふ可し、今『レ、ミゼラブル』を『噫無情』と題し、又音の似通ひたりと云ふ人あり、然れども之も爾うまで考へしには非ず、唯だ社會の無上より、一個人が如何に苦めらるゝやを知らしめんとするが原著者の意なりと信じたれば、他に適切なる文字の得難さに斯くは命名したるなり
■原書はユーゴー先生の生存中に幾版をも重ねたれば先生親から幾度も訂せし者と見ゆ、英譯にも數種あり、余の有せる分のみにても四種に及ぶ、猶ほ耳に聞きて未だ手にせざる分も無きに非ず、是等を比較するに、或者は高僧ミリールの傳を初に置き、或る者はヂャン、ヷルヂャンを初めに置きたるが如き最も著るしき相違なり、思ふにミリールは先生が理想とせし人なる可ければ卷首に之を掲ぐるが當然なる可きも、晩年に及び讀者に與ふる感覺の如何に從ひて次章に移したるならんか、余は(新聞紙に掲ぐるには)後者の順序が面白かるべきを信じ、其れに從ふ事としたり
■譯述の體裁は余が今まで譯したる諸書と同く、余が原書を讀て余の自ら感じ得たるが儘を、余の意に從ひて述べ行く者なれば、飜譯と云はんよりも人に聞きたる話をば我が知れる話として人に話すが如き者なり、若し此を讀みて原書に引合せ、以て原書を解讀する力を得んと欲する人あらば失望す可し、斯かる人に對しては、余は切に社友山縣五十雄君の英文研究録を推薦す(内外出版會社の出版にて一册定價二十錢、英米の有名なる作者の詩歌及び短詩を親切に飜譯し註釋したる者なり)
■若し原書を句毎に譯述すれば五百回にも達す可し、少くとも三百回より以下なる能はず、然れども余は成る可く一般の讀者が初めの部分を記憶に存し得る程度を限りとし百五十回乃至二百回以内に譯し終らんことを期す
■ユゴー先生が此書に如何の意を寓したるやは余不肖にして能く知らざるなり、之を學[※;1文字不明。兄?]諸氏に質すに、社會組織の不完全にして一個人が心ならざる境遇に擠陷さるゝを慨したるなりと云ふ人多し、多分は然るなる可し、先生の自ら附記したる小序左の如し
△法律と習慣とを名として、社會の呵責が此文明の眞中に人工の地獄を作り、人の天賦の宿命をば人爲の不運を以て妨ぐることの有る限りは
△現世の三大問題、即ち勞働世界の組織不完全なるに因する男子の墮落、饑渇に因する女子の滅倫、養育の不足の爲の兒童の衰殘、を救ふの方法未だ解釋せられざる限りは
△心の饑渇の爲に衰死する者社會の或部分に存する限りは
△以上を約言して廣き見解に從ひ、世界が貧苦と無學とを作り出す限りは
則ち此種の書は必要無きこと能ばざる也
蓋しル井、ナポレオンが非常政策を發する前、佛國には社會主義の勃興あり、暗に政府及び朝廷を驚かしめたり、先生は是れより先き、文勲を以て貴族に列せられたるも深かく社會黨の運動に同情を寄せ、王黨を脱して共和黨に入り大に畫策する所ありたれば、社會下層の無智と貧困とを制度習慣の罪と爲し、其の如何に凄慘なるやを示さんと欲したる者ならんか、先生が流竄の禍を買ひたるも畢竟は斯る政治上の意見の爲なり、若し我が日本に『レ、ミゼラブル』の一書を飜譯する必要ありとせば、必ずや人力を以て社會に地獄を作り、男子は勞働の爲に健康を損し、女子は饑渇の爲に徳操を失し、到る處に無智と貧苦との災害を存する今の時にこそ在るなれ、唯だ余がユーゴー其人に非ざるを悲しむ可しとす
譯 者 識
噫無情 : 一 一人の旅人《りよじん》
縮刷 噫無情《ジーミゼラブル》(前篇)
佛國 ユーゴー先生 著
日本 黒岩涙香 譯
彿国《ふらんす》の東南端プロボンと云ふ一州にダイン(Digne)と稱する小都會がある
別に名高い土地では無いが、千八百十五年三月一日、彼の怪雄 拿翁《なぽれおん》がエルバの孤島を脱出《ぬけだ》してカン(Canes)の港に上陸し、巴里《ぱりー》の都を指して上つたとき、二日目に一泊した所である、彼れが檄文を印刷したのも茲《こゝ》、彼れの忠臣ベルトラン將軍が彼より先に幾度《いくたび》か忍び來て國情を偵察したのも茲《こゝ》である
此外に此小都會の多少人に知られて居るのは徳望限り無き高僧 彌里耳《みりいる》先生が過る十年來土地の教會を管して居る一事である
* * * * *
今は其れより七ヶ月の後、同じ年の十月の初《はじめ》、或日の夕方、重い足を引摺つて漸く此地に歩み着た一人の旅人は、日に焦た黒い顏を、古びた破帽子に半ば隱し、確には分らぬが年頃四十六七と察せらる、靴も着物も其 筒袴《づぼん》もボロ/\に破れて居るは云ふに及ばず、埃《ほこ》りに塗《まみ》れた其の風體の怪さに、見る人は憐れみよりも恐れを催し、路を避ける程で有つたが、彼れは全く疲れ果て居ると見え、町の入口で、汗を拭き/\井戸の水を汲上げて呑み、又一二丁行きて町中の井戸で水を呑んだ、抑《そもそ》も彼れは何所《どこ》から來た、何所へ行く、何者である、來たのは多分、七ヶ月前に拿翁《なぽれおん》の來た南海の道からで有らう、行くのは市廳《しちやう》の方である、頓《やが》て彼れは市廳に着た、爾《さう》して最《も》う役人の退《ひ》けて了ッた其の中に歩み入つたが、當直の人にでも逢たのか凡《およ》そ半時間ほどにして又出て來た、是れで分ッた、彼れは何所かの牢で苦役を務め、出獄して他の土地へ行く刑餘の人である、途々神妙に役所へ立寄り、黄色い鑑札に認《みとめ》を印《しるし》て貰はねば再び牢屋へ引戻さるゝのだ、法律の上から『油斷のならぬ人間』と認められて居る奴である
市廳を出てから、彼れは又町を徘徊《さまよ》ふた時々人の家を窺《のぞ》き込む樣にするは、最早や空腹に堪へ兼ねて、食と宿りとを求め度いのであらう、其うちに土地で名高いコルバスと云ふ旅店の前に行た、入口から直《すぐ》に見通した料理場に、燃揚るほど炭の火が起ッて、其上に掛けた平鍋には兎の丸焼や雉の揚出が轉がッて脂のたぎる音が旨さうに聞え、得ならぬ匂が腸《はらわた》まで染透るほどに薫ッて居る、勿論彼れは此前を通り切れぬ、油揚に釣れる狐の状《さま》で踉々《よろ/\》と中に入ッた、
中には主人《あるじ》自ら忙しく料理の庖丁を操《とつ》て居たが、客の來た物音と知り、顏も揚げずに『好く入ッしやい、御用向はと』[誤:御用向は』と]問ふた、疲れた空腹の、埃《ほこり》だらけの旅人は答へた『夕餉と寢床《ねどこ》とを』主人『其れはお易い御用です』と云ひつゝ初めて顏を上げ、客の風體を見て案外に感じたが、忽ち澁々の聲と變ッて『エー、お拂ひさへ戴けば』と云足した、客は財布を出し掛けて、[『]金は持つて居るよ』主人『其れなら宜しい』と無愛想よりも稍《や》や當惑けである
客はがッかりと安心した體《てい》で、背《せな》に負つて居た行李《かうり》と懷中《ふところ》の財布と手に持た杖とを傍《かたへ》に置いた、其間に主人《あるじ》は帳場に在つた新聞紙の白い欄外を裂取て、鉛筆で走り書に何か書認《かきしたゝ》め、目配《めくばせ》を以て傍《そば》に居た小僧を呼び、二言三言其の耳に囁て今の紙切を手渡すと、小僧は心得た風で戸外《おもて》の方《かた》へ走り去た
十月の初《はじめ》だから夜に入ると聊《いさゝ》か寒い、殊に茲《こゝ》はアルプス山の西の裳野《すその》に當り、四時絶間無き頂邊《てうへん》の雪から冷切た風が吹下すので、外の土地とは違ふ、先刻まで汗を絞て居た旅人も早や火の氣が戀しく成たと見え、火鉢の方に手を延べて、少しも主人《あるじ》の仕た事に氣が附かず、唯だ空腹に攻られて『何うか食ふ物だけは急いで貰ひ度い』主人『少々お待ち下さい、唯今』と云ふ所へ小僧は又急いで歸り、返辭と見える紙切を主人に渡した、主人は之を讀んで眉を顰《ひそ》め、暫し思案に餘る體《てい》で、其紙切と客の横姿《よこすがた》とを彼是れ見較べる樣にして居たが、爾《さう》とも知らぬ客の方は、空腹の上に猶《ま》だ氣に掛る事でも有るのか、少しも心の引立たぬ景状《ありさま》で、首《かうべ》を垂れて考へ込んで居る、遂に主人は決心が着たと見え、突々《つか/\》と客の傍《そば》に寄り『何《ど》うも貴方《あなた》をお泊め申す譯に行きません』全く打て變たと云ふ者だ、客は半分顏を揚げ『エ、何だと、騙《かた》られるとでも思ふのか、では先拂に仕やう、金は持て居ると斷ッたのに』主人『イヽエ、室《へや》の空た所が有りませんゆゑ』客は未だ失望せぬ、最《い》と靜《しづか》に『室《へや》が無ければ馬屋で好い』主人『馬屋は馬が一ぱいです』客『では何の樣な隅ッこでも構はぬ、藁さへ有れば敷て寢るから、先《ま》ア兎も角も食事を濟ませてからの相談にしやう』主人『食事もお生憎樣です』客は初めて驚ろいた『其樣な事は無い、私しは日の出ぬ前から歩き通して、腹が空て死にさうだ、十二里も歩いて來たのだ、代は拂ふから食はせて貰はねば』主人『喰る物が無いのです』客は聲を立てゝ笑ッた、全く當の外れた笑ひである、爾《さう》して料理場に向き『喰る物が無いとな、彼の澤山あるのは何だ』主人『あれは總てお誂へです』客『誰の』主人『先客の』客『先客は何人ある』主人『ハイ、アノ、十――二――人』客『十二人、フム、二十人だッて食ひ切れぬ』云ひつゝ客は坐り直して更《あらた》めて腰を据ゑ『茲《こゝ》は宿屋だらう、此方《こつち》は腹の空た旅人だから、食事をするのだ』
主人《あるじ》は店口で高聲などするを好まぬ、客の耳に口を寄せ『今の中に立去て下さい』全くの拒絶である、放逐である、客は振向て何事かを言返さんとしたが、主人が其の暇を與へぬ、猶も其耳に細語《さゝや》いて『無言《だまつ》てお去り成さい、貴方《あなた》の名も知て居ます、云ひませうか、貴方《あなた》は戎《ぢやん》、瓦戎《ばるぢやん》』戎《ぢやん》、瓦戎《ばるぢやん》と云ふ奇妙な名に、客はギクリと驚いた