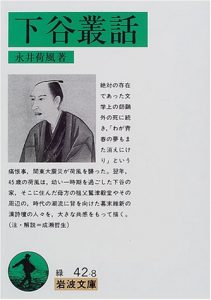◎永井荷風と大沼沈山
「江戸詩人選集」には、以前、紹介した成島柳北とともに、大沼沈山の詩も載っていた。そこで、沈山の詩を繙くとともに、彼を扱った永井荷風の「下谷叢話」を読んでみた。
永井荷風は、森鷗外に傾倒し、師とも仰いでいたようだ。特にその史伝小説に影響され、関東大震災の後、古き東京(江戸)に思いをはせ、「下谷叢話」(青空文庫)を発表した。鷗外のそれとは一味違い、扱う人物が荷風の縁者(鷲津毅堂の外孫)なだけに、思い入れが深い気がする。また大窪詩仏、菊池五山、館柳湾、梁川星巌、成島柳北など江戸後期から末期、明治に至るまでの漢詩人が網羅的に多く登場、彼らのコミュニティも描かれ、そこにも荷風の憧れを感じる。後半になると、維新前後の詩人が多くなり、文字通り「二世」を生きた人生だったが、荷風が取り上げる沈山は、江戸時代の「一世」を送り、残りは余燼ともいえる。荷風は書く。
枕山の依然として世事に関せざる態度は「偶感」の一律よくこれを言尽《いいつ》くしている。
孤身謝俗罷奔馳 孤身俗ヲ謝シ奔馳ヲ罷ム
且免竿頭百尺危 且ツ免ル竿頭百尺ノ危キヲ
薄命何妨過壯歲 薄命何ゾ壮歳ヲ過こユルヲ妨ゲンヤ
菲才未必補淸時 菲才未ダ必ズシモ清時ヲ補ハズ
莫求杜牧論兵筆 求ムル莫カレ杜牧ノ兵ヲ論ズルノ筆ヲ
且檢淵明飮酒詩 且ツ検セヨ淵明ノ飲酒ノ詩ヲ
小室垂幃溫舊業 小室幃《い》ヲ垂レテ旧業ヲ温ム
殘樽斷簡是生涯 残樽《ざんそん》断簡是レ生涯
[語注]奔馳:走り去る 竿頭百尺:更に一歩を踏み出すことを目指す 杜牧:唐の詩人、兵法書に詳しい 淵明:晋の詩人、陶淵明、「飲酒」の詩は有名 幃:とばり 断簡:文書の断片、「断簡零墨」という
わたくしはこの律詩をここに録しながら反復してこれを朗吟した。何となればわたくしは癸亥震災以後、現代の人心は一層険悪になり、風俗は弥いよいよ頽廃《たいはい》せんとしている。此《か》くの如き時勢にあって身を処するにいかなる道をか取るべきや。枕山が求むる莫《なか》れ杜牧《とぼく》兵を論ずるの筆。かつ検せよ淵明が飲酒の詩。小室に幃《い》を垂れて旧業を温めん。残樽《ざんそん》断簡これ生涯。と言っているのは、わたくしに取っては洵《まこと》に知己の言を聴くが如くに思われた故である。
枕山は年いまだ四十に至らざるに蚤《はや》くも時人と相容《あいいれ》ざるに至ったことを悲しみ、それと共に後進の青年らが漫《みだ》りに時事を論ずるを聞いてその軽佻《けいちょう》浮薄なるを罵《のの》しったのである。
飲酒
一
憶我少年日 憶フ我ガ少年ノ日
距今僅廿春 今ヲ距《へだ》ツルコト僅《わず》カニ廿春
當時讀書子 当時ノ読書子
風習頗樸醇 風習頗ル樸醇
接物無邊幅 物ニ接シテ辺幅無ク
坦率結交親 坦率交親ヲ結ビ
儒冠各守分 儒冠各々《おのおの》分ヲ守ル
不追紈袴塵 紈袴ノ塵ヲ追ハズ
今時輕薄子 今時ノ軽薄子
外面表誠純 外面誠純ヲ表ス
纔解弄文史 纔ニ文史ヲ弄スルヲ解シ
開口說經綸 口ヲ開ケバ経綸ヲ説ク
問其平居業 其ノ平居ノ業ヲ問ヘバ
未曾及修身 未ダ曾テ修身ニ及バズ
譬猶敗絮質 譬フレバ猶敗絮ノ質ノゴトク
炫成金色新 炫《くらま》シテ金色ノ新タナルヲ成ス
世情皆粉飾 世情皆粉飾
哀樂無一眞 哀楽一真無シ
只此醉鄕內 只此ノ酔郷ノ内ニ
遠求古之人 遠ク古ノ人ヲ求ム
小兒李太白 小児ハ李太白
大兒劉伯倫 大児ハ劉伯倫
隔世拚同飮 世ヲ隔テテ同飲ニ拚《まか》セ
我醉忘吾貧 我酔ヒテ吾ガ貧ヲ忘レン
[語注]憶我少年日:陶淵明の雑詩「憶う我少壮の時」 樸醇:質素で真面目 坦率:さっぱりして飾り気がない 儒冠、紈袴:儒者が貴族の子弟に取り入る。杜甫「紈袴餓死せず、儒冠多く身を誤る」 敗絮質:ぼろの綿入れのような実情 李太白、劉伯倫:ともに酒豪、劉伯倫は「竹林七賢」の一人 拚:すっかりまかせる
ここで、荷風が割愛した沈山の「飲酒」の二首目を掲げる。
二
春風吹客到 春風《しゅんぷう》客《かく》を吹いて到らしむ
春酒傍花斟 春酒《しゅんしゅ》花に傍《そ》うて斟《く》む
不談天下事 天下の事を談《だん》ぜず
只話古人心 只《ただ》古人の心を話《かた》る
樽空客亦去 樽《たる》空《むな》しくして客《かく》亦《また》去る
月淡海棠陰 月淡くして海棠《かいどう》陰《くら》し
明朝又來飮 明朝《みょうちょう》又《また》来《き》たりで飲め
何勞抱素琴 何ぞ素琴《そきん》を抱《いだ》くろ労《ろう》せん
[語注]明朝又來飮:李白「我酔うて眠らんと欲す卿しばらく去れ。明朝意あらば琴を抱いて来たれ」 素琴:弦のはっていない琴。陶淵明が撫でて楽しんだとある。
枕山がこの「飲酒」一篇に言うところはあたかもわたくしが今日の青年文士に対して抱いている嫌厭《けんえん》の情と殊《こと》なる所がない。枕山は酔郷の中に遠く古人を求めた。わたくしが枕山の伝を述ぶることを喜びとなす所以《ゆえん》もまたこれに他《ほか》ならない。
「天下の事を談ぜず、ただ古人の心をかたる」とは、「紅旗征戎《こうきせいじゅう》吾が事に非ず」(藤原定家「明月記」)にも通じるかもしれないが、沈山や荷風の感慨を額面通りに受け取ってはならず、彼ら独自のイロニーであろう。たしかなことは、時代の風潮に「前向き」なだけが、その人の評価にはならないことである。こうした荷風の江戸末期と大正から昭和にかけてを重ね合わせ、沈山に思いをはせる気持ちは現在にもきっと生かせるだろう。
荷風は、「下谷叢話」を、明治以降についての沈山などの詩作については、その墨を薄くしており、毅堂と沈山の死をもって静かに擱筆する形となる。これまた荷風の見識だろうが、余燼ともいうべき明治に入っての沈山も、世間を確かな眼で眺め、なかなか「熱いもの」を持っているようだが、いずれ、また。
【参考】
・永井荷風「下谷叢話」(岩波文庫、青空文庫)
・「成島柳北 大沼沈山 江戸詩人選集 第十巻」 岩波書店