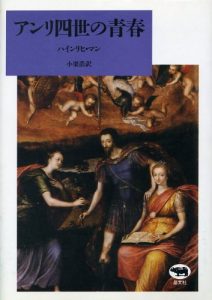◎ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」
◎メリメ「シャルル九世年代記」(岩波文庫)
メリメ(Wikipedia)はいわずと知れた「カルメン」などのフランスの小説家。片方では、歴史家でもあったようだ。そんな彼に、バルテルミーの虐殺をテーマにした歴史小説ともいえる「シャルル九世年代記」がある。
閣下。あなたが八月二十四日の虐殺をご覧になつたら! もしあなたが血で真赤に染つたセーヌ河、雪解けあとの氷片よりも多くの死骸を運んだあの河をご覧でしたら、我等の敵に対してそんなご同情なさらないでせう。私は旧教徒は皆虐殺者だと思ひます
実際は、シャルル九世の登場は少ないが、メリメは、精神的に病んでいた(国王の重圧に耐えかねた、シャルル九世の一言が虐殺を惹起したと示唆する。小説では、肉親や友人の登場で物語が綴られる。その代表として、兄弟がカトリックとプロテスタントに分かれて戦った、ヂョルジュ大尉とベルナール・メルヂー、その恋愛の対象、ディアーヌ夫人、いづれも小説の上での架空人物であろうが、昨日まで、日常の普通の会話をしていただけに、その結末はあまりにも痛ましい。
自分の国を悪く言ふものぢやないよ。我我を包囲するこの軍隊の中には、君の言ふやうな悪人は少いよ。兵士は王の給料が欲しさに鋤鍬を捨てて来た百姓だし、貴族や中隊長は王に忠誠の誓ひをしたから已むを得ず戦つてゐるのさ、恐らくは彼等の方が正当で、我々は叛逆者さ
「寛容」(トレーランス)という言葉は、中世から近世にかけては、現代に比べ、やや低次元に使われていた、と読んだことがある。言葉が正確か自信がないが「仕方なく許す」とでも言おうか?もちろん、その傍らでエラスムスやラブレーなどフマニストが、この言葉に磨きをかけていったが…
医学・生物学の用語に「免疫学的寛容」というのがある。これは、生体内では、抗原と抗体は厳密に一対ではなく、自分とは違う異物には、かなり曖昧な関係があることを指す。片方では、この曖昧さから、免疫がからむいろんな病気が成り立つが、ギリギリのところで、ウィルスや細菌などから防御しているという絶妙のバランスが保たれている。
フランス宗教戦争においては、途中「寛容」が図られたことはあったが、そのバランスが短時間に崩れてしまった。現代に当てはめると、超大国の「悪」を許さないことには、やぶさかでないが、日常的な付き合いの中で、相手を「仕方なく許す」といった「寛容」を活かせる道はないのだろうかと、ふと夢想してみる。