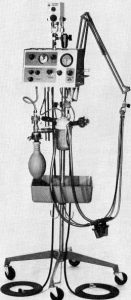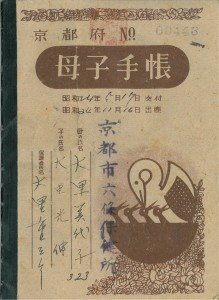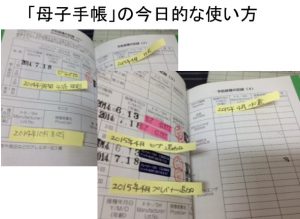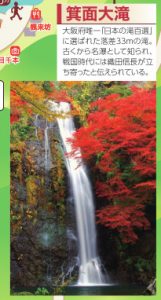◎ハインリッヒ・マン「アンリ四世の青春」
◎堀田善衛「城舘の人」
フランスの16世紀は、後進国とまでは言わないが、どちらかと言えば、ルネッサンスの中心だったイタリアに比して、後塵を拝していたのではないか。また、イデオロギー的にも、手法の是非はともかくとして、ドイツ、スイスなどの新教派の拡大に一歩遅れを取っていたのではなかろうか?例えば初期バロック音楽でも、イタリアなどと比べると、リュート音楽が「主流」で、野暮ったさは否めない。例をあげると、ゴーティエ一家というリュート作曲家一族がいる、その中で、エヌモン・ゴーティエの曲が Youtube にある。後のベルサイユを発信地にした典雅な音楽とは、かけ離れている。これはこれで、別種な素朴ともいうべき趣があるが…こうした社会環境は、これからのストーリーの背景にあったとも思われる。
さて、「バルテルミーの虐殺」を経たその16世紀末のフランス史では、三人のアンリが、その焦点になる。すなわち、アンリ二世(1551-1589)とカトリーヌ・メディシスの子、アンリ三世、カトリック同盟の首領ギーズ公アンリ(1550-1588)とわが主人公、アンリ四世(1553-1610)である。三人とも、最期は悲劇的な結末であったことは痛ましい限りである。
俗っぽいが、三人の関係を、ちょうど同時期の信長、秀吉、家康に比べる向きもあり、アンリ四世は家康に比すこともできようし、強いて言えばが、ギーズ公アンリは信長に、アンリ二世は秀吉に当てることも可能だが、相違点も多々あり、話が続かない。
ともかく、三人の確執は、後の話にひとまず置き、とりあえずは「虐殺」を辛うじて逃れたアンリ四世(アンリ・ナヴァール)に眼をやってみよう。プロテスタントからカトリックへ改宗というアリバイ的な立場を取った、アンリ・ナヴァールだが、ルーブル王宮での半ば幽閉生活には、毎日が心ここにあらずという生活が続くが、足かけ4年で、そこからの脱出に成功する。その逃避行の途中で、モンテーニュとの奇跡とも言うべき二度目の出会いがあった。そして、肝胆相照らす仲となる。これには、アンリ・ナヴァール側に「虐殺から監禁」という痛烈な体験が関係しているのであろう。年長のモンテーニュとしては、それまでも、いやというほど現実の過酷さを体験したことだろうが(機会があれば、これまでのモンテーニュの辿ってきた事柄に触れてみたい)、やっとアンリ・ナヴァールと同じ地平に立つことができた。さすがに、「エセー」には、アンリとの出会いについては書かれてはいないが、現実を凝視する眼がたしかな「エセー」からの引用。
「均衡のとれた中庸の人物を私は愛する。度をこえることは善においてもほとんどいとうべきものだ。」(「エセー 第1巻30章)
また、「エセー」では、ローマの文人の言葉も引く「何事においても熱中は禁物で、徳ですら過ぎれば狂となる。」(ホラーティウス「書簡」)
Omnia vitia in aperto eviora sunt. (アルユル欠陥ハアカラサマ二ナレバヨリカルイ」(セネカ 「エセー」(第2巻31章)
元来「中庸」は、ともすれば、中途半端な「日和見」的な立場と取られがちである。しかし、モンテーニュは醒めている。度を越した善は、ましてやその「強要」は、しばしば多大な損傷をもたらす。モンテーニュが経験したことが、そう語っている。
別に話を拡げるつもりはないが、現在、この時点で係争地で起こっている悲惨な状況を見よ!お互いの「善」「正義」の強要が、子どもや罪なき弱者の命を奪っている。あと幾年いや幾世紀、「度を越えた善、狂となった過ぎた徳」の応酬が続くのだろうか?アンリ四世とモンテーニュとの邂逅が、いくたび繰り返さなければならないのだろうか?
ここまで書いて、半世紀も前のことになるが、高校時代のワンゲル部の後輩が、「ジハードに征く」として、彼の地で生を終えたことを、ふと思い出した。